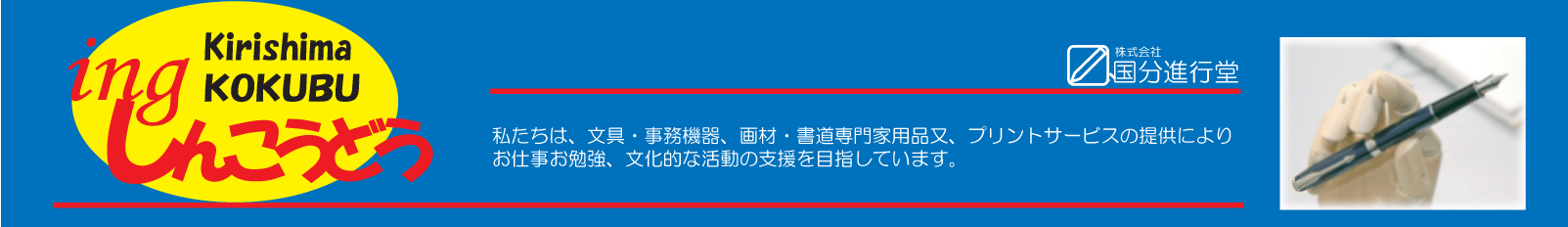

特別連載

古代隼人のいきざまを
ふりかえる
―隼人国成立から1300年―
中村明藏(鹿児島国際大学院講師)
一、隼人の抗戦、その背後の真相は 二、ヤマト政権による隼人崩し 三、まず、薩摩国が成立した 四、大隅国の誕生―難産の末に― 五、隼人国の郡、郷構成のナゾ 六、強いられる苦難、そして抗い― 七、隼人は何を食べていたのか― 八、主食はサトイモ・アワと海・山の幸― 九、『正税帳』から見える隼人国― 十、『山背国隼人計帳』をのぞき見る― 十一、演出された幻影隼人― 十二、土俗から王権服属歌舞へ― 十三、ハヤトの呼び名はどこから― 十四、肥後・豊前国から隼人国へ移住― 十五、隼人たちは何を信仰していたのか― 十六、カミかホトケか、それとも― 十七、どこへ消えた 国府域住民― 十八、古代最大の水田開発か― 十九、めざそう 新しい道を― 二十、女帝と銅鏡 そして清麻呂― 二十一、和気清麻呂、歴史に登場― 二十二、征隼人持節大将軍 大伴旅人― 二十三、旅人の子 家持(やかもち)も薩摩守(かみ)となる― 二十四、隼人正(かみ)になった 大住忌寸三行(いみきみゆき)― 二十五、機を見るに敏 曽君多理志佐(たりしさ)― 二十六、隼人国の信仰・宗教をさぐる― 二十七、「大隅国神階記」に見える神社―
【4、大隅国の誕生】
大隅最大の豪族曽君一族、いな隼人最強といったほうがふさわしい一族曽
君をどう手懐{てなず}けるか、これは朝廷にとっては難題である。
その方策を講ずるように指令された大宰府もその手法に考えあぐねてい
た。そんな折に、大宰府に都から派遣されていた役人(府官)の一人、かれは都
では『日本書紀』の編纂事業に加わっていた人物でもあるが、妙案を口にした。
かつて、中央で権勢を誇っていた蘇我氏に対して、どうその勢力を削{そ}ぐか、
この難題に長期にわたって手を拱{こまね}いていた中大兄{なかのおおえ}皇子らは、武力で争う方策
では困難と見ていたが、ついには相手側勢力の分断策をとったのであった。
蘇我勢力の中心人物、蘇我入鹿{いるか}の従兄弟に当る蘇我倉山田{くらやまだ}石川麻呂を味方
に引き込む案に思いいたった。入鹿と石川麻呂はともに、蘇我氏を最強豪族に盛り上げた馬子{うまこ}の孫に当たる。
馬子は大臣{おおおみ}の地位にあって仏教受容推進策をとり、それに反対する大連{おおむらじ}の
物部守屋{もののべのもりや}と対立していたが、その間に皇位継承問題もからみ、ついに守屋を
倒した。これ以後、それまでの大臣・大連の二頭政治は、蘇我氏の独裁政治となった。
馬子の権勢は、前後に例のない一塔三金堂をもつ法興寺(飛鳥寺)の建立や、聖徳太子と歴史書『天皇記』『国記』
を編纂したこと、また巨大な石を用いた石舞台古墳がその墓といわれていることなどで、垣間見ることができよう。
これらの事業をいつも目の前にして育ったのが、孫の入鹿と石川麻呂であつた。入鹿は、馬子直系の蝦夷{えみし}の子
で、蘇我本宗家を継いでいた。いっぽう石川麻呂は分家ではあるが、蘇我一族では智勇にすぐれた人物として注目さ
れていた。
飛鳥の山田寺はかれが建立したもので、三十年ほど前に寺跡から廻廊などの遺構・遺物が見つかり、現存最古の貴
重な木造遺物とされている。また、奈良「興福寺の仏頭」はこの山田寺の仏像であったが、平安末期のころに興福寺僧
徒によって、飛鳥から奪取されたもので、興福寺にその巨大な頭部が保存されている。これらによっても、本宗家の
法興寺に対抗するかのような山田寺の偉容がしのばれるが、そこに石川麻呂の意気が感じられる。
この石川麻呂に目をつけた中大兄皇子は、かれを味方に引き込み、蘇我氏の勢力を分断する計略をもくろんだので
あった。
そこで、ひそかにこれから断行しようとしているクーデターの一端を石川麻呂に語り、助力を求めたのであった。
その際に、中大兄はクーデター後には、石川麻呂を右大臣の要職につけることを約束した。
この中大兄の計略は石川麻呂の心を動かしたようである。この密約を背景にして、蝦夷・入鹿を抹殺することに成
功したのであった。
乙巳{いつし}の変とよばれるこのクーデターによって、中大兄は大化の改新事業を開始することになり、石川麻呂は約束
通り右大臣になった。しかし乙巳の変から四年後に、かれは自殺に追い込まれた。
 曽君細麻呂が隼人の荒俗を教喩して、外従五位下を授けられた記事は、どこか蘇我倉山田石川麻呂と二重映しに
なるところがある。かれは隼人の土俗風から脱して「細麻呂」と改名したとみられ、みずから都人風を好み貴族まが
いの振る舞いに走ったのではなかろうか、と思われる。また、その後どうなったのか。かれの名は再び史上に現れる
ことはなかった。
曽君細麻呂が隼人の荒俗を教喩して、外従五位下を授けられた記事は、どこか蘇我倉山田石川麻呂と二重映しに
なるところがある。かれは隼人の土俗風から脱して「細麻呂」と改名したとみられ、みずから都人風を好み貴族まが
いの振る舞いに走ったのではなかろうか、と思われる。また、その後どうなったのか。かれの名は再び史上に現れる
ことはなかった。
曽君細麻呂のような人物が、曽君一族のなかから他にも出てきた可能性も否定できない。いずれにしても、細麻呂
の一例からみて、強大な曽君勢力の一角は切り崩されつつあったとみることができよう。
それから三年余り後、七一三年四月に大隅国が日向国から分立した。成立当初は、肝杯(肝属{きもつき})・贈於・大隅・姶?{あいら}
(姶羅)の四郡であった。
とはいえ、すんなりと大隅国が成立したわけではなく、相当の抵抗があっ
たことがわかる、というのは、成立後に「隼賊を討ちし将軍ならびに士卒等戦
陣に功有りし者一千二百八十余人」に勲位を授けるなど、論功行賞の記事(『続目
本紀』)が見えるからである。
行賞にあずかった大量の叙勲者からみて、大隅隼人たちが中央政権側の侵略に対
し、かなり抵抗したことが知られる。しかし、抵抗は挫折し、大隅国は成立をみたの
であった<。
これより前に薩摩国は成立していたので、この年をもって隼人二国が成立し、今
年はそれから千三百年という、記念すべき年になる。
日向国から七一三年に分割され、成立した大隅国の四郡を見ると、北半部の大部分
は贈於郡であり、南半の半島部を主とした地域が三郡となろう。このような四郡の分
布からすると、贈於郡の地域は広大であり、曽君勢力圏が反映されている様相が見
てとれる。
その地域を縮小して、曽君勢力を弱体化していくことが、中央集権のつぎの課題で
ある。その課題に向けての第一の施策は贈於郡の分割である。それも、ただ二分すれ
ば済むのではない。その隣接地に国府を設置して、そこに曽君勢力と対峙するための
相応の態勢を備える必要があった。
その結果が、桑原郡の設置となり、国府所在郡とすることになったのであろう。贈
於郡と桑原郡の境界は天降川{あもりがわ}(旧流で、広瀬川・大津川)とした。
天降川は江戸時代前期に大規模な川筋直しが行われているので、旧流は今の川筋
より東側を流れていたようである。その川筋の西側、鹿児島湾奥部に桑原郡が分置さ
れた。湾奥の海に面した水・陸交通の要衝ともいえる地域である。
また国府は、現在の国分・府中のあたりで、現・祓戸{はらいど}神社、気色{けしき}の杜、向花{むけ}小学
校一帯かと推定されるが、未調査部分が多く、細部については未詳である。それでも近年には気色の杜近くから、土
器片に平安中期とみられるひらがな書きの歌の一部の墨書が見つかっており、国府が所在したことを示す有力なあか
証しとされている。
そのいっぽうで、国府は移動することが西海道(九州)諸国でもしばしば確認されているので、その点も視野に入
れて対処することも必要である。それはひとまずおくとして、桑原郡に置かれた国府での、曽君勢力に対峙する態
勢はどのように備えられたのであろうか。
それについては、大隅国成立の翌七一四年三月につぎのような記事が見える(『続目本紀』)
隼人、昏荒{こんこう}野心にして、憲法に
習はず。因{よ}って豊前{ぶぜん}国の民二百
戸を移して、相勧{すす}め導かしむ
すなわち、隼人は暗く愚かなため、朝廷の法令に従わない。そこで豊前国の
人民二〇〇戸を移住させて指導させたい、というのである。
この記事では、豊前国から隼人国のどこへ移住したのかは明らかではな
い、そこで、移住先を推測してみると、大隅国の国府所在の桑原郡の郷{ごう}名に、
豊前・豊後両国に関係のある地名が見出される。すなわち、大分・豊国・仲川の
三郷は移住者集団の郷の可能性が大きいと推定できそうである。それにして
も二〇〇戸には満たない。というのは郡の下の郷は五〇戸で構成されるか
ら、三郷では一五〇戸にしかならない。
また、当時の一戸は大家族であったから、一戸はほぼ二〇~二五人で、二〇〇戸では四千~五千名にもなる。それ
ほど大量の移住者が計画通りに移動できたのか、筆者は他の情勢も勘案して、少なからず疑問をもっている、このよ
うな移住者集団が薩摩国の場合にも見られたが、それも含めて、あらためて別稿でとりあげたい。
ところで、大隅国に移住した豊前国を主とした移住者集団は、贈於郡から分立した桑原郡で数郷を構成して国府
周辺を警固することも任務として居住したと思われるのであるが、その居住地には以前から住んでいた在来の人び
とが居たはずである。その在来の居住者はどうなったのであろうか。
同じような問題は、かつて薩摩国の国府の地に肥後国からの住民が移住してきた時にも生じたはずであるが、こ
こでも在来の居住者の行方については、史料は何も語っていない。しかし、気にかかることなので、後日推測を交
えてとりあげようと思っている。
いまは、薩摩国に続いて大隅国が成立したことで、ひとまず隼人二国は難産の末になんとか誕生したことを記し
て、話をすすめたい。
ところで、誕生した国の下にはいくつかの郡があり、郡の下にはいくつかの郷があった。一郷は五〇戸で構成さ
れる原則があったことはすでに述べたが、大隅・薩摩両国の郡・郷について一覧しておきたい。
といっても、両国とも成立当初の郡・郷構成は、残念ながら明らかでない。八世紀前半の史料とされている『律書残
篇』に、
薩摩国 郡十三、郷廿五
大隅国 郡五、郷十九
とあるが、この史料はその他の記事に疑問があり、その信憑性については問題がある。ただ、二国
の郡・郷数だけについていえば、一応はこの程度であろうかと思われる。それでも郡名・郷名につ
いては明らかでない。
隼人二国の郡・郷数、および郡・郷名を記した文献は『和名類聚抄{わみょうるいじょうしょう}』(略し
て『和名抄』)である、平安時代の承平年間(九三一~三七年)に成立した最古の百科辞典ともいえる書物で、古代史研究には
貴重かつ便利な内容を備えている。
この『和名抄』によって、大隅・薩摩両国の郡・郷の全体がはじめて一覧できるのであるが、両国ができてから二〇〇年以上も経過
しているので、その間の変化の様相を知ることができないのは残念である。また、郷名などの読み方も記されていない。
その郡・郷名一覧を次回で紹介したい。
次号につづく
一、隼人の抗戦、その背後の真相は 二、ヤマト政権による隼人崩し 三、まず、薩摩国が成立した 四、大隅国の誕生―難産の末に― 五、隼人国の郡、郷構成のナゾ 六、強いられる苦難、そして抗い― 七、隼人は何を食べていたのか― 八、主食はサトイモ・アワと海・山の幸― 九、『正税帳』から見える隼人国― 十、『山背国隼人計帳』をのぞき見る― 十一、演出された幻影隼人― 十二、土俗から王権服属歌舞へ― 十三、ハヤトの呼び名はどこから― 十四、肥後・豊前国から隼人国へ移住― 十五、隼人たちは何を信仰していたのか― 十六、カミかホトケか、それとも― 十七、どこへ消えた 国府域住民― 十八、古代最大の水田開発か― 十九、めざそう 新しい道を― 二十、女帝と銅鏡 そして清麻呂― 二十一、和気清麻呂、歴史に登場― 二十二、征隼人持節大将軍 大伴旅人― 二十三、旅人の子 家持(やかもち)も薩摩守(かみ)となる― 二十四、隼人正(かみ)になった 大住忌寸三行(いみきみゆき)― 二十五、機を見るに敏 曽君多理志佐(たりしさ)― 二十六、隼人国の信仰・宗教をさぐる― 二十七、「大隅国神階記」に見える神社―
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd