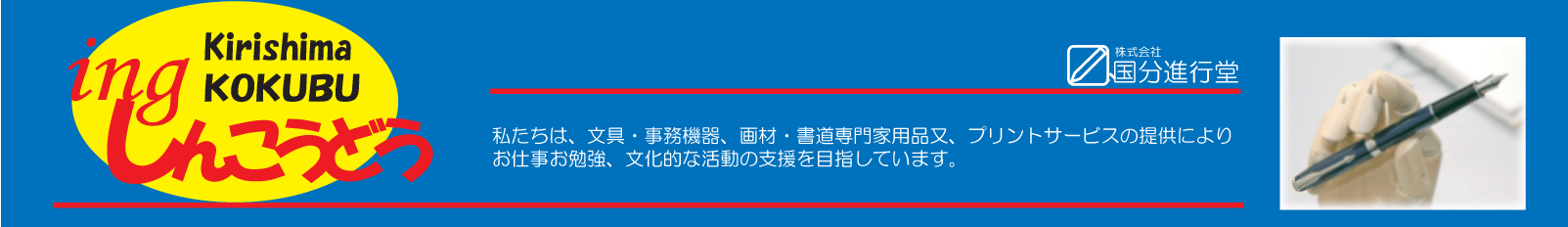

特別連載

古代隼人のいきざまを
ふりかえる
―隼人国成立から1300年―
中村明藏(鹿児島国際大学院講師)
一、隼人の抗戦、その背後の真相は 二、ヤマト政権による隼人崩し 三、まず、薩摩国が成立した 四、大隅国の誕生―難産の末に― 五、隼人国の郡、郷構成のナゾ 六、強いられる苦難、そして抗い― 七、隼人は何を食べていたのか― 八、主食はサトイモ・アワと海・山の幸― 九、『正税帳』から見える隼人国― 十、『山背国隼人計帳』をのぞき見る― 十一、演出された幻影隼人― 十二、土俗から王権服属歌舞へ― 十三、ハヤトの呼び名はどこから― 十四、肥後・豊前国から隼人国へ移住― 十五、隼人たちは何を信仰していたのか― 十六、カミかホトケか、それとも― 十七、どこへ消えた 国府域住民― 十八、古代最大の水田開発か― 十九、めざそう 新しい道を― 二十、女帝と銅鏡 そして清麻呂― 二十一、和気清麻呂、歴史に登場― 二十二、征隼人持節大将軍 大伴旅人― 二十三、旅人の子 家持(やかもち)も薩摩守(かみ)となる― 二十四、隼人正(かみ)になった 大住忌寸三行(いみきみゆき)― 二十五、機を見るに敏 曽君多理志佐(たりしさ)― 二十六、隼人国の信仰・宗教をさぐる― 二十七、「大隅国神階記」に見える神社―
【二十二、征隼人持節大将軍 大伴旅人―】
七二〇年に大隅国守(くにのかみ)が隼人によって殺害され、以後一年数ヵ月にわたって隼
人が朝廷に抵抗した事件はよく知られている。
そのとき、朝廷が隼人を制圧するため大軍を派遣したが、その大軍を率い
た人物が大伴宿祢旅人(すくねたびと)であった。旅人は当時中納言で中務卿(なかつかさきょう)も兼ねていた
から、政府の要職にあったのであるが、この隼人の抗戦勃発で「征隼人持節
大将軍」に任命されて九州の南端までやってきたのである。
じつは、大伴旅人はこの時はじめて隼人と接したのではなかった。この抗
戦より十年前の七一〇年正月元日の朝廷の儀式で、旅人は隼人を率いていた。
この正月元日の儀式は藤原宮では最後にあたり、三か月後には都は平城京に
移っている。その最後の朝賀はつぎのようであった。
女帝の元明天皇が大極殿(だいぎょくでん)に出御(しゅつぎょ)さ
れ、臣下から拝朝の礼を受けた。そのとき隼人・蝦夷(えみん)も参列していた。この
儀式で左将軍をつとめていた大伴旅人は、右将軍・副将軍とともに皇城門
(朱雀・すざく門)の外で東西に分れて陳列していた騎兵の中を、隼人・蝦夷を率いて
行進したのであった。
このように、大伴旅人は都が藤原京にあった時期から隼人に接触してい
た。その点では、当時の有力官人としては、隼人と縁のあるまれな存在であっ
た。そこで、大伴旅人という人物と、その周辺についてさぐってみたい。
大伴氏は、朝廷に早くから仕えた有力な軍事氏族で、天皇・宮廷の警護な
どにあたった。古代では、世襲的職業グループを「伴(とも)」といい、伴を率いて朝廷
に奉仕する首長を「伴造(とものみやつこ)」といっていた
が、大伴とはその中の最有力者の意であろうと思われる。始祖伝承では、天
孫ニニギノミコトが高千穂峰に天降った際に随伴・先導していた天忍日(あめのおしひ)命が
祖にあたると伝えられているので、天皇家に奉仕する家柄としての伝えも古
い。
この天孫降臨の伝承でも、大伴氏は南部九州の地とつながっていることに
なる。それは、やはり天皇家と密着していた伝承をもつことの一面でもあろう。
しかし、大伴氏の出自の地は摂津(大阪市)から和泉(堺市)の地域で大阪湾沿
岸部とみられているので、天皇家の出自の地である大和とは少し距離がある。
おそらく、四世紀後半から五世紀にかけて、天皇家の勢力が大阪湾沿岸部に
進出した時期に、大伴氏は天皇家に接近し、その配下に入ったのであろう。
以後、大伴氏は勢力を伸張させて、五世紀後半の雄略朝になると、一族の
大伴室屋(むろや)が大連(おおむらじ)に任命されるまでに
なった。大連は大臣(おおおみ)と並んで天皇の下で政権を掌握する地位であった。とり
わけ、朝廷の軍事面で一族の佐伯氏とともに活躍した。
ところが、六世紀に入ると、室屋の孫金村(かじむら)が大連として継体天皇の擁立に
力を発揮したいっぼうで、朝鮮半島政策で失敗したことから、同じ軍事氏族
の物部(もののべ)氏などからの弾劾で失脚し、政界の要職の座を物部・蘇我両氏に奪わ
れることになった。
以後の大伴氏は七世紀の半ばまで、政権の第一線から離れていたが、七世
紀の半ばに大伴長徳(ながとこ)が右大臣になったことから、大伴氏の勢力は回復してき
た。また、長徳の弟馬来田(まくだ)や吹負(ふけい)らが壬申の乱(じんしんのらん)(六七二年)で大海人皇子に
味方して活躍したことから、天武朝になると家運が隆盛した。それらを背景
にして、八世紀になると旅人が登場してきたのであった。
大伴旅人は六六五年に生まれている。天智天皇の治世であった。天皇は旅人の出生六年後
には没しており、死没の翌六七二年には天智の子の大友皇子と天智の弟の大
海人皇子が皇位をめぐって争う、壬申の乱が起こっている。
しかし、このころまでのことについては旅人はいまだ幼少であったから、記
憶は十分には残っていないのでは、と推察している。それでも、彼の成長期はか
つての名門軍事氏族・大伴氏の復活期に当たっているので、かれも将来を期
待される環境にあったとみられる。
旅人の父安麻呂は、長徳の子であった。したがって、旅人は父から長徳や
壬申の乱で活躍した一族の話を聞かされて育ったはずである。安麻呂自身も
壬申の乱では叔父の吹負に従って、大海人皇子側について相応の働きをした
ことから以後出世し、七〇五年には大納言になり大宰帥(そち)を兼務した。位階も
正三位に進み、このころでは石上麻呂(いそのかみまろ)や藤原不比等(ふひと)につぐ重臣であったが、
七一四年に没し、従二位を贈られている。
このような旅人の父祖の活躍をみると、かつて大連にまで登りつめた五~
六世紀の室屋・金村ほどの重職ではないものの、七世紀後半から八世紀初め
には、かなりの要職を務める者が一族から出ていたといえよう。そのあとを
継いで大伴旅人は登場してくるのである。
ところが、すでに述べた七一〇年の正月元日の儀式で、左将軍として騎兵と
隼人を率いる以前の大伴旅人について史書には、かれについての記録が見え
ないのである。生年からみると、すでに四六歳になっているし、位階も五位に
昇っていたとみられるので、地方の国守などを歴任していたとしても不合理で
はないのであるが。
旅人は翌七二年には従四位下、さらに七一五年に従四位上を授与され、
同年中務卿(なかつかさぎょう)に任じられている。中務省は八省のなかでも最重要省で、天皇の
側近に侍従し詔勅の起草などや上表の受納などをつかさどる役所であり、
卿は省の長官であった。したがって、現代の大臣に相当するが、大臣の中でも
筆頭に近い地位にあったとみられる。
さらに七一八年には中納言にも任じられている。この職も天皇に近侍して、
奏上や宣下をつかさどるので、中務省の延長線上位にある。ところが、旅人は
中納言になっても中務卿を兼ねていたので、天皇に最も近い要職にあったと
見ることができよう。
このような要職にありながら、七二〇年に大隅国守陽侯史(やこのふひと)麻呂が殺
害されると、征隼人持節大将軍に任じられたのであった。この任命は、大伴氏
が古来朝廷の軍事を担当してきた名族という氏固有の伝統によるのであろ
う。
「持節」とは、隼人を征討する将軍に天皇が節刀を賜与して、天皇の権限を
代行することを容認したことを意味している。その節刀を持って隼人征討
にあたったのであり、この間の旅人の行為・行動は天皇の代行として、すべて認
められることであった。
隼人の国守殺害は、天皇・朝廷にとっては屈辱的反逆行為であったから、大
宰府から事件が急報されると、数日のうちに征討軍を編成して西海道(九
州)に向かわせている。急遽任命された征討軍の主脳は、大伴旅人を大将軍と
し、以下に副将軍二名であり、律令のなかの軍防令(ぐんぼうりょう)の規定からすると、この
構成での出兵は兵士一万人以上の場合に相当する。
それらの兵士の大半は、大宰府に急使を遣わして、大宰府管下の西海道諸
国から徴集されたとみられる。大挙しての出兵の目的地は大隅国府のある
鹿児島湾奥部であったから、西海道の東・西沿岸部にそって征討軍は南下し
たとみられる。となると、東岸部では日向国府が、西岸部では薩摩国府が兵帖(へいたん)
基地とされ後方拠点になったとみられる。
都を発した大伴旅人大将軍は大宰府で情報を収集し、兵力を整えた後に
西岸部側を南下して薩摩国府を拠点として指揮をとったと推察される。朝
廷では、戦闘は短期間で、勝利で終わると考えていたとみられる。というの
は、中央で要職にあった大伴旅人を大将軍に任命していることから、長期戦
は予測していなかったとみられる節があるからである。
ところが、予測ははずれて隼人の強い抵抗にあい、長期にわたって苦戦を
強いられることになった。旅人は都を出て約半年後の七二〇年八月になる
と、いまだ勝利への見通しがつかぬまま、副将軍を残して帰京することに
なった。年齢も五六歳であったことから、長期の野戦は身体にこたえたこと
もあったのであろう。いっぽうでは、やはり朝廷での要職を長期にわたって空
けることができなかったと見るべきであろうか。
隼人の抵抗はその後も続き、翌七二一年七月になって副将軍らはよ
うやく帰京し、「斬首獲虜合わせて千四百余人」と勝利の戦果を報告して
いる。
大伴旅人はその後、隼人と関わることはなかったのであろうか。じつは、隼
人との関係は断続的にその後も見出せる。旅人は七二八年ごろ、大宰帥(そち・大
宰府の長官)になっている。それより四年前にすでに正三位に昇叙しているの
で、いまさらという感じがする。大宰帥は従三位相当官で旅人より下位の官
職であり、六四歳にもなっていたので、当時としてはかなりの高齢である。都
から離れた大宰府に異例の異動で、しかもこの年になって、なぜという思いで
あったろう。
おそらく、背後には藤原氏による政略があったとみられる。その翌年には、
長屋王の変がおこっているからである。
長屋王は天武天皇の孫で、聖武天皇即位とともに左大臣となり、政権の最有
力者であったが、藤原氏の陰謀の犠牲となって自死した。その直後に、藤原不
比等(ふひと)の娘光明子(安宿媛・あすかひめ)が、それまでの伝統を破り臣下の出身にしてはじ
めて皇后となった。光明皇后の出現で、藤原氏はいっそう勢力を振るうように
なった。大伴旅人が大宰府に遠ざけられたのは、かれが長屋王に近い存在と
見られていたことが主因であろうか。
大宰府赴任後、旅人は妻の大伴郎女(いらつめ)に病没されている。都から遠くに離さ
れたうえに、妻を失なって、ときに酒に寂しさをまぎらす日もあったようであ
る。『万葉集』には、「大宰帥大伴卿、酒を讃(ほ)むる歌十三首」が残されている。そ
の中の二首だけをとりあげる。
今(こ)の世にし楽しくあらば来む生(よ)には轟にも鳥にもわれはなりなむ (三四八)
生者(いけるもの)つひにも死ぬるものにあれば今(こ)の世なる間(ま)は楽しくをあらな (三四九)
人生の寂しさと、諦観こもごもを感じさせる歌である。十三首の中には、も
ちろん酒を好み讃えた歌もあるが、この二首にこそ旅人の当時の心根が読み
とれそうである。
大伴旅人が大宰帥在任中に隼人に関わるできごとがあった。それは、朝廷
が隼人の地域に班田制を施行するように大宰府に要請したことである。じ
つは、七二九年に朝廷は全国の口分田を悉(ことごと)く収公して、あらためて班田を行
なうように指示していた。いわゆる班田収授の法は、年月を経ると不都合が
目立つようになっていたのである。ある地域では田地に不足が生じ、ある地域
では同じ家族の成員でも各人の田地の所在地が遠くかけ離れていたり、また
田地の肥沃(ひよく)度に大差があるなど、さまざまな支障が生じていた。そこで、朝廷
では田地(口分田)を一旦収公して、あらためて班田を行なおうとした。その
際、班田制をいまだ実施していなかった隼人の地域にも、その採用をせまっ
たのであった。
この朝廷の要請に対し、当時大伴旅人が長官(帥)をつとめていた大宰府
は、つぎのように回答している。
①大隅・薩摩両国の百姓は建国以来、いまだ班田を実施していない。
②百姓の中には田を所有している者もあるが、それらはすべて自力で開いた墾田であり、その田を
代々受け継いで耕作しているので、それを改めて動かすことを願っていない。
③このような現状からして、もし班田収授を実施したら、おそらくやかましい訴え事が多発すること
であろう。
この回答をうけて、七三〇年三月になると、朝廷では班田制の採用をあきらめて、従来通りのままとしている。
隼人居住地域は山地・丘陵が多く、平地が少ない。その狭少な平地は火山
灰性土壌におおわれて肥料となる有機成分が少ない。そのうえ、地質は水
分の浸透性が高く保水力が弱いので、とりわけ水田不適地が多い。、
このような耕作地の状況を、大伴旅人はかつて征隼人大将軍として十年前
に現地に赴いた経験からもよく知っていたから、この地域に班田制を適用す
ることは、いまだ不可能と判断したのであろう。この地域に班田制が採用さ
れたのは、それからさらに七〇年後のことであった(延暦十九年、八〇〇年)。
ところで、大伴旅人には薩摩の地を詠(よ)んだ歌が『万葉集』にある。
隼人(はやひと)の湍門(せと)磐(いはほ)も年魚(あゆ)走る
吉野の瀧になほ及(し)かずけリ (九六0)
この歌の前詞に「帥大伴卿の、遥かに吉野の離宮を思ひて作る歌一首」とあ
る。歌の大意は、隼人の薩摩の湍門(瀬戸)の巨岩も、年魚の走る大和吉野の
宮滝の激流の光景にはやっぱり及ぼないなあ、というのである。
隼人の湍門とは、本土と長島の間の急流で知られる、いわゆる黒之瀬戸で
ある。大宰帥が管内各地を巡視するのは、職務としては十分考えられること
であるから、その折に詠んだというのが定説である。しかし、すでに六五歳前
後にもなっていた大伴旅人が黒之瀬近くまで遠出したとはその体力からして
考えにくいので、おそらく七二〇年の征隼人大将軍として南下したときの、
黒之瀬戸の激流を思い出しての一首だろうと思う。また、この湍門を関門海
峡の早靹(はやとも)瀬戸とする説もあるが、それは当たらない。
この一首の歌意には、都から遠ざけられている旅人の心境が読みとれそう
である。かつて遊んだ大和吉野の宮滝への懐旧の念がつのるいっぽうで、隼人
の地を讃(ほ)めたくないという真意があっての歌とみられるからである。
大伴旅人は七三〇年に大納言に任じられて上京しているが(大宰帥はそ
のままか)、翌年には従二位で没している。六七歳であった。中央官人・名族で、
これほど隼人と深くかかわった人は、ほかには見出せない。
一、隼人の抗戦、その背後の真相は 二、ヤマト政権による隼人崩し 三、まず、薩摩国が成立した 四、大隅国の誕生―難産の末に― 五、隼人国の郡、郷構成のナゾ 六、強いられる苦難、そして抗い― 七、隼人は何を食べていたのか― 八、主食はサトイモ・アワと海・山の幸― 九、『正税帳』から見える隼人国― 十、『山背国隼人計帳』をのぞき見る― 十一、演出された幻影隼人― 十二、土俗から王権服属歌舞へ― 十三、ハヤトの呼び名はどこから― 十四、肥後・豊前国から隼人国へ移住― 十五、隼人たちは何を信仰していたのか― 十六、カミかホトケか、それとも― 十七、どこへ消えた 国府域住民― 十八、古代最大の水田開発か― 十九、めざそう 新しい道を― 二十、女帝と銅鏡 そして清麻呂― 二十一、和気清麻呂、歴史に登場― 二十二、征隼人持節大将軍 大伴旅人― 二十三、旅人の子 家持(やかもち)も薩摩守(かみ)となる― 二十四、隼人正(かみ)になった 大住忌寸三行(いみきみゆき)― 二十五、機を見るに敏 曽君多理志佐(たりしさ)― 二十六、隼人国の信仰・宗教をさぐる― 二十七、「大隅国神階記」に見える神社―
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd