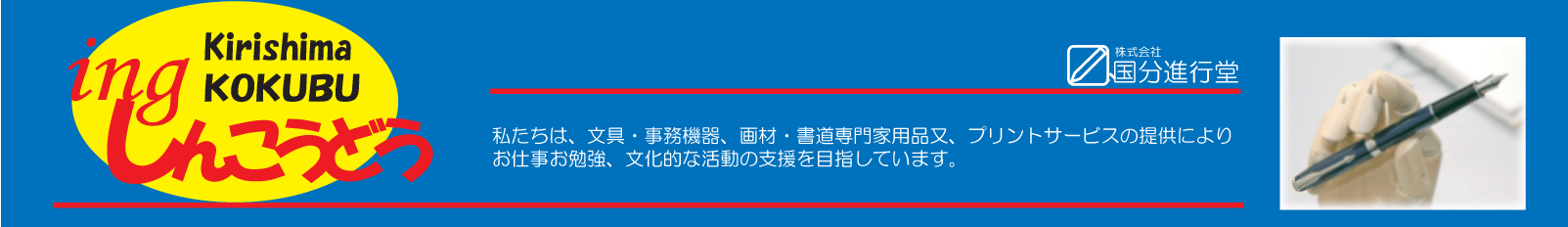

特別連載

古代隼人のいきざまを
ふりかえる
―隼人国成立から1300年―
中村明藏(鹿児島国際大学院講師)
一、隼人の抗戦、その背後の真相は 二、ヤマト政権による隼人崩し 三、まず、薩摩国が成立した 四、大隅国の誕生―難産の末に― 五、隼人国の郡、郷構成のナゾ 六、強いられる苦難、そして抗い― 七、隼人は何を食べていたのか― 八、主食はサトイモ・アワと海・山の幸― 九、『正税帳』から見える隼人国― 十、『山背国隼人計帳』をのぞき見る― 十一、演出された幻影隼人― 十二、土俗から王権服属歌舞へ― 十三、ハヤトの呼び名はどこから― 十四、肥後・豊前国から隼人国へ移住― 十五、隼人たちは何を信仰していたのか― 十六、カミかホトケか、それとも― 十七、どこへ消えた 国府域住民― 十八、古代最大の水田開発か― 十九、めざそう 新しい道を― 二十、女帝と銅鏡 そして清麻呂― 二十一、和気清麻呂、歴史に登場― 二十二、征隼人持節大将軍 大伴旅人― 二十三、旅人の子 家持(やかもち)も薩摩守(かみ)となる― 二十四、隼人正(かみ)になった 大住忌寸三行(いみきみゆき)― 二十五、機を見るに敏 曽君多理志佐(たりしさ)― 二十六、隼人国の信仰・宗教をさぐる― 二十七、「大隅国神階記」に見える神社―
【十二、土俗から王権服属歌舞へ】
隼人が六年相替などの朝貢で「風俗歌舞」を奏上していたことは、『続日本
紀』に散見している。その歌舞が隼入の土俗的なものであろうことは推測でき
ても、歌舞の実態を具体的には知り得ない。
それでも、わずかな手がかりはある。それは、『日本書紀』の日向神話で一書(あるふみ)
が伝える隼人の祖の服属の話である。そこでは隼人の祖(兄の海幸彦)は、天皇家の祖(弟の山幸彦)に対して、「俳優
者(わざおぎひと)」になることを誓い、著犢鼻(たふざぎ)(ふんどし)をして、赤土で掌(てのひら)と顔に塗り、
足をあげて踏み歩いて、溺(おぼ)れた苦しみのまねをして、潮(しお)がしだいに
満ちて足を浸(ひた)した時には、つま先立ちをし、膝(ひざ)まで浸した時には足
を挙(あげ)げ、股(もも)まで浸した時には走り回り、腰まで浸した時には腰をな
でる。また腋(わき)まで浸した時には手くびを胸に置き、頸(くび)まで浸す時には手
を挙げてひらひらす。
「この一連のしぐさは、今に至るまで、かつて絶えることなし」と記している。
この一連のしぐさが、隼人の舞のようすを伝えるものであり、服属儀礼の様相を語ったものとされてる。このし
ぐさが「今に至るまで、絶えることなし」とあるのは、『日本書紀』の編纂・成立の時期を考えると、八世紀初頭まで
の状況であろうか。
この記事によると、ほとんどはだか同然の身体に、顔や手に赤土を塗り、潮が満ちてくるにしたがい、海水に溺
れて苦しむ。そのようなしぐさが、隼人の天皇に対する服属の舞に見られるという。
これが「風俗歌舞」といわれる、隼人の土俗の舞に近いものであるとすると、『延喜式』隼人司条で、朝廷の儀式の
場での隼人の服飾などとは大きな隔たりがある。
そこには、天皇・官人たちを前にした晴の場での、かなり演出された隼人たちの姿が浮かび上がってくるようであ
る。
そのようすを想像すると、最近見られる大ホールのはなやかな舞台で、農・漁村の古い伝統を持つ芸能が演じられ
る時に、農・漁村の本来の労働着とは思われない、きらびやかな衣装を身に着けて演じられる、その容姿にどこか共
通したものがある。
そこでは、土着・土俗が失われ、観客に好まれる色もの、そして大もの小ものの道具が仕立てられ、現実とかけ離
れた虚構が演じられている。そのような舞台を見ていると、千数百年前の、朝儀での隼人の姿と二重写しになる。
『延喜式』隼人司状の隼人の服飾では、「白赤木綿(ゆふ)の耳形鬘(ばん)」という髪飾りや「緋帛(ひはく)の肩巾(ひれ)」がとりわけ目立ってい
る。前者は色々想像することはできても、他に類例を求め得ないものである。後者の肩巾(領巾とも)の類例はかなり
見出せる。それでも気になるのは前者の「赤」と後者の「緋帛」の赤色である。
そこで、ここでは「緋帛の肩巾」についてとりあげてみよう。この肩巾の長さは「五尺」(一五〇㎝)ともあり、肩か
ら両胸前に垂らすショール状のものである。肩巾は隼人特有のものではなく、古代では利用例が広く見出される。
たとえば、『万葉集』巻五には、
海原の沖行く船を帰れとか 肩巾振らしけむ松浦佐用比売(まつらさよひめ)(八七四)
という歌がある。これは朝鮮半島に出兵する大伴狭手彦(さでひこ)と松浦佐用姫との悲
恋伝説にもとついて作られた歌であり、佐用姫が振った肩巾には、沖行く船を引き戻す呪力が期待されている。
また、『古事記』によると、スサノオの娘スセリ姫は、恋人のオオナムチが父の策略によって、蛇の室に閉じ込めら
れた危難を救うため、「其(そ)の蛇咋(く)はむとせば、此(こ)の比礼(肩巾)を三たびふりて、打ち撲(はら)ひ
たまへ」といって蛇をはらい、ついで蜈蚣(むかで)・蜂も比礼ではらっている。
この二例では女性が身につけている肩巾は、護身のためにつけるものであり、
呪力を発揮するものであった。
つぎに、肩巾の色についてみると、
『万葉集』のつぎのそれぞれの歌が参考になろう。まず、
秋風の吹きただよはす白雲は たなばたつ女(め)の天つ肩巾かも(二〇四一)
とよんでいる歌である。この歌では、白雲は織女(たなばたつめ)の肩巾、とよんで
いるところからすると、肩巾は白雲のように白いものだとする古代の人びとの感
覚がそこにあろう。
また、歌では肩巾が「𣑥」というコウゾで作った木綿(ゆふ)を枕詞に使い、「𣑥肩巾」が
しばしば使われている。
𣑥肩巾の鷺坂(さぎざか)山の白つつじ 吾には染はね妹に示さむ(一六九四)
𣑥肩巾の白濱波の寄りあへず 荒ぶる妹に恋ひつつぞをる(二八ニニ)
などの歌があり、肩巾は「鷺」「白」「白濱」にかかるもので、ここでも白いものであった。
ところが、朝廷での儀式で隼人たちが身につけるのは「緋帛」という赤い絹の肩巾であり、女性に限らず、男性も身につけ
ていた。その源流は、さきの服属隼人の土俗、赤土を顔や手につけて踊る、そこに見ることができ、朝儀ではそれが都人・官人
たちに受けるように、はなやかに演出されているように思われる。
 つぎに、隼人の吠声について見てみよう。吠声についても『日本書紀』の日向神話を語った一書(あまふみ)に、隼人の服属に次いで
「諸(もろもろ)の隼人たち、今にいたるまで天皇の皇居の傍(そば)を離れずして、代(よよ)に吠(ほ)ゆる狗(いぬ)にな
りて仕えまつる者なり」と記している。
つぎに、隼人の吠声について見てみよう。吠声についても『日本書紀』の日向神話を語った一書(あまふみ)に、隼人の服属に次いで
「諸(もろもろ)の隼人たち、今にいたるまで天皇の皇居の傍(そば)を離れずして、代(よよ)に吠(ほ)ゆる狗(いぬ)にな
りて仕えまつる者なり」と記している。
この『日本書紀』の記事からしても、狗の鳴き声にも似た吠声は、同書の編纂・成立までの時期には、すでに発せられ
ていたようである。それは、「万葉集」のつぎの歌によっても知ることができる。
隼人(はやひと)の名に負(お)ふ夜声いちしろく わが名は告(の)りつ妻(つま)と恃(たの)ませ(二四九七)
という歌である。そこでは、隼人の有名な夜声のようにはっきりと、私は自分の名を告げましたので、妻として頼み
にしてください、と歌っている。この夜声は吠声にほかならない。その吠声もまた呪力があるとされていたことは、
すでに述べた通りである。
ここで、吠声に関連した習俗と、『万葉集』のさきの歌に関連して、余聞を少し。その一つは沖縄で聞いた話である。
沖縄のある地域では、夜外出した主人が帰ってくると、家に入る前に豚小屋に行き、豚を鳴かせるというのであ
る。そうすると、外から身についてきた邪気・邪霊が鳴き声で払われて、清浄な身体になって帰宅できるという。この
話は隼人の吠声に通じるものがあって、興味深かった。
もう一つは、隼人の夜声を歌った後半の部分に、「わが名は告りつ妻と恃ませ」とあることである。すなわち、女性
が自分の名を相手に告げるときは、妻となることを意味している、というのである。
そういえば、古代の女性の名は伝わらない場合が多い。文学史に名を残すほどの女性であっても、『蜻蛉(かげろう)日記』の
著者は藤原道綱の「母」であり、『更級(さらしな)日記』の著者は菅原孝標(たかすえ)の「娘」であり、名は不明である。作品がもっと著名な場
合でも、『源氏物語』の著者紫式部、『枕草子』の著者清少納言は通称であって、本名は不詳である。余聞はこの辺で一応は止めておきたい。
これまでに見てきたように、隼人は朝廷で異装をさせられ、いわば「見せ物」とされていた観がある。それは反面
において、天皇権力が南辺の領域の蛮族にまでおよんでいることを誇示する効果をねらった「見せ物」でもあった。
そのような、「見せ物」的隼人の始源をさがすと、七一〇年正月元日の朝賀の儀式の記事が目に留まる。そこには
「天皇(元明)大極殿(だいごくでん)に出御(しゅつぎょ)して臣下たちの朝賀を受ける。隼人・蝦夷たちも参
列す。左将軍大伴旅人・副将軍穂積老(ほづみのおゆ)、右将軍佐伯石湯(さえきのいわゆ)・副将軍小野馬養(おののうまかい)など
が皇城門の外の朱雀(すざく)路(宮城正門前の大路)に東西に分れて騎兵が並ぶ中を、隼人、蝦夷を率いて進む」とある。
いかにも仰々(ぎょうぎょう)しい行進での隼人・蝦夷の入場である。率いる左将軍大伴旅人は軍事氏族として著名な大伴氏の氏
上(うじのかみ)であったし、右将軍、・副将軍らも、大伴氏に準ずる家柄の正副将軍たちであった。
この元日・朝賀の式は藤原宮では最後の儀式であり、二ヶ月後には奈良平城京に遷都し、新しい宮殿での諸儀式
が行われることになっていた。その新宮での諸政に夢をかけた元明女帝の期待に、国土の南辺・北辺の異族、隼人・蝦夷の入場行
進は十分に応えるものであったと思われる。
その平城宮での、七一五年元日の儀式には新しい異族たちが参列していた。隼人にかわって南島人の参列である。この儀式には、
皇太子(後の聖武天皇)もはじめて礼服を着て拝朝したが、陸奥・出羽の蝦夷と並記されたのは、南島の奄美はいうまでもなく、沖縄
諸島の久米島さらに石垣島の人びとであった。
南島のこれらの島々がすべて支配領域ではないが、朝貢する人びとの範囲は、隼人居住地よりはるかに南に伸びていた。新しい異
族の元日儀式参加に、元明天皇は満足の意を示したであろう。記事には「元日の儀式に、鉦(かね)・鼓(つずみ)を用い
るのは、これより始まる」とあり、まさに鳴物(なりもの)入りの歓迎であった。
以後も隼人は個別の集団として、六年相替の朝貢をつづけ、風俗の歌舞を奏上していた。その朝貢は九世紀初頭まで続行された
が、南島人の朝貢は七二七年を最後に消えている。
諸儀式において、天皇の権威維持を支えたのは、以後『延喜式』隼人司の隼人たちだけであった。
一、隼人の抗戦、その背後の真相は 二、ヤマト政権による隼人崩し 三、まず、薩摩国が成立した 四、大隅国の誕生―難産の末に― 五、隼人国の郡、郷構成のナゾ 六、強いられる苦難、そして抗い― 七、隼人は何を食べていたのか― 八、主食はサトイモ・アワと海・山の幸― 九、『正税帳』から見える隼人国― 十、『山背国隼人計帳』をのぞき見る― 十一、演出された幻影隼人― 十二、土俗から王権服属歌舞へ― 十三、ハヤトの呼び名はどこから― 十四、肥後・豊前国から隼人国へ移住― 十五、隼人たちは何を信仰していたのか― 十六、カミかホトケか、それとも― 十七、どこへ消えた 国府域住民― 十八、古代最大の水田開発か― 十九、めざそう 新しい道を― 二十、女帝と銅鏡 そして清麻呂― 二十一、和気清麻呂、歴史に登場― 二十二、征隼人持節大将軍 大伴旅人― 二十三、旅人の子 家持(やかもち)も薩摩守(かみ)となる― 二十四、隼人正(かみ)になった 大住忌寸三行(いみきみゆき)― 二十五、機を見るに敏 曽君多理志佐(たりしさ)― 二十六、隼人国の信仰・宗教をさぐる― 二十七、「大隅国神階記」に見える神社―
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd