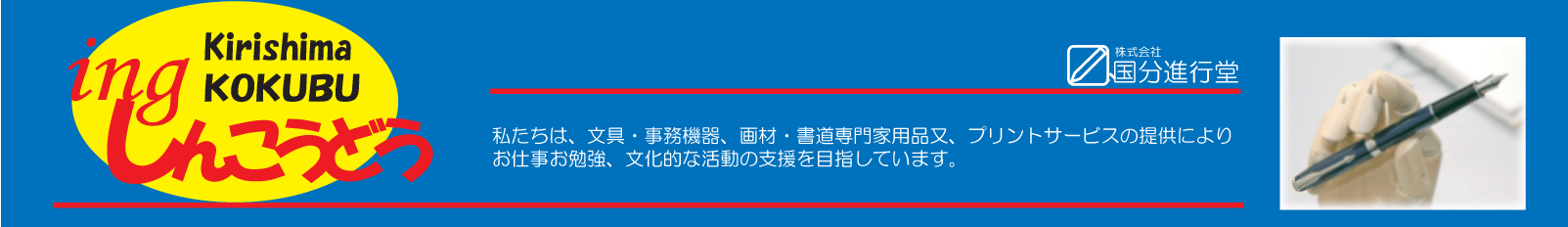

特別連載

古代隼人のいきざまを
ふりかえる
―隼人国成立から1300年―
中村明藏(鹿児島国際大学院講師)
一、隼人の抗戦、その背後の真相は 二、ヤマト政権による隼人崩し 三、まず、薩摩国が成立した 四、大隅国の誕生―難産の末に― 五、隼人国の郡、郷構成のナゾ 六、強いられる苦難、そして抗い― 七、隼人は何を食べていたのか― 八、主食はサトイモ・アワと海・山の幸― 九、『正税帳』から見える隼人国― 十、『山背国隼人計帳』をのぞき見る― 十一、演出された幻影隼人― 十二、土俗から王権服属歌舞へ― 十三、ハヤトの呼び名はどこから― 十四、肥後・豊前国から隼人国へ移住― 十五、隼人たちは何を信仰していたのか― 十六、カミかホトケか、それとも― 十七、どこへ消えた 国府域住民― 十八、古代最大の水田開発か― 十九、めざそう 新しい道を― 二十、女帝と銅鏡 そして清麻呂― 二十一、和気清麻呂、歴史に登場― 二十二、征隼人持節大将軍 大伴旅人― 二十三、旅人の子 家持(やかもち)も薩摩守(かみ)となる― 二十四、隼人正(かみ)になった 大住忌寸三行(いみきみゆき)― 二十五、機を見るに敏 曽君多理志佐(たりしさ)― 二十六、隼人国の信仰・宗教をさぐる― 二十七、「大隅国神階記」に見える神社―
【二十三、旅人の子 家持(やかもち)も薩摩守(かみ)となる】
大伴家持は、旅人の長男である。次弟には書持(ふみもち)がいる。兄弟ともに歌人で
あるが、残された歌の数からすると、書持は家持にはるかにおよばない。家持
の生年は七一六年と一応はしておくが、一説によると七一七年、七一八年として
いるので、一・二年はずれる可能性もある。いずれにしても、父の旅人の五十歳
過ぎてからの後継男子であったから、旅人にとってはおそらく待望の男子誕
生であったと思われる。
したがって、幼少時は父の赴任地であった大宰府にも同行していたと思わ
れる。そうであったとすれば、西海道はかれにとっては思い出の地であったが、
そこで母を失くしてもいるので、寂しい回想の地でもあったのであろう。
その家持が『続日本紀』に登場してくるのは七四五年に従五位下を授け
られたときで、三〇歳でようやく貴族の仲間入りをしたので、史書にようや
く名が記されることになったことによる。しかし、すでに父旅人は十数年前
に没しており、一族には有力な後ろ楯になる人物は、ほとんど見当たらない
ときであった。
家持が貴族として活動しはじめた時期は、それまで権勢を誇っていた藤
原氏が、その権力を失墜させていたときであった。藤原氏は不比等の四子、
武智(むち)麻呂・房前(ふささき)・宇合(うまかい)・麻呂の四兄弟は
妹の光明子が皇后となったこととあいまって、それぞれに政界の中枢に乗り
出していた。とりわけ長男の武智麻呂は、長屋王を自死させたあと、右大臣
になり、さらに左大臣へと昇りつめていた。
ところが、一族に思いもよらぬ災厄(さいやく)が襲いかかってきた。七三七年に都に
天然痘が大流行して、四子(四卿)が半年のうちにあいついで死没したので
あった。
そのあとには、皇族出身の橘諸兄(たちばなのもろえ)が右大臣として政権をにぎり、唐から帰
国した吉備真備(きびのまきび)や僧の玄肪(げんぼう)が登用さ
れて活躍した。このような状況を黙視できないのが、宇合の子の広嗣(ひろつぐ)であっ
た 。
藤原広嗣は都から遠ざけられて、大宰少弐(しょうに・次官)の職にあったが、吉備真
備・玄防の排除を名目に西海道で大規模な反乱を起こした。この反乱には隼
人も動員されて、曽君多理志佐(そのきみたりしさ)も出兵している。しかし、反乱は鎮圧され、橘
諸兄はその後に左大臣になり、表面的には安泰に見えた。
しかし、藤原氏の挫折や、広嗣の反乱に衝撃を受けた聖武天皇の動揺は
おさまらず、天皇は恭仁(くに)(京都府)難波(なにわ・大阪市)・紫香楽(しがらき・滋賀県)などに
遷都し、数年の間は転々とした。この時期の聖武天皇の不安・動揺を示す事
業が、大仏造立である。天皇は「鎮護国家」を願って廬舎那(るしゃな)大仏建造をはかり、
仏教による国家安泰を具現しようとして、この事業を当初は紫香楽宮の地
で始めたのであった。
しかし、都が転々としたため事業は中断し、七四七年になって平城京で造
営事業を再開し、東大寺大仏として七五二年に開眼供養にいたった。大伴
家持が、かつての名族大伴旅人の復活をはかって、貴族の仲間入りをしたの
は、このような政情のときであった。
いっぽうで、橘諸兄は政権の要枢にあること約二〇年、七四歳の高齢で没
し、子の奈良麻呂が後継の地位をうかがっていたが、藤原氏では武智麻呂の
子仲麻呂が台頭してきたことから、家持は身の処し方に苦慮することになっ
た。
家持は地方の官人として越中(えっちゅう・富山県)の守をつとめた後に帰京し、少納
言・兵部大輔(ひょううたいふ・兵部省の次官)と中央官人への道を昇っていたが、七五七年に橘
奈良麻呂の乱(藤原仲麻呂を除こうとはかった)に関与したと見なされ、仲麻
呂によって因幡(いなば・鳥取県)の守に左遷された。かれはこの事件には直接関わっ
てはいなかったが、一族の者が関与していたための連坐であった。働き盛りの
四十代前半での挫折で、前途に不安を残すものであった。
その後は、一時的には仲麻呂の信任を得たようで、信部(中務省の一時的
改称)大輔になっている。藤原仲麻呂は一族出身の光明皇太后の信任を得て
紫微中台(しびちゅうだ・それまでの皇后宮職の改編)の長官に就任していた。紫微令とい
う長官職は光明皇太后を背景とした仲麻呂の権力基盤となり、対立してい
た橘奈良麻呂を獄死に追い込んで、独裁専制的様相を見せはじめていた。そ
の仲麻呂の専横に反対する藤原良継(よしつぐ・宇合の子)が変を起こすと、大伴家持
は良継に組みしたとして、七六四年薩摩守に左遷されている。家持はここで
も時の政情に翻弄(ほんろう)されている。
大伴家持が薩摩守になったときの位階は従五位上であり、薩摩守相当の
位階である正六位下からすると、数階高いので左遷であることは確かである
が、良継の変にどの程度加担したかは明らかでなく、その疑いがあるという
程度で、都から遠ざけられたというのが実態ではなかったかと思われる。藤
原仲麻呂にとっては、かつての軍事名族大伴氏の後継者が、都に在住するこ
とを嫌って遠隔の地へ、流罪的異動をはかったのであろう。
家持が赴任した七六四年の十二月には、「大隅・薩摩両国之堺」で火山噴
火が起こっている。おそらくは、その位置からして桜島の爆発であろう。「姻
雲晦冥(えんうんかいめい)、奔電(ほうでん)去来、七日之後乃(すなわち)天晴」と
いう状況から、かなり規模の大きい噴火で、犠牲者が「八十人」出ている。
家持は当時五十歳近い年で、このような噴火ははじめての体験であったと
想像するのであるが、どのような感慨をもったのであろうか。歌詠みとして一
首でも残しておいてくれたらと、残念に思うばかりである。『万葉集』の編集
者として知られ、自作の歌も四百五十首以上載せている家持が、この大噴火
に際し、心を動かされないはずはなかったであろうに。
家持は翌七六五年には薩摩守を辞している。中央の政界は目まぐるしく
変動しており、藤原仲麻呂が反乱を起こし、近江で敗死するいっぽうで、称徳
女帝と結んだ僧道鏡が台頭してきたのであった。
一、隼人の抗戦、その背後の真相は 二、ヤマト政権による隼人崩し 三、まず、薩摩国が成立した 四、大隅国の誕生―難産の末に― 五、隼人国の郡、郷構成のナゾ 六、強いられる苦難、そして抗い― 七、隼人は何を食べていたのか― 八、主食はサトイモ・アワと海・山の幸― 九、『正税帳』から見える隼人国― 十、『山背国隼人計帳』をのぞき見る― 十一、演出された幻影隼人― 十二、土俗から王権服属歌舞へ― 十三、ハヤトの呼び名はどこから― 十四、肥後・豊前国から隼人国へ移住― 十五、隼人たちは何を信仰していたのか― 十六、カミかホトケか、それとも― 十七、どこへ消えた 国府域住民― 十八、古代最大の水田開発か― 十九、めざそう 新しい道を― 二十、女帝と銅鏡 そして清麻呂― 二十一、和気清麻呂、歴史に登場― 二十二、征隼人持節大将軍 大伴旅人― 二十三、旅人の子 家持(やかもち)も薩摩守(かみ)となる― 二十四、隼人正(かみ)になった 大住忌寸三行(いみきみゆき)― 二十五、機を見るに敏 曽君多理志佐(たりしさ)― 二十六、隼人国の信仰・宗教をさぐる― 二十七、「大隅国神階記」に見える神社―
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd