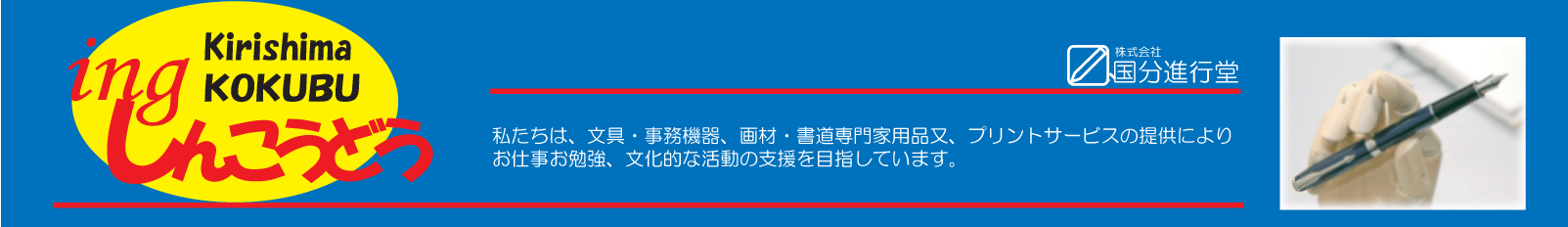

特別連載
<1.その一へ><1.その二へ> <1.その三へ><1.その四へ> <1.その五へ><1.その六へ> <1.その七へ><1.その八へ> <1.その九へ><1.その十へ>

万之瀬(まのせ)川は薩摩半島の中央部をほぼ西へ向って流れている。旧加世田市と旧金峰
町の境界近くに、今の河口部はある。ところが、その川筋は一八〇二年(享和二)以前
は、河口部が現在より南の旧加世田市小湊(こみなと)の小松原にあったという。したがって、河
口部が西流するようになったのは約二〇〇年前のことで、それ以前には河口部では南
西方向に流れていた。
それでも、以後の川筋がまっすぐになったわけではない。河口部を少し遡ってみる
と、南さつま市役所の付近には旧河道といわれている低地があり、またさらに上流の
川辺町の中心街を歩いていると、かなり大きな橋を二度も渡るが、土地の人の話だと
両方とも万之瀬川の架橋だという。
川辺の地名は「川の辺(かわのへ)」だというから、まさに万之瀬川の川添いであろうが、曲折す
る川筋と支流の多いことが実感できよう。
旧加世田市・旧川辺町一帯を、文化財マップを頼りにして、あっち、こっちと探している
と、そこにはいつも川との出会いがある。かつての、加世田・川辺はいうまでもなく、田
布施(たぶせ)・阿多、さらには知覧の一部まで、万之瀬川の本流・支流は灌概用水として田をう
るおしていたというのもうなづける。
その旧川筋で注目される遺跡が、旧河口近くの奥山古墳である。この古墳は、最近
まで六堂会(ろくどうえ)古墳と呼ばれていた円墳(径約十三・五メートル)で、早くから石棺が露出
していた。
いまでは、内陸に入り込んだ所に立地しているこの古墳を、数十年前に考古学研究
者たちと訪ねたとき、その中の一人が石棺の中に入り、仰向け状態になったところ、
全身がすっぽりはまったので、皆で「伸展(しんてん)葬」に誂え向きだと、囃したことを思い出
す。
また、六堂会という地名は、かつてこの地域に六地蔵の類を納めた御堂があって、そ
の由緒にもとついた名でもあろうかと、あまり深くは考えてもいなかった。
【「六堂会」とはどこ?】
ところが、鹿児島大学総合研究博物館の橋本達也さんを中心としたグループに
よる再調査によって、その名称をはじめ、この古墳についての多くの新しい知見を得る
ことになった。その成果を、勝手に、また部分的に利用させていただいて、以下に所感
を述べてみたい(『同研究博物館報告書No.4』に依拠)。
まず驚いたのは、古墳の名称として冠せられている「六堂会」という地名が、小字名
をはじめ、その近辺には見つからないというのだ。数十年の間、考古学研究者が使っ
ていた呼称が実在しない地名だという。不思議なことがあるものだ。
この古墳をめぐっての研究史をたどると、一九四二年(昭和十七)以来用いられて
きたというから、もう七十年にもなる。最初の報告書は、同年の『古代文化』(13-3)に
掲載された。その時の「薩摩万世町六堂会古墳」の題での発表が、この名称使用
の端緒であったという。
この古墳の所在地は、鹿児島県南さつま市加世田小湊五二六一番地で、小字名は
「奥山」であった。以後、市当局の承認を得て、「奥山古墳」と名称が変更されることに
なった。
【「奥山古墳の実像】
奥山古墳の築造は古墳時代の前期と推定され、その立地は万之瀬川の旧河口に近
く、吹上浜砂丘が形成される以前は、入江状の港の好適地に面していたとみられてい
る。同じような適地に立地する古墳は薩摩西岸部に、鳥越古墳(阿久根市Y船間島
古墳(薩摩川内市)安養寺丘(あんようじがおか)古墳(同)などと分布し、古墳築造の背景には海を介し
ての首長層の存在が浮上すると見られている。
いまは奥山古墳に限定して調査結果をみると、この古墳の石棺構築法と石材が九
州西海の天草地域に由来することが確認できるので、奥山古墳の被葬者は天草地域
の首長層と密接な関係をもつことが想定できるという。
また、古墳から出土した土器も、在地の成川式土器様式のものではなく、古墳にと
もなう祭祀土器として移入されたもので、その故地には熊本県宇土半島基部地域が
想定されるともいう。
このような報告を読んでいると、筆者にはかつて興味をいだいた九州最大級の豪
族・肥君(ひのきみ)一族の姿が思い出されてくる。
肥君の末喬の一人、肥君猪手(ひのきみのいて)は七〇二年の筑前国嶋(しま)郡川辺里(現在の福岡県糸
島半島)の戸籍に戸主として見え、嶋郡の大領(だいりょう:郡長)でもあった。その猪手の家族
は、古代の戸籍の中で最大で一二四名を数え、そのうちの三七名は奴碑(ぬひ)であった。
いまも正倉院文書として残るこの戸籍は、最古のものとして知られているが、残・
念なことに断簡(だんかん:切れ切れになった文書)であった。ところが、筆者が大学院のとき
教わった北山茂夫先生が若い時、バラバラになっていたこの戸籍を一連のものとして
つなぎ合わせ、大家族をみごとに復元させたのであった。この復元の端緒や苦労話な
ど、北山先生の功業は、当時の古代史学界では伝説のように語られていた。その真相
をご本人から聞き出そうとして、筆者はその機会を心待ちにしていたのであったが、い
つもは饒舌(じょうぜつ)な先生は、この戸籍復元の話になると、なぜかあまり多くを語ることはな
かつた。
【肥君は九州の北へ、南へ】
閑話休題。さてその肥君は、その氏名からみて、もとは肥後の豪族であったとみら
れる。その肥君の一族が七世紀末までには北部九州に勢力を伸張させ、八世紀初頭
の戸籍に多数の奴婢を従えた郡長として痕跡をとどめたのであった。
その肥君の肥後における本拠地が、宇土半島の基部にあったといわれている。とり
わけ、八代平野の中心部を貫流して八代海(不知火海:しらぬいかい)に注ぐ氷川(ひかわ)の流域である。
とすると、奥山古墳の被葬者は、肥君一族か、肥君につながる勢力の一端が進出し
ていた可能性も想定できそうである。
肥君一族が、八世紀前半には薩摩の北部、出水郡の大領となっていたことが、天
平八年(七三六)の『薩摩国正税(しょうぜい)帳』で確認できる。正税帳では大領のほか、少領(副郡
長)として「五百木部(いほきべ)」、その下の主政・主帳の二人も「大伴部」というように、肥後系統
の氏名が見える。となると、出水郡は肥後系の人物によって郡司が占められていたと
いえよう。そのような勢力の先端が、奥山古墳の地にまで伸びていたのである。それ
も古墳時代の前期という早い時期に。
しかし、奥山古墳の周辺には他に高塚古墳は見出されず、一代の首長墓のみで、連続
してその勢力が持続されず、首長の系譜形成まではいたっていない。それは薩摩地域の
首長墓に共通して概していえることである。
この点は、大隅地域の高塚古墳の分布と異なる特性である。いわば、大隅地域の高
塚古墳の分布が面的展開を見せているのに対し、薩摩地域の高塚古墳は点的で終
結している。奥山古墳もその一例である。
【河ロ部は対外交易拠点】
万之瀬川下流域は、古代末期から中世にわたっても、海外交易の拠点として重視さ
れている。現河口から約四キロほどさかのぼった位置に立地する、旧金峰町宮崎の持
躰松(もつたいまつ)遺跡はその代表例である。一九九六年以降調査されたところによると、十一世紀
後半期から十五世紀前半期ごろとみられる大量の中国製陶磁器を中心に、常滑(とこなめ)焼な
どの国内産陶器類が出土し、活発な交易活動の痕跡が見られた。旧加世田市側には唐
坊(とうぼう:現、当房)・唐仁原(とうじんばる)などの地名も残り、
中国系住人の居住地と推定されている。
万之瀬川は、このように薩摩半島、とりわけその西岸部の歴史と深くかかわってい
るが、いまは、奥山古墳築造以前に焦点をあてて、その歴史を概観してみたい。
【砂丘形成以前の地形】
薩摩半島西岸部には砂丘が形成されている。いわゆる吹上浜と呼ばれている砂丘
地帯である。その砂丘と、古墳時代以前の縄文・弥生時代の遺跡の分布は、どのよう
に関連しているのであろうか。
砂丘形成以前の海岸線と、遺跡の分布を示す地図を掲出してみよう。
一見して明らかなように、現在の弓状砂浜の海岸線とは大きく様相が異なり、縄
文時代は各所に入江状の大小の湾入が形成されたリアス海岸である。一帯の遺跡は、
その入江に沿うように分布している傾向が顕著である。したがって、各遺跡は海を
媒介とした文化の流入が容易に想像できよう。
また、海岸には各所に岩礁があったようで、牡蠣(かき)などの貝殻(かいがら)もまじって採掘される
という。一帯の遺跡からは概して貝殻がよく出てくるらしく、後述の阿多貝塚の所
在地は貝殻崎の地名で呼ばれる場所に立地しており、古くから貝殻の出ることで知
られていたらしい。
そこで、いくつかの遺跡をとりあげてみたい。まずは、南部九州の弥生時代の開始
期を知らせることで著名な高橋貝塚である。旧金峰町高橋に所在する。いまでは海
岸から約二・五キロ東の内陸部に離れているが、先掲の地図で見
ると、深く湾入した入江の入口に立地しており、海からの文物が北から、南から流
入するに恰好(かっこう)の場所である。その立地に似合わしい多様な遺物が出土している。いま
は、遺跡地に神社(玉手神社)が建立されているので、同地に接近する道筋の目標にも
なっている。
【高橋貝塚】
高橋貝塚の地に人が住みはじめたのは縄文時代の終りごろからで、夜臼式(ゆうす)土器の
出土がそれを示しているが、もっとも注目されるのは弥生前期の遺物である。
とりわけ、石包丁・石鎌などの稲の収穫具とともに、底面に籾(もみ)痕のある土器の出土
から早い時期に稲作が定着していたことが知られる。その時期は、朝鮮半島から北
部九州に稲作文化が伝わってから間もないころとみられる。おそらく、南部九州では
もっとも早い稲作文化の伝来地と推定される。
いっぽうで、同時期に牡蠣殻を主体とする貝塚も形成されていることから、漁撈も
さかんで、遺跡地一帯は生活適地であったとみられる。なお、鉄製品も出土している
が、腐食(ふしょく)が進んでいて形態の判別が困難だという。
さらに高橋貝塚で注目されるのは南海産のオオツタノハやゴホウラなどの大型貝
を加工した腕輪などの出土である。なかでもゴホウラの腕輪は半加工の未製品が多
く出土していることから、南海で採取された貝がこの地で粗製加工されて北部九州
などに運ぼれて、移出先の地でさらに精製加工されたのではないかと推定されてい
る。とすれば、高塚貝塚の地は、南海と北部九州を結ぶ、中継地であった可能性も考
えられよう。
つぎに、旧金峰町宮崎上焼田(かみやきた)にある阿多貝塚をとりあげたい。一帯は「貝殻崎(かいがらさき)」と呼
ばれるように、貝殻が古くから出土していた。最初の調査は昭和の初期で、
さらに一九七八年(昭和五三)に調査され、縄文時代前期から古墳時
代前期にわたる遺物が出土している。なかでも、筆者が注目するの
は、北部九州系の甕棺墓(かめかんぼ:二基)であり、北部九州との交流ばかりで
なく、移住者の存在が推定されることである。
この甕棺墓に関連して、近くの下小路(しもしょうじ)遺跡から甕棺墓(合せ口式で、南部
九州では初出土)も見つかっており、隣接地の扁平な巨石と一体的に見ると、朝鮮半島
南部系の支石墓(しせきぼ)が、北部九州を経由して導入されたと考えられることである。
支石墓は弥生時代の前期から中期にかけて北部九州に分布する墓制である。自然
石の支柱(支石)の上に大形の平石(撑石:しょうせき)を戴せたドルメンとも呼ぼれるもので、石
の下や周囲に甕棺が埋納され、群在することが多い。
南部九州では、旧金峰町のほか、旧吹上町(白寿:はくじゅ・入来:いりき遺跡など)で、その痕跡が認め
られている。
このような支石墓の痕跡からしても、北部九州の人びとが移住して滞在していたと
の想定は十分に可能であろう。
【上加世田遺跡にヒスイ】
つぎに周辺の注目すべき遺跡を見ておきたい。まずは、上加世田(うえかせだ)遺跡である。現、
南さつま市の市庁舎の東方に立地している(旧加世田市川畑)。縄文時代晩期の集会
場遺構である。
集会場遺構と推定したのは、全体が楕円形で、中心部が低い、いわば擂鉢状の形
状で、出土遺物・遺構などから見ても、住居とは明らかに異なることである。
遺構は長径二三メートル、短径十六メートルの楕円形で、中心部の窪地の最深地点
では二・一五メートルの深さがある。
遺構内から炉跡、埋め甕、岩偶(がんぐう)を納めた甕、軽石を入れた甕などがあり、配石遺構
のなかには石棒を立てたものが二基、遺跡一面に配置した岩偶、石棒が見つかってお
り、性器祭祀の信仰の場を思わせていた。
遺物ではヒスイの勾玉(まがたま)やヒスイの原石、攻玉(こうぎょく)用(玉類加工用)の砥石(といし)などが出土し
ており、ヒスイ原石の搬入ルートと加工技術の導入などに謎を残している。ヒスイの
原産地は、いうまでもなく県内にはなく、新潟県が知られているが、そのような遠地
からどのようにしてもたらされたのか。直接にか、間接にか。謎は深まるばかりである
が、わずかに謎解きの糸口が見え隠れする。
それは同遺跡から出土している土器に、東日本に分布する大洞(おおぼら)式の文様に類似したも
のがあり、その伝播ルートの解明である。
なお、岩偶はいずれも妊娠した女性像を表現したとみられるものであり、石棒は男
性をシンボライズしたもので、集会場が生産祈願の場であったことは明らかである。
【「阿多」の刻書出土】
つぎに、旧金峰町宮崎の小中原(こなかばある)遺跡をと
りあげよう。この遺跡は、平安時代を主体とするが、縄文時代から中世にわたる複合
遺跡である。
発掘現場は各地でしばしば見学させていただいたが、いつも思うのは発掘担当者
の方がたは並大抵の体力ではもたないだろうとその研究心と熱意に敬服してきた。寒
風にさらされ、暑さに耐え、黙々と仕事を続けられている。
そのような日頃の思いのなかでも、小中原遺跡の発掘作業は感動的でさえあった。
見学させていただいた日は、まさに炎暑であった。焼けつくような太陽の下で、背中
には莚(むしろ)のようなものを背負うようにして身につけ、炎熱をいくらかでも避けるよう
にして作業を続けていた。
莚と見えたのは、近づいてよく見ると、いまでは姿を消した昔の炭俵(すみだわら)をひろげたも
のに似ていた。おそらくは、真夏の農作業で古くから用いられてきた炎天での耐暑法で
あろう。
そこで見せていただいた遺物もまた感動的であった。平安中期の土器片に「阿多」の
文字が刻書(こくしょ)されて出土していたのである。
『日本書紀』に記されている「阿多隼人」の本拠地の一角が、小中原遺跡の地で、明かさ
れたのである。
八世紀以後は「阿多郡」となったのが、この一帯であった。その「阿多」の地名は、いま
も公共施設、バス停などで、千数百年を経た今も使われている。
関西在住の著名なある学者は、その著書のなかで、「阿多の地名は消えてしまった」
と述べているが、いまでも生きている地名である。ただ、古代よりはその地域が限定さ
れてはいるが。
そこで、古代の「阿多」の地名と、その周辺をめぐる問題についてさぐってみたい。
『日本書紀』天武天皇十一年(六八二)七月に、大隅隼人と阿多隼人が朝貢した記
事が見えるが、この記事以後「大隅」「阿多」の隼人の姿が具体的になってくる。南部九
州の地名あるいは住民の呼称「隼人」もこの頃に定着してきたのであろう。
『日本書紀』では、天武朝より古く一・二巻の神話のなかにも、南部九州の地名・人名な
どが記されているが、それらは七世紀後半から始まった『古事記』を含めた史書編さんの
過程で、時期をさかのぼらせて造作したものであろう。コノハナサクヤヒメの別名アタ
ツヒメや阿多君などがその例である。
それらの神話のなかで想定されている「阿多」の地は、万之瀬川下流域を中心と
した、薩摩半島南西部である。この地域に八世紀に入って薩摩国に属する郡制が導
入されると、阿多郡が設けられる。その配下に四郷が置かれた。鷹屋(たかや)・田水(たみず)・葛例(かれい)・阿
多(あた)の四郷で、その読みは仮につけたものであるが、ほぼ順当であろう。
薩摩半島には概して小規模郡が多いが、阿多郡は四郷でも半島部では最大の郡で
ある。郡の規模は、郡制以前の豪族勢力圏が継承されているとみられている。とする
と、阿多郡の地域には、薩摩半島最大の豪族が蟠踞(ばんきょ)していたことになる。その豪族が
阿多君(きみ)であった。
【霊山の信仰】
阿多の地域の西には金峰山(きんぽうざん)が立地する。神の依(よ)りつく山、仏の寝姿などとも形容
されるが、のちには修験道の行場(ぎょうば)ともされるように、神仏習合の霊山である。アタツ
ヒメは、この霊山の巫女(みこ)ともされているが、神話では高千穂に降臨したニニギノミコ
トが、その美貌に一目惚れして、求婚している。
また、阿多の南西には野間(のま)岳が西海に突き出た半島の先端に雄姿を見せている。航
海神を祀るともいわれるように、南から、あるいは西から、この地をめざす船の航路
目標ともなっている。この山もまた、阿多地域の霊山であった。
野間岳の八合目付近には野間神社が鎮座している。祭神は日向神話に登場するニ
ニギノミコト・ピコホホデノミコト以下多彩であるが、いっぽうで、中国の航海神である
娘媽(ろうま)神とする説もあり、その神名からノマ(野間)の名がついたともいわれる。
(注記-本稿の写真の一部は河口貞徳著『日本の古代遺跡鹿児島』より転載)
<1.その一へ><1.その二へ> <1.その三へ><1.その四へ> <1.その五へ><1.その六へ> <1.その七へ><1.その八へ> <1.その九へ><1.その十へ>
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd