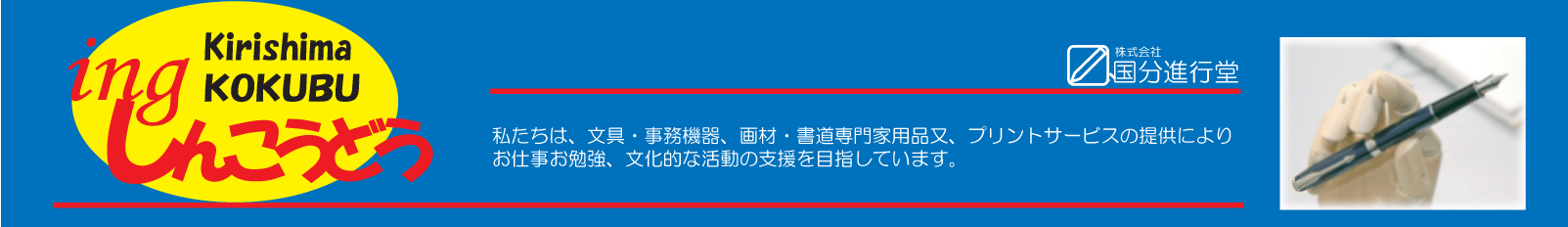

特別連載
<1.その一へ><1.その二へ> <1.その三へ><1.その四へ> <1.その五へ><1.その六へ> <1.その七へ><1.その八へ> <1.その九へ><1.その十へ>

河内国と大和国の国境いには一連の山並みがあり、両国の境界になっている
尾根が両側の平地部からよく望まれる。その山並みは、北から生駒(いこま)・信貴(しぎ)・
二上(にじょう)・葛城(かつらぎ)・金剛(こんごう)などの諸山で、中央部
の信貴・二山の両山がいくらか低い。
これらの山々は古代から河内・大和の人々に親しまれたもので、『万葉集』
をはじめ多くの文献に登場する。それは、古代においては、とりわけ宮都が
この両国に営まれたことから、河内の人々が大和へ、あるいは大和から河内へ
と往来が頻繁で、そのたびにこの山並みを越えなければならなかったことに
も一つの理由があった。それだけに、この山並みを越えるルートが古来いくつか
開けていた。
そのうちの一つが竹内街道である。竹内街道はいまの大阪府堺市から東方へ
のび、羽曳野(はびきの)市を抜け、二上山の南を越えて大和に入る。大和に入ってもこの
街道はさらに東にのび、飛鳥の北部へ連なる。
二上山はその名のように二つの頂部があり、それぞれ雄岳(お)・雌(め)岳とよばれ
る五〇〇メートルほどの高さの山である。私はかつて大和に住んでいたころ、
大和では二上山(にじょうさん)のほかにはこの山の別の呼び名を聞いたことはなかったが、あ
るとき、河内を歩き廻っていたところ、土地の人に二子(ふたこ)山と教えられたことが
あった。
古代の人々は「ふたかみ山」と呼んだようで、『万葉集』の歌ではこの呼び方
のほかでは歌の心をとらえ難いようである。
いまから一六〇〇年ほど前の、五世紀の前半のことであった。
主人と思われる人物を馬の背にかつぎのせた一団が、河内平野をあわただしく東
へ進んできた。竹内街道をやってきたかれらは、ときにふり返り、追手を気にしている
ようすである。二上山の山麓までやってきた一団は、休むこともなくそのまま斜面を登
りはじめた。暗闇の中を。
疲れはてているのでもあろうが、ことばを交わす者もなく、重い足をただ上に運んで
いる。そして、ようやく中腹の展望のきく位置までやってくると、先頭の三人が馬を
とめて立ち止まり、後続の従者達はその場にすわりこんだ。
かれらはいま登ってきた道筋を目でたどり、耳をすまし、追手の気配のない
のを確かめると、北西の方向に目を移した。月夜ではあるが、樹木の生い茂る
山道では月の光も忘れていた。ところが、坐りこんだこの付近は木のない草
地で、眼下の展望もきく。青い下界がそこに沈んでいた。
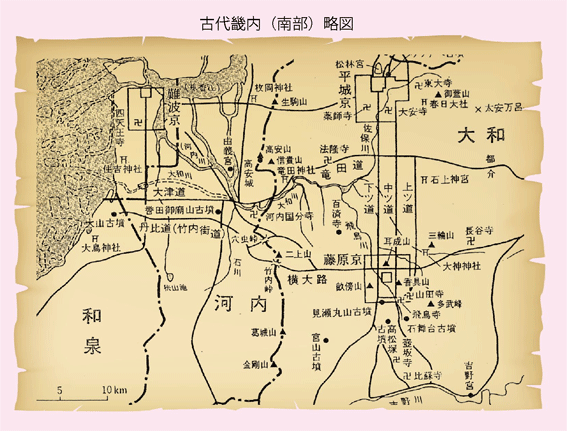 いまかれらが目をやった方向に一筋の白い光が走っている。大和川の流れで
ある。その川筋の果てるかなたに赤い光がかすかに見える。それがかれらの
脱出した難波高津宮(なにわのたかつのみや)の炎上の火であることはすぐわかった。
いまかれらが目をやった方向に一筋の白い光が走っている。大和川の流れで
ある。その川筋の果てるかなたに赤い光がかすかに見える。それがかれらの
脱出した難波高津宮(なにわのたかつのみや)の炎上の火であることはすぐわかった。
古代の王朝はその初期においては大和で発展したが、四世紀の末から五世
紀にかけては大阪湾に臨む河内平野に進出した。応神(おうじん)天皇とその子、仁徳(にんとく)天
皇の時代のことである。歴史家はそれを河内王朝といい、応神王朝ともよん
でいる。
仁徳天皇の御陵ともいわれる大山(だいせん)古墳がいま堺市にあるのは、この王朝が
河内平野を基盤にしていたことを示す一つの証拠とされるが、その父応神天皇
の御陵ともいわれる誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳も同じ河内平野の東にあり、従来の天皇
の陵墓が大和に存在することからすれば、河内王朝といわれる背景もうなず
けよう。
仁徳天皇についての、いまの子供たちの知識はその陵墓の規模が世界最
大であるということだけにつきる。しかし、戦前の国史の教科書には、その名の
ように徳の高い人物として描かれていた。
手元にある文部省検定済昭和十年発行の『尋常小学国史』(上巻)による
と、次のような一文がある。
第十六代仁徳天皇は、応神天皇の御子で、御なさけ深く、いつも人
民をおあはれみになった。天皇は、都を難波におざだめになったが、皇
居はいたって質素な御つくりであった。天皇は、ある日、高い御殿におの
ぼりになリ、四方をおながめになると、村々から立ちのぼるかまどの
煙が少なかったので、これは、きっと不作で食物が足らないためであら
う。都に近いところでさへこんな有様であるから、都を遠くはなれた
国々の人民はどんなに苦しんでゐることだろうと、ふびんにお思ひに
なり、三年の間は税ををざめなくてよいとおほせ出された。そのため皇
居はだんだんあれてきたが、天皇は少しも御気におかけにならず、御召
しものさへ新しくおつくりになることもなかったくらゐである。その
うちに、豊年がつづいて、村々の煙も盛に立ちのぼるやうになった。天
皇は、これを御らんになって、「われは、もはやゆたかになった。」とおほ
せられ、人民がゆたかになったことを、この上なくおよろこびになった
(下略)。
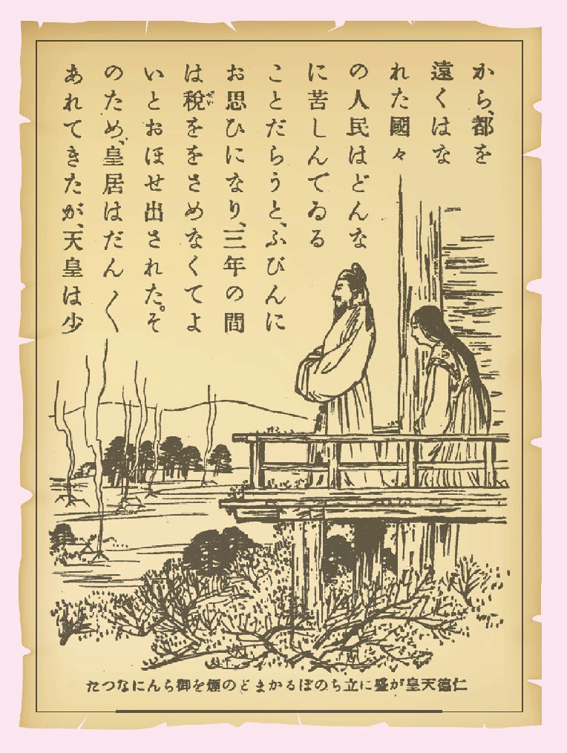 ところで、話はこの天皇の皇子たちのことである。
ところで、話はこの天皇の皇子たちのことである。
仁徳天皇と皇后の磐之媛(いわのひめ)との間には四人の皇子があった。上から、イザ
ホワケ(去来穂別)、スミノエノナカ(住吉仲)、ミツバノワケ(瑞歯別)、ヲアサズマワクゴノスクネ
(雄朝津間稚子宿祢)の四人である。
長子のイザホワケは皇太子であった。仁徳天皇が亡くなると、イザホワケは皇
位につくはずであったが、その直前に一つの事件がおこった。
イザワホケは羽田矢代宿祢(はたのやしろのすくね)の娘、黒
媛(ひめ)を妃とすることを望み、すでに婚約の儀もおわり、婚礼の日を決めるため、
弟のスミノエノナカを使者として遣わした。ところが、使者としておもむい
たスミノエノナカは黒媛の美しさに惹かれて一夜を共にしてしまった。そのと
き、スミノエノナカは兄の名を偽って名のったという。
兄のイザホワケは次の日の夜、黒媛をたずねた。なにも知らない兄は黒媛
の部屋に入ると、その寝室で鈴の音がするので、おかしいことだと思い、黒媛
に「その鈴は・・」とたずねると、「昨夜、太子がお持ちになった鈴ではございま
せんか。いまさらどうしておたずねになるのですか。」との答えにおどろき、
弟が黒媛と通じたことを知り、黙ってその場を去った。
鈴を黒媛の家に忘れて帰ったことから、兄に黒媛との間を知られた弟のス
ミノエノナカについて、日本書紀は、
爰(ここ)に仲皇子、事有らむことを畏(おそ)りて、太子を殺(し)せまつらむとす。密(ひそかに)に
兵(いくさ)を興(おこし)して、太子の宮を囲む。
と記しているが、筆者にはこの書きぶりからすると、スミノエノナカの行動ははじめから計画的であったと思われ
てならない。
ところで、スミノエノナカの挙兵にかえってその虚をつかれたイザホワケの
側では、側近の者たちが太子を助け出そうと、太子に事態の急なることを告
げるが、太子は泥酔していてそれに応じようとしないため、太子をかつぎ出
し馬にのせてようやくその場を脱出した。
太子をつれ出した一行は、難波から道を南にとり、いまの堺市付近までく
ると東へ進路を変え、竹内街道を進んだ。かれらの選んだこのコースには、途
中に父祖の陵墓があることから、暗にその加護を求める気持ちが働いていた
のかも知れない。が、最終の目的地は大和にあった。
夜半の道を、東へ東へと急いで、やがてかれらは二上山の麓までたどり着い
た。
さきに、主人と思われる人物を馬の背にかつぎのせた一団が暗闇の中をやっ
てきたのは、じつはかれらであった。
ここまでつれ出されて、太子はようやく酔がさめ、難波の方角をのぞんで
皇居の燃える火をみておどろいたという。正気にかえった太子は一刻も早く
大和へのがれようとして、一行をせきたてた。夜も明けはじめた。
途中で一人の少女に出会った。その少女のいうには、山中には武器をもった兵
士が多くいるという。スミノエノナカの手が早くも回っていた。一行は竹内越え
を捨て、北に進んで、大和川の川沿いに竜田山を越える進路をとった。
しかし、ここにもすでに追手はせまっていた。しばらく身を隠してようすを
伺うと、追手の数はさほど多くはない。
そこで、こちらから兵を出して追手を逆に包囲して捕えた。
追手の一団は、淡路島の野島の海人(あま)で首領は阿曇連浜子(あずみのむらじはまこ)という者で、ス
ミノエノナカの命令に従った者たちであった。
追手が淡路島からまで動員されていることは、イザホワケ太子の側にとって
は少なからず衝撃であった。スミノエノナカの側には予測を上まわる兵力が集
結しており、追手も次々にやってくることが十分に予想されるからである。か
れらは大和への道を急いだ。
川沿いの道は、両岸に山がせまり逃げ場がない。攻める側にとってはそこが
ねらい場である。太子の一行は気はあせるものの、身を隠しながらの行動であ
るから、思うように先に進めない。
やはり追手は現れた。数百名とみられる。追手とはいえない。すでにかれら
は先回りしていて道をふさいでいた。こんなときには無闇に交戦することは愚
かである。その数からみても勝ち目はない。しばらくようすを伺い、使者を出
した。
使者は殺傷されず無事帰ってきた。そのやりとりの報告を聞くと、待ち伏
せしていたのは倭直吾子籠(やまとのあたいあここ)とその手勢
で、いうまでもなくスミノエノナカの指令によって、太子一行の行く手をふさい
でいた。
しかし、吾子籠には情勢によっては太子側につこうという気もあり、交渉
しだいという意向がよみとれるという。古来、戦場ではよく見られる日和
見(ひよりみ)の手合いである。そこで重臣の一人を再びつかわし、吾子籠と交渉させたと
ころ、「太子を助けまつらむ」といい、服従の意を示すために妹の日之媛(ひのひめ)を太子
に献上するという。
吾子籠の寝返りによって危急を脱した太子一行は、かえって護衛の兵力を強
め、大和盆地を西から東へ抜けて、石上(いそかみ)の振(ふる)神宮にたどり着いた。いま天理市
布留(ふる)にある石上神宮である。
イザホワケ太子が石上神宮に拠ったのは、この神宮は古くから武器貯蔵所
となっていた。今でも有名な七支刀(しちしとう)などが所蔵されている。その上、太子の側
近の一人に物部大前(もののべのおおまえ)がいたことも関連している。というのは、石上神社は物部
氏の司る神であり。物部氏はまた朝廷においては軍事を担当する氏族であっ
たことにもよるからである。
このようにして、ようやく一つの軍事拠点を手中にした太子は、ここでしば
らく難波の情勢をみて時機を待つことになった。
石上に落着いて数日すると、弟の一人、ミツバノワケが兄をたずね追ってき
た。しかし、兄の太子は、この弟の心中を疑って会おうとはしなかった。弟のミ
ツハノワケは、そのとき兄の側近に対して自分の心情を次のように吐露したと、
『日本書紀』は伝えている。
「今太子と仲皇子と、並に兄なり。誰にか従ひ、誰にかそむかむ。然れど
も道無きを亡ぼし、道あるに就かば、其れ誰か我を疑はむ。」
それだけ告げると、ミツハノワケは兄に会えぬまま、難波へひき返した。す
でに心は決まっていた。次兄のスミノエノナカを殺し、長兄の太子に自分の真
意を行動で示すことである。
かつて高徳のほまれ高い仁徳天皇の皇子たちは、かくて兄弟相互に争うこ
とになった。古代において兄弟間における殺戮(さつりく)は、さほど珍しいことではない。
が、その多くの場合は一夫多妻にもとづく、異母兄弟の間での事件である。と
ころが、仁徳天皇の皇子たちの場合は、同母兄弟であった。
いずれにしても、兄弟間の争いは少なからずみられる。その主因となる古
代の慣習について、ここで少しふれておきたい。
それは、とくに皇位継承法についてである。皇位は父から子へという原則が
一般には考えられている。子のうちでは長子が優先される。ところが、古代にお
いては父子間の継承よりも兄弟間の継承が多い。というより、兄弟継承ができ
ない情況の場合に、皇位は初めて次の世代、すなわち子の世代に移る。
仁徳天皇の皇子たちの皇位継承法のあとをたどると、仁徳天皇のあとに
は長子のイザホワケが即位し履中天皇になり、そのあとには弟のミツハノワケ
の反正(はんせい)天皇、さらにその後には弟のヲアサズマワクゴノスクネの允恭(いんぎょう)天皇と
続いた。兄弟三人が次々と皇位についたわけである。そのあと、皇位は次の世
代に移り、允恭天皇の皇子たち二人が兄から弟へとういように皇位を継承し
ている。すなわち、安康天皇と弟の雄略天皇である。
といっても、兄弟継承が制度化されていたわけではないので、兄から弟へと
皇位が継承ざれず、兄から子へという父子継承の可能性も少なからずあると
ころに、皇位をめぐる争いがおこる一因がある。
古代最大の内乱といわれる壬申(じんしん)の乱も、このような皇位継承法に起因し
ていた。すなわち、天智(てんじ)天皇が弟の大海人(おおあま)皇子をいったんは皇太子に定めて
おきながら、のちに自分の子の大友皇子に皇位を譲ろうとしたことから、大
海人皇子が反発し、天智・大友側との争いになった。結果的には大海人皇子
が勝って天武(てんむ)天皇として即位するのであるが、天智と大海人は同母の兄弟で
あったことからすると、壬申の乱は兄弟の関係よりも父子の関係のきずなの
強欲さをみせつけられた争いでもあった。
古代の皇位継承をめぐるこのような慣習に、複雑な人間関係がからみ、皇
子たちの行動がひき出されてくる。イザホワケ太子とスミノエノナカの不仲。
スミノエノナカを抹殺することによって皇位に一歩接近するミツバノワケの
兄太子への忠誠。
スミノエノナカに仕える一人の隼人がいた。名をサシヒレ(刺領巾)という。
『日本書紀』に「近習(きんじゅう)」と表記されてい
ることからすると、皇子の身近に仕え、身辺の雑事にあたるいっぽうで、皇子の
護衛の任務もあったとみられる。
ヤマト王権に征服された隼人の一部は、服属の証(あかし)として畿内に移住させら
れていた。一種の人質であろう。その隼人たちの中から選ばれてスミノエノナ
カの近習になったのがサシヒレであろう。南九州の蛮族とみなされている隼
人が天皇家の内部で用いられるというのは、サシヒレに限らず、雄略天皇に仕
えた隼人の例もある。
大和の石上の振神宮で兄にその心を疑われたミツハノワケは、難波にひき返
すと次兄のスミノエノナカを殺害する計画をめぐらした。そのとき、ミツハノ
ワケの脳裏にひらめいたのはスミノエノナカに仕える近習隼人を利用するこ
とであった。
ミツハノワケはひそかに隼人のサシヒレを呼び出した。そして次のように
相談をもちかけた。
「若し汝(なれ)、吾が言に従はば、吾れ天皇と為リ、汝を大臣に作(な)して、天の下
治(し)らしめざむは那何(いかに)ぞ。」
この「汝を大臣に」という夢のような話を、サシヒレは現実の自身と重ね合
わせて危惧を感じなかったのであろうか。そして続く。
「然らば汝が王(みこ)を殺せ。」
という、ミツハノワケのことばを不用意に受け入れた。
このとき、ミツハノワケは自分の着ていた錦(きぬ)の布と袴を脱いでサシヒレに与
えたという。サシヒレはいわれるままにそれをすぐ実行に移した。主人のスミ
ノエノナカが厩(かわや)に入るのを伺い、矛(ほこ)で刺
し殺したのである。
かくして、スミノエノナカを殺したミツハノワケは隼人のサシヒレを伴なって
大和へ向かった。そして、再び二上山の麓までやってきた。
その途中でミツハノワケは、サシヒレをどのようにとりあつかうかを考えて
いた。『古事記』の記述を直訳すると次のようだ。
サシヒレは自分のためには功績があった。しかし、己の主君を殺したこ
とは人の道ではない。といって、その功績に報いぬのは自分がサシヒレを欺
したことになる。約束通りに実行すると・・・。
やはり、サシヒレは恐ろしい奴だ。
心中で、このような問答がくり返されていた。その結果、
「其の功に報ゆれども、其の正身を滅してむとおもほしき。」
と、『古事記』は述べている。ミツハノワケはサシヒレにいった。
「「今日は此間(ここ)に留まりて、先ず大臣の位を給ひて、明日(あす)上リ幸(い)でまさむ」
そこで、山麓ににわかに仮宮を造り、豊(とよ)の明(あか)りの宴がとり行なわれた。サシ
ヒレには大臣の位が賜与され、役人たちをして拝ませた。隼人のサシヒレは、
ついに大臣になったことに歓喜した。
ミツハノワケ皇子が隼人に声をかけた。
「大臣と同じ盞(つき)で酒を飲もう」と。顔が隠れるほどの大鋺(まり)に酒がそそがれ、
二人の間に進められた。鋺というのは「椀」ともかき、ワンのことである。水
や酒などを入れる器であるが、顔がかくれるほどの大銃で互いに酒を酌み交
わすことは、親愛の情を表すものである。
そこで、大鋺につがれた酒を、まずミツハノワケが飲んだ。そして、隼人のサ
シヒレに大鋺が渡された。サシヒレは、大臣になった喜びと、皇子と対で酒が
飲める感激を顔面に満たせて、大鋺を受けるとその酒を一息に飲み干すように大鋺を顔前で傾け、ついには大鋺で
顔を覆った。酒がのどを通る音が聞こえるように見えた。
そのときであった。皇子は敷物の下に隠していた剣を取り出すと、いま酒
が流れ落ちているサシヒレののどに力一杯に剣を突き刺した。
サシヒレは後方に転倒した。そして、そのまま動かなくなった。剣はサシヒレ
ののどに突きささったままで、ほとんど垂直に立っていた。のどからはわずかに
血がにじんだ。血はのどをおちていた濁酒(にごりざけ)とまじったのか、淡い桜色に見え
た。
次の日、ミツハノワケの一行は、何事もなかったように二上山の南の竹内峠
を越えると、一気に大和に入り飛鳥へと急いだ。
やがて飛鳥の低い山並みが見え出した。そこまで来て、一行は小休止した。
ふり返ると、二上山の雄岳・雌岳の両岳は低い雲にかくれて見えなくなってい
た。雨が近い。
そのとき、ミツハノワケは自分がかわいがっていた近習がいないのに気がつい
た。飛鳥への道を急いでいたため、その近習がどこでいなくなったのかわから
なかった。
二上山の方に再び目をやると、その麓からかぼそい煙が立ちのぼっていた。
<1.その一へ><1.その二へ> <1.その三へ><1.その四へ> <1.その五へ><1.その六へ> <1.その七へ><1.その八へ> <1.その九へ><1.その十へ>
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd