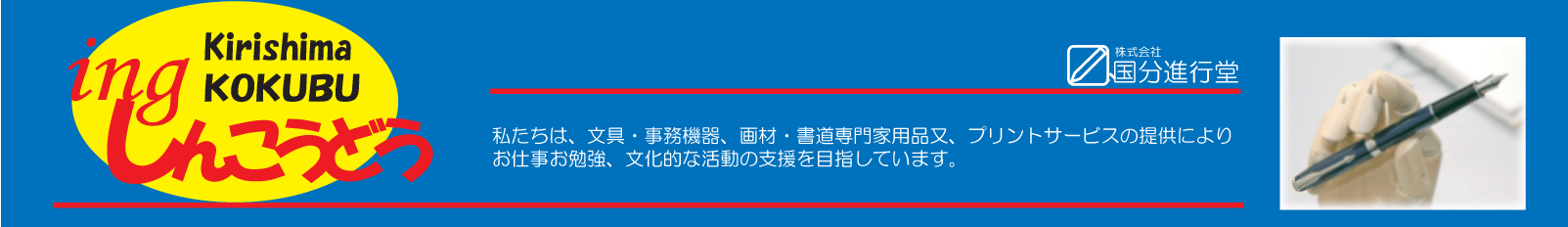

特別連載
<1.その一へ><1.その二へ> <1.その三へ><1.その四へ> <1.その五へ><1.その六へ> <1.その七へ><1.その八へ> <1.その九へ><1.その十へ>
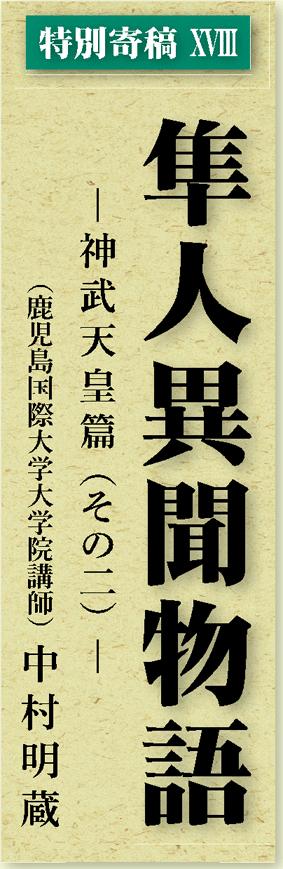
神武天皇の生涯を『記紀』(古事記・日本書紀)によって、もう少したどってみた
い。
天皇は、高千穂に降臨したニニギノミコトから数えて四代目で、南部九州で誕生
したことになっている。父はウガヤフキアエズ、母はタマヨリヒメ(海神の娘、トヨタ
メヒメの妹)で、誕生地の伝承の一つが宮崎の鵜戸神宮の地であるという。
天皇は四人兄弟の末子ということになっている。かつて、末子相続は西日本各
地の慣習として分布していたが、薩摩半島ではその慣習がとくに近時まで残存し
ていた、と民俗学の研究者は語っている。
神武天皇にいたる四代のなかでも、その例が見られる。
「神武」の名は、おそらく後世につけられたもので、『日本書紀』による死後の諡(し)
号(おくり名)は「神日本磐余彦天皇(かむやまといはれひこのすめらみこと)」で
あるが、ここで用いられている「日本」「天皇」などの表記も後代の用字である。とな
ると、「磐余彦」に意味があり、その前後の表記は美称あるいは敬称として、のちに
加えられたものであろう。
 いっぽう、同書では「神武」の諱(いみな:生前の名)は「彦火火出見(ひこほほでみ)」ともある。これは、二
代前の山幸彦と同名で、ニニギノミコトの子の一人である。とすると、本来の神話は、
天降ったニニギの子が第一代の天皇になる構成であったが、阿多隼人に伝承されてい
た海神神話を、隼人同化をはかって、その間に挿入したことによって、名前がダブる
ことになり、現存の新しい神話が構成されることになったのではな
いか、との推定も可能となる。しかし、いまはそれ以上は追求せず、先
に進めたい。
いっぽう、同書では「神武」の諱(いみな:生前の名)は「彦火火出見(ひこほほでみ)」ともある。これは、二
代前の山幸彦と同名で、ニニギノミコトの子の一人である。とすると、本来の神話は、
天降ったニニギの子が第一代の天皇になる構成であったが、阿多隼人に伝承されてい
た海神神話を、隼人同化をはかって、その間に挿入したことによって、名前がダブる
ことになり、現存の新しい神話が構成されることになったのではな
いか、との推定も可能となる。しかし、いまはそれ以上は追求せず、先
に進めたい。
神武は十五歳で太子となり、成人して吾田(阿多)邑(むら)の吾平津媛(あひらつひめ)
を妃とし、手研耳命(たぎしみみのみこと)を生む。
四十五歳にして、一念発起して、「西の偏(ほとり)」から国の中心をめざし、「諸の皇子・舟
師(水軍)をひきいて東を征(う)ち」に向う。いわゆる、神武東征である。
途次、筑紫(つくし)・安芸(あき)・吉備(きび)などに寄りなが
ら、河内の白肩之津(しらかたのつ:現、大阪府枚方市北部)に到る。古くは現在の地形よりも大
阪湾から内陸部に潟湖が入り込んでいたようである。
筑紫では、速吸(はやすい)之戸(豊予海峡)をぬけて菟狭(うさ:宇佐)の一柱騰宮(あしひとつあがりのみや)
を経て岡水門(おかのみと:現、福岡県遠賀川河口)へ到る。その後、
瀬戸内沿岸の安芸(広島)・吉備(岡山)へと進路をとっている。
ところが、東征の出発地については『古事記』に「日向より発たして筑紫に幸行
でましき」とあるだけで、具体的港津の名は記されていない。「日向」は、古くは鹿児
島・宮崎両県の地域を広く指していたので、神武天皇東征出航伝承地は両県にい
くつかある。そのうちの肝属川河口の柏原や耳川河口の美々津などを、前にあげ
たが、もう一カ所を紹介しておきたい。
それは、鹿児島湾奥部の霧島市福山町にある宮浦(みやうら)神社の地である。この神社は
式内社であるから、神社の歴史としては古い。祭神は神武天皇ほか、天神七代・地
神五代とするが、『延喜式』では「一座」であるから神武天皇が中心であろうか。
この神社の境内、本殿を正面に見る左右に銀杏の大木が二本ある。樹齢一千年
以上(樹囲八メートル弱)ということであるから、神社の歴史と前後する長い生
命を保っている。また、境内地の一角には、「神武天皇御駐蹕傳説地宮浦」と記され
た石碑が建っており、右寄りに「昭和十五年十一月十日」、左寄りに「鹿児島縣知事
指定」とあって、谷山の柏原神社の石碑と同じく、紀元二千六百年を記念して造立
されたものとみられる。
 また、神社への国道の途次、国分市街地寄りには若尊鼻(わかみこのはな)といわれている、海中に突
き出た岬がある。釣場としても知られているらしく、いつ行っても釣り人が多い。
桜島も好角度で眺められるので、釣果がなくても、都塵をしばし忘れられる、隠れ
た名勝地である。
また、神社への国道の途次、国分市街地寄りには若尊鼻(わかみこのはな)といわれている、海中に突
き出た岬がある。釣場としても知られているらしく、いつ行っても釣り人が多い。
桜島も好角度で眺められるので、釣果がなくても、都塵をしばし忘れられる、隠れ
た名勝地である。
この岬の名の由来については、クマソを討ちに来た日本武尊(やまとたけるのみこと)の上陸地という伝承
にもとづくとされている。『日本書紀』によると、クマソ征討に出立するときのヤマ
トタケルの年齢は十六歳とされているので、「若尊」の名にふさわしい。また、ヤマト
タケルはクマソを討つときに女装しているので、それも似合う相応の年でもあろう。
この岬の名称やその由来伝承には、あるロマンさえ感じさせるものがある。
ところが、『古事記』に描かれたヤマトタケル像は、残酷非道な人物であった。
その父親景行(けいこう)天皇の話から姶めたい。景行天皇の妃は数えられるところで七
人以上である。皇子たちを集計して、「録(しる)せるは廿一王、入れ記さざるは五十九王、
あわせて八十王」とある。すなわち、皇子は八十人いるが、記録しているのは二十一人
というのである。そのうちの二人が大碓(おほうす)命・小碓(をうす)命(のちのヤマトタケル)兄弟で
あった。(『日本書紀』には双生児とある)。
さて、父の天皇は美濃国(現、岐阜県)に「容姿麗美」の姉妹がいると聞いて、兄の
大碓命を遣わして二人を召し上げることにした。ところが大碓命は「己(おの)れ自(みずか)ら其の
二(ふた)りの嬢子(やまとめ)を婚(まぐわ)ひじて、更に他(あだ)し女人を
求めて、詐(いつわ)りて其の嬢女と名づけて貢(たてまつ)りき」とあり、二人の女性をめぐっての父子
の争いがあった。
 景行天皇の実在については、かなり疑いがもたれているので、妃・皇子の数について
も信憑性は少ないとしても、『記紀』の編纂者は、神代は別にして、皇代の記述はそ
れなりの人間関係を前提として、記述を取捨したとみられる。
景行天皇の実在については、かなり疑いがもたれているので、妃・皇子の数について
も信憑性は少ないとしても、『記紀』の編纂者は、神代は別にして、皇代の記述はそ
れなりの人間関係を前提として、記述を取捨したとみられる。
『記紀』編纂期にあたる七世紀後半の天武天皇には十名以上の妃がいたことが
認められるし、その後の律令(後宮職員令)でも、皇后は別格として、妃(ひ)二人、夫(ぶ)
人三人・嬪(ひん)四人の規定があったから、妃(きさき)は十人ないし、それ以上となる。
古代に限らず、一夫多妻の習俗は後代にも多く見出される。江戸時代、徳川十一代
将軍家斉(いえなり)は、側室四十人で、子女五十五人をもうけた。明治期のある元勲は、明治天
皇から子どもが何人いるかと聞かれ、「調べてから、ご報告申し上げます」と即座に
は答えられなかったという話が残っている。調べても全員わかったかどうか気にな
るが、話をヤマトタケルにもどそう。
さて、景行天皇と大碓皇子(命)父子の女性をめぐる争いから、天皇は弟の小碓
皇子に「なぜ、お前の兄は朝夕の食事に出てこないのか、お前が教え諭(さと)せ」といわれ
た。それから五日たっても、大碓皇子が出てこないので、天皇が小碓皇子に再度確
認したところ、小碓皇子は「すでに教え諭しました」と答えた。そこで天皇は「如何(いか)
に教えたのか」とたずねると、「兄が朝方側(かわや)に入ったとき、待ち捕えて、搤(つか)みつぶし
て、手足をバラバラにして、薦(こも)に包んで投げ棄てました」と答えた。
天皇は、それを聞いて、小碓皇子の猛(たけ)き荒き情(こころ)を恐れて、「西の方に、クマソタケル
が二人いる。かれらは天皇の命に従わず、無礼な者たちだ。その二人を討ち取れ」と
いって、遣わした。それが、クマソ征討に向う発端であった。
また、女装してクマソ兄弟を討ち殺すときは、弟が逃げ出したところを、「其の
背皮(そびら)を取りて、剣を尻(しり)より刺し通した」とあり、兄を殺すときは、「熟苽(ほぞち)の如く振り
折(た)ちて殺した」という。すなわち熟(う)れた瓜(うり)がジクジクするように、兄の肉体をグチャ
グチャに切って殺したというのである。
クマソの弟と兄、それぞれの殺し方は普通ではなく、残虐そのものである。それに
加えて、実の兄の殺し方を思い出すと、なんとも尋常ではない性格である。
そもそも、クマソはなぜ「征伐」されねばならなかったのか。「伐」とは、罪人を攻
める、罪を罰して斬(き)る、首を切って殺すなどの意である。クマソが実在していたとす
れば、南部九州の先住民であり、わたくしたちの先祖である。列島の南端の別天地
で自立して、生活を楽しんでいたと想像される。そのクマソ一族が天皇の命令に従
わなかったといって、「征伐」される理由になるのだろうか。
わたしたちも、つい「クマソ征伐」という表現を、深く考えずに使ってしまうこと
に、慣らされてしまっている。
若尊鼻の絶景にもどりたい。
ヤマトタケルもクマソもしばし忘れさせてくれる静かな海、やわらかい陽光、
そして昭和火口から白い煙をあげている堂々とした桜島が、すぐそこにある。
ワカミコの名称については、別の伝承がある。それは、「若皇子(わかみこ)」から名付けられた
もので、神武天皇の幼名「若御毛沼(わかみけぬ)」にもかかわるという。『古事記』によると、ウガ
ヤフキアエズとタマヨリヒメの間には四人の子があり、「生みませる御子の名は、
五瀬(いつせ)命、次に稲氷(いなひ)命、次に御毛沼(みけぬ)命、次に若御毛沼命」とあり、末子のワカミケヌの
「亦(また)の名は神倭伊波禮毘古(かむやまといはれびこ)命」とある。
となると、神武天皇を祭神とする宮浦神社との結びつきもあって、「若皇子」あ
るいは「若御毛沼」から転じた表記か、とも推測可能である。しかしながら、宮浦
神社については『延喜式』以後の記録がほとんど失われており、わずかに江戸時代の
一七五二年(宝暦二)に「正一位」の神位奉授があったことが知られている。したがっ
て、「若皇子」「若御毛沼」の伝承が、何らかの出典にもとつくものとの確証は見出
し得ていない。
話をまたもとに戻して、神武天皇の東征をもう少し追ってみたい。
大阪湾から上陸して、河内から大和に入ろうとした神武は、両国の境にある生
駒(こま)山西麓の孔舎衛(くさえ)坂で長髄彦(ながすねひこ)に行手を
阻(はば)まれてしまった。クサエザカの地名は、いまも大阪から奈良に向う近鉄沿線に
残っており、すぐ東には生駒山が前途をさえぎるように迫っている。長髄彦は、そ
の名前からして長身巨漢の体躯で、一帯を領有支配していた豪族の首領であろ
う。
新来の神武にとっては強敵であったから、神武は一旦後退して、大阪湾を南へ廻
り、紀伊半島から大和に入る進路をとっている。その間に、兄五瀬命などを戦いで
失っていた。熊襲から難路を北上、途中高倉下(たかくらじ)に助けられ、八咫烏(やたがらす)の先導などを受
けながら大和に入り、遂に長髄彦を討つのであるが、この間の『記紀』の記事はか
なり詳しく長い。
したがって、その多くを省いたが、一つだけ書き留めておくと、戦いが不利になった
時に、金色の鵄(とび)が飛んで来て天皇の弓の先(弓弭:ゆはず))に止り、敵を眩惑したという。こ
の金鵄(きんし)の話が由来となって、明治時代になって陸海軍軍人で武功抜群の者に「金
鵄勲章」が下賜されるようになったという。また、この金鵄の話は、明治以後の教
科書に載せられていたので、国民の多くが共通知識として語り、伝えられていたとい
う。
大和に入った天皇は、その後畝傍山(うねびやま)の南東の橿原(かしはら)の地に宮殿を建て、媛蹈鞴
五十鈴媛(ひめたたらいすずひめ)を正妃(皇后)に立てて、帝位についた。
これまで、「神武」あるいは「天皇」の名で話を進めて来たが、これまでは磐余彦(いはれびこ)
であって、即位して「天皇」となる(その天皇号も七世紀末からの使用で、それ以前
は「大王」であったか)。その即位年は辛酉(かのとり)で、紀元前六六〇年にあたるという。在
位は七十六年と長いが、さらに崩御年は百二十七歳であったというから、並の人間
ではない。陵墓は、畝傍山北東にある。
ところで、即位年を神武元年としての年代の数え方は太平洋戦争時までは一
般的に使われていた。昭和十五年(西暦一九四〇)は、その神武紀元でちょうど
二六〇〇年にあたっていたから、記念行事が全国各地で行われた。なかでも、神武天
皇の誕生地であった鹿児島・宮崎両県では行事が盛んであった。その一端について
は、次号でとりあげる。
当時、歌われた「紀元二千六百年」は国民の愛唱歌の一つであった。一番から五
番まであるが、一番だけ書き出してみる。いまだご記憶の方も多いと思う。
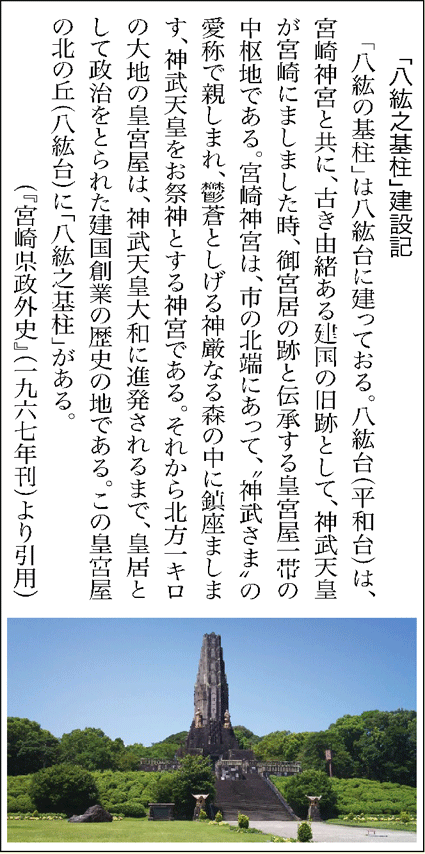
金鵄(きんし)輝く 日本の 栄(は)えある光 身にうけて
いまこそ祝えこの朝(あした)
紀元は二千六百年
ああ一億の胸はなる
この歌詞の冒頭は「金鵄」である。太平洋戦争を経験されている高齢の女性に、
この歌詞を見せたら、つい歌い出して、なつかしい表情をされた。そして、この曲を
聞くと、当時の食糧難をもついでに思い出してしまうという。当時は替え歌もはや
り、歌の最後は「ああ一億のハラは減(へ)る」と、一億国民の実情を語ってくれた。
ところで、歌詞の最初の「金鵄」についても訪ねたら、それは「キンシクンショウ」
(金鵄勲章)ですよ、と即座に答えられた。そこで、神武天皇の弓の先端に止まっ
た「金鵄」の話を聞いてみた。すると、それは「金のトビ」です。教科書で教わったか
ら間違いありません、と断言された。なるほど、と納得させられた。教科書と「紀元
二千六百年」の歌詞の間にはその理解に齟齬(そご)が生じていたようである。
ところで、神武天皇の即位年が西暦紀元前六百六十年の辛酉(しんゆう)の年となったので
あろうか。この設定については、早くも平安時代に三善清行(みよしきよゆき)が十世紀の始めに示唆
的提言をしている。また、江戸時代の十九世紀になると、伴信友(ばんのぶとも)の主張があり、明
治時代に東洋史学者の那珂通世(なかみちよ)に至って定説となった学説がある。
それは中国古代の予言説である讖緯(しんい)説にもとづいているという。シンイ説とは陰
陽五行説(いんようごぎょうせつ)によって、干支(かんし)の辛酉年には政
治上の変革があり、ときに国の主権者が交替するという。その辛酉年は六〇年(一
元)ごとにめぐってくるが、一元が二十一回繰り返されると、一蔀(いちぼう:一二六〇年)とし、
この年には大変革が起こるとされる。そこで推古天皇九年(六〇一)の辛酉年を基
準とし、それから一蔀さかのぼらせた辛酉年(紀元前六六〇年)を神武天皇即位年、
国の建国初年として『日本書紀』にその年代が記されたというのである。
しかし、その後の歴史記述では神武紀元はあまり使われなかった。ところが、明
治六年(一八七三年)一月に神武天皇即位日や天長節を祝日としたことから、神武紀
元(皇紀)が国定教科書に記述されるようになり、太平洋戦争後に廃止されるま
で存続した。
神武紀元が廃止されると、西暦が一般的に通用するようになったが、西暦が「正
しい」とまでいうのはどうであろうか。西暦はイエス・キリストの誕生を元年とし
て数えているので、キリスト教徒の多い国で利用されてきた。ところが、世界には多
くの宗教があって国情も異なっている。ただ、西暦を用いる国が多いので、それに合
わせるのが国際的に「便利」ということであろう。
神武紀元が、明治六年から用いられたのは、ある事情があった。その事情とは、
その前年末から翌年初めにかけて、日本の暦法に大きな変化が起こっていたこと
である。
明治五年は、国民皆学・国民皆兵が布告された年である。すなわち、近代的学
校制度(学制)と徴兵制度(兵制)の姶まりである。このうち、暦法とからんで月・
日に不思議な現象がおこった。たとえば、「徴兵告諭(こくゆ)」が明治五年十一月二八日に
発布され、従来の武士に代わって「全国四民男児二十歳二至ル者ハ、尽(ことごと)ク兵籍二編入
シ、以テ緩急(かんきゅう)ノ用二備フヘシ」と、太政官が徴兵令の意義を説明している。そして、翌
六年一月十日に徴兵令が発せられたのであるが、告諭から四十数日あるはずの日
数が、現実にはわずか十五日しかなかったのであった。
じつは、その間に太陽暦が採用されたのであった。
それまでの旧暦(太陰太陽歴)は、明治新政府を悩ませていた。というのは、種々
の新政を実施するための財源に苦慮していたからである。旧暦では、原則として三
年に一年は十三ヵ月となっており、ときに二年に一年になることもあった。
江戸時代までの諸藩の出費を見ると、たとえば藩士への俸禄は年俸を基本とし
ていたので、一年が十二ヵ月でも十三ヵ月でも、その対応に変化はなかったが、明治
新政府は新制度のもと、役人や巡査などに支払う給料は、年俸ではまかなう財力
はなく、月俸(月給)を基本にしていた。ところが、一年に十三度も月俸を支払わね
ばならない年が出て来たのである。
明治になって、元年、三年についで、六年が十三ヵ月になる(閏(うるう)月のある年)予定
であったから、五年の末近くの十一月九日に、来年(六年)から「太陽暦採用の詔書」
が発布された。
その結果、明治五年十二月三日を、一八七三年(同六年と月一日としたので
あった。この日をもって、日本は太陽暦を採用するとともに、西暦と日本暦が合致
することになった。
一八七三年元日以前のできごと・事件に西暦を用いると、じつはズレがあるのだ
が、現在は教科書をはじめ、通常の日本史ではそのズレは黙認している。
この暦法のズレは、神武天皇即位日すなわち紀元節をどの日にするかで、政府
当局者をかなり困惑させている。そこには、暦法のズレだけにとどまらない。国家
体制の基本にかかわる重要問題がかかわっていたからである。
それまで長期にわたった武家政治に代わって、政権をとった明治新政府は、天皇
制国家を樹立し、その政治体制をどのように維持・存続させるかに腐心(ふしん)していた。
のちの「大日本帝国憲法」では、「天皇ハ神聖ニテ侵スヘカラス」とあり、また「天皇ハ
国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬(そうらん)」するとあるように、天皇は絶対的存在であった。
その天皇の絶対性の根元は、第一代の神武天皇に発していたのであった。した
がって、神武天皇の即位日にあたる紀元節は、明治国家にとって重要な祝日で
あった。
太陽暦採用の詔書が発布されたあと、すぐに太政官布告に
「今般太陽暦御頒行(はんこう)、神武天皇御即位ヲ以テ紀元ト定メ被(ら)
レ候」とあり、神武天皇即位日の一月一日を太陽暦に換算し、一八七三年(明治六)
一月二十九日をもって、即位の祝日とし、例年祭典を執行することにした。しかし、そ
の日に不都合があったのか、曲折を経て、二月十一日と定めて「紀元節」となった。
それを引き継いだのが、現在の「建国記念日」である(一九六七年に復活)。
太陽暦の採用は、新政府の財政上の問題に端を発したが、いっぽうでは西欧文化
に歩みを合わせる「文明開化」にもかなっていた。
ところが、地方や民衆、商人にとっては混乱が生じ、迷惑をこうむった。
太陽暦の採用が発布されたのは、採用日の二十余日前のことであった。暦屋はす
でに来年の暦を作り、販売を始めてた。その回収で大損害が生じた。
また、各地の役場では、新しい暦の送付や配布がないままに事務を取り扱ったた
め、その後も旧暦で日付を記入していたという。
<1.その一へ><1.その二へ> <1.その三へ><1.その四へ> <1.その五へ><1.その六へ> <1.その七へ><1.その八へ> <1.その九へ><1.その十へ>
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd