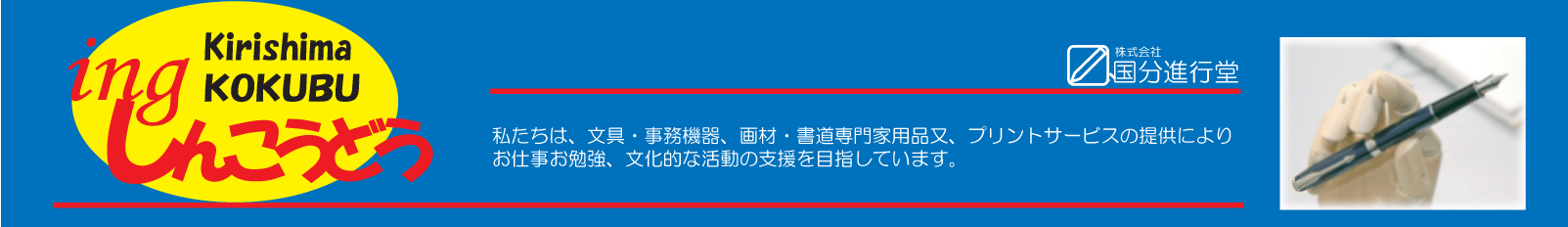

特別連載
<1.その一へ><1.その二へ> <1.その三へ><1.その四へ> <1.その五へ><1.その六へ> <1.その七へ><1.その八へ> <1.その九へ><1.その十へ>
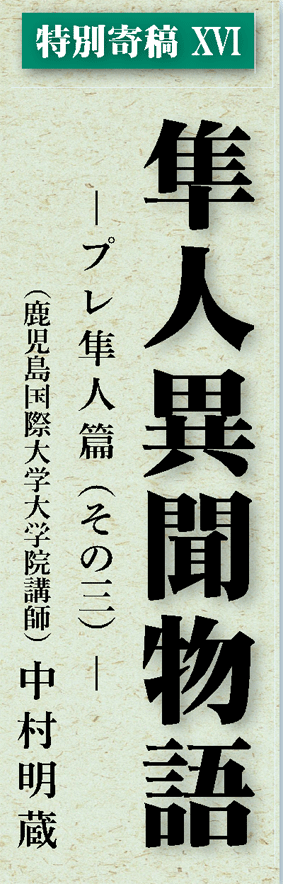
古代では、人が死ぬとすぐには埋葬せず、しばらくは遺体を特定の場所に
安置して祭る風習があった。
このような風習をモガリ(殯)といっている。一般庶民の場合は、習俗として
は伝えられ、その痕跡が残ることはあっても、その記録が残っていることは稀で
あろう。三世紀の倭の習俗を伝える『魏志』倭人伝には、人が死ぬと十余日は喪
に服し、肉を食せず、喪主は哭泣(こっきゅう)し他人は歌舞飲食し、葬った後に一家は水中で
禊(みそぎ)をする、とあるのは、モガリの原初的一例であろう。
また、『日本書紀』を中心とした歴史書には、主に天皇のモガリが記されてお
り、殯宮儀礼(ひんきゅうぎれい)などと称されている。すなわち、天皇崩御後、殯宮が建てられ、殯
宮内に皇后・皇太后・皇女などの肉親女性が籠(こも)り、遊部(あそびべ)が奉仕して儀礼が行
なわれた。遊部はその祭事で霊の蘇生と鎮魂を祈ることを職としていた。
いっぽう、殯庭では皇太子以下皇子、有力豪族の氏上(うじのかみ)などが慟哭(どうこく)し、誄(しのびごと)
(謙辞・弔辞:るいじちょうじ)を述べる儀礼が、くり返し行なわれた。この殯庭儀礼では、ときに
次代の皇位をめぐる対立や、豪族たちの政争が浮上、露呈されることがある。
その一部は、あとで述べることにしたい。
モガリ(殯)の期間は短くて数カ月、長いときは数年、あるいは五年以上にも
およぶことがある(敏達(びだつ)天皇は五年八か月、斉明(さいめい)天皇は五年三か月)。その期
間の長短は、陵墓の築造期間に対応するのでもあろうが、先述した皇位継承
や政争も影響しているとみられる。
王家の殯宮と類似で、小規模な構造の送葬習俗は各地に残存していた。伊
豆諸島・南西諸島あるいは対馬などでモヤ(喪屋の意か)・イミヤ(忌屋の意
か)などと呼ぴ、墓地に屋形状の小屋を造り、ときにその中に近親者が籠る場
合もあるという。
南西諸島では、鹿児島県沖永良部島でモーヤという小屋に棺を置いて、親
子・兄弟が数日間そこで時々棺を開けて死体を見たりする。また、沖縄県津
堅島では薮の中に風葬したのち、遺族や親戚が毎日訪れて死者の顔をのぞ
き、死者が若者であれば、生前の遊び仲間の青年男女が酒肴や楽器を持って訪
れ、顔をのぞいた後で、歌い踊って慰めたという。さらに、奄美大島では石囲い
の古墓をモーヤ・ムヤなどという所があるが、これらもかつてはモガリのような
習俗があって、その痕跡と推定されるという。
伊豆諸島では、イミヤ(神津(こうづ)島イミカド(三宅島)・カドヤ(新島)などと称
する仮屋を寺の境内や、村から離れた山間に作って、死者の子息が二十五日
から数ヵ月籠る習俗が、近年まで残っていたという。
モガリあるいは類似の行為・行動は、上は支配者層から民衆にいたるまで、
またその地域的広がりもあって、日本列島に住む人びとの、死に対する基層
観念の、ある部分を垣間見せているようである。
死者を生者の世界から遠ざけ、隠してしまおうとする思考や、死を稼(けが)れと
する見方、畏怖(いふ)の対象とする感覚があるいっぽうで、・死者を悼(いた)み、遺骸を離れ
ず、長期にわたって死者と生活を共にしたいという強い願望が共存しているの
である。
神話で、イザナキが亡くなった妻のザナミをたずねて黄泉国(よみのくに)に行き、妻の死
体にウジがたかり、雷(いかづち)が死体の各部分に巣くっているさまを見て、驚愕(きょうがく)し逃げ還
るようすが語られている。これもモガリの様相を伝えているようである。
遺体を長期間安置すると、腐敗し、蛆虫(うじ)がわき、異臭が立ち込めてくるこ
とは想像に難くない。そして、やがては白骨化が進んでくるであろう。そのな
りゆきを熟視することで、人びとは死を受け入れ、納得するのであろうか。
かつて、脳死状態での臓器摘出の議論がさかんであったとき、日本人の一部
がそれに強く反対する動きを見て、筆者はモガリの習俗が日本人の感覚の基
底にいまも伝存している、と思ったことがあった。生きている人体の臓器提供
など、論外であったのであろう。
さて、王家の殯宮儀礼にもどろう。
殯宮儀礼の場が、政争露呈の場になった一例をあげてみよう。六世紀の末
に敏達天皇が崩御(五八五年八月)、広瀬(現、奈良県北葛城郡)で殯宮が営ま
れた。そのときの大臣(おおおみ)は蘇我馬子(そがのうまこ)であ
り、大連(おおむらじ)は物部守屋(もののべのもりや)であった。大臣・大
連は天皇の下にあって最高の地位を占めていた。いわば二人制の首相のごとき
存在であった。
この二人が並んで誄を述べることになった。二人は、しばらく前から仏教の
受容をめぐって対立していた。蘇我氏は五三八年(五五二年説もあり)に百済の
聖明王から仏教が伝えられると、馬子の父稲目(いなめ)が崇仏(すううぶつ)の態度を示し、物部尾
輿(おこし)らの排仏派と対立したが、それが相互に子の世代にまで引き継がれて争っ
ていた。
父から子へと二代にわたる争いであったから、その対立には根深いものがあ
り、争いを引き継いだ両人が、並んで誄を述べようとしていたのであったから、
緊張はおのずから高まっていた。
殯庭で誄を述べる二人のようすを『日本書紀』は、つぎのように伝えてい
る。まず、馬子大臣が大刀をつけて誄をすると、守屋大連はあざ笑って「まるで
猟箭(ししや:猟に用いる長い矢)で射られた雀のようだ」といった。つぎに大連が手足
をふるわせながら誄すると、大臣が笑って「鈴をつけたらよく鳴るだろう」と
いった。これによって、二人はいよいよ怨恨(えんこん)をいだくようになった。
いっぽう、王家の忠臣三輪君逆(みわのきみさかう)は、隼
人に命じて殯の場所を守衛させた。また、穴穂部(あなほべ)皇子(欽明天皇の皇子の一
人で、皇位継承権を有する)は、異母兄弟の敏達天皇の殯宮儀礼がつづくので、
「どうして死んでしまった王のもとに奉仕して、生きている王(自分)のもと
に仕えようとしないのか」と高言して、忿懣(ふんまん)をぶちまけた。
殯宮儀礼の場は、このように政争の場にもなり、次代の皇位をめぐる争い
の場にもなっていた。そのような場にも隼人はかかわっていたのであった。
皇位は、敏達天皇が亡くなった翌月に、異母兄弟の用明天皇が継ぐことに
なり、即位した。しかし、その後も穴穂部皇子の不満はおさまらず、翌五八六
年の五月に、皇子は炊屋姫(かしきやひめ)皇后を姧(おか)そうとして、むりやりに殯宮に押し入ろ
うとした。そこでも寵臣(ちょうしん)の三輪君逆は、兵衛(ひょうえ)を召集して宮門をとざし、守りを
固めて入るのを拒(こば)んだ。
兵衛は、のちの令制による官司(兵衛府)であり、宮門を守る役目をもってい
たので、ここではその用語を時期をさかのぼらせて用いたのであろうが、その実
態はさきの隼人と同義であろうと思われる。ただ、隼人が単独でその役目を負
うことはできないので、個人的な近習よりはしだいに組織的守護役に発展し
ていたことは認められるであろう。
隼人は早く五世紀には、王家あるいはその親族に深く仕えるようになって
いたが、それから一五〇年以上経た敏達朝前後になっても、その伝統は継続し
ており、天皇の遺骸が安置されている殯宮を守る役割を果たしていたのであ
る。
このような王家と隼人との関係をみると、日向神話の、天皇家の祖に服従と
守護の奉仕を誓った隼人の姿が二重映しになって想起されよう。
『古事記』や『日本書紀』におさめられた神話によると、天皇家と隼人の関係
は次のように、それなりの論理を通した関係で物語られる。
すなわち、海幸、山幸神話において、兄の海幸彦は隼人の祖として、また弟
の山幸彦は皇祖として語られ、釣針を失くした弟を責めた兄は、のちに弟が
海神から授けられた潮盈(みつ)珠・潮乾(ふる)珠によって懲らしめられたとき、「僕(あ)は今よ
り以後(のち)は、汝命の昼夜の守護人と為(な)り
て仕え奉らむ」といったという。
この神話は、隼人が天皇家に仕える事実をふまえて、その由来を説明しよ
うとしたのであるが、隼人の祖と皇祖を兄弟とまで近接させた関係で結びつ
けた背景には種々の憶測が生まれるであろう。
『古事記』も『日本書紀』も八世紀初めに成立しているが、そこで語られる神
話、とりわけ隼人が天皇家に仕えるようになった由来を語る神話の背景は、
五世紀以来の隼人の奉仕の姿にある、ということができよう。
ところで、殯宮儀礼の途上で起こった蘇我氏と物部氏の対立の激化は、そ
の後どうなったのであろうか。また、穴穂部皇子や三輪逆はどうなったのであ
ろうか。その後のなりゆきと、その結末を見とどけておきたい。
炊屋姫皇后が殯宮に籠り、儀礼を行なっているところに強引に入ろうと
して拒まれた穴穂部皇子は、門を固めている三輪逆に、「門をあけろ」と呼ば
わった。七回も。それでも三輪逆はそれに応じなかった。
そこで皇子は、大臣の蘇我馬子と大連の物部守屋に、三輪逆の無礼を告げ、
自分は殯宮で誄をして、「朝廷を荒さず、鏡の面のように浄らかに保って、奉
仕するつもりだ」といい、「逆を斬ってしまいたい」とも告げた。大臣・大連の二
人は、「まことに、ごもっともです」と答えた。
あくまでも皇子は皇位につくことをねらい、逆を殺すことを口実に、守屋
大連とともに軍兵をひきいて、磐余(いわれ)の皇后の地を囲んだ。逆はこの動きを察
知して、三輪山に身を隠し、夜半になって、ひそかに山を出て炊屋姫皇后の後
宮(こうきゅう:海石榴市宮=つばきいちのみや))に隠れた。
しかし、逆の居場所を密告する者がおり、大連は軍兵をさし向け、逆を
斬った。馬子大臣はそれを知って悲しみ、「天下の乱れるのも遠くはあるまい」
と歎いた。
用明天皇の二年(五八七)、いよいよ決着をつける時がきた。この年、病に悩
んだ天皇は仏教に帰依(すがること)せんことを群臣たちにはかった。
これに物部守屋大連と、朝廷の祭祀を司どる中臣勝海(かつみ)が反対した。崇仏派
の中心、蘇我馬子とそれに従う鞍部多須奈(くらべのたすな:渡来人で仏教の信奉者司馬達等
の子。鞍作止利の父でもある)などは賛成した。大連と大臣はそれぞれ兵を集
め、両者の対立は激しくなった。その間に、中臣勝海は殺され、天皇は死没し
た。
大臣の馬子は、皇后(のちの推古天皇)を奉じて穴穂部皇子を殺す。ついで
馬子は泊瀬部(はくせべ)皇子(次代の崇峻天皇)・厩戸(うまやど)皇子(用明天皇の子、のちの聖徳太
子)らとともに、物部守屋大連を滅ぼすことを実行した。
以後、大臣・大連の二頭体制は崩れ、大臣だけの専制政体が長期にわたって
持続されることになった。大臣の馬子は用明天皇のあとの崇峻天皇を殺害
させて、そのあとに最初の女帝となる推古を即位させ、女帝は三十六年にわ
たって在位することになった。
その間に、聖徳太子が摂政をつとめているが、太子は馬子からすると孫の
世代であり、また太子の父(用明天皇)・母(穴穂部間人皇后:あなほべのはしひと)はともに蘇我系
の血を引いていたから、太子の業績とされる諸事業の影には、馬子の姿が見え
隠れしている。ちなみに、推古天皇は馬子の姪であったから、背に叔父の圧力を
常に感じながらの在位ではなかったか、との想像も可能であろう。
ここで、あらためて古代の皇位継承について考えてみたい。すでに見てきたよ
うに、皇位は父子継承の場合もあったが、兄弟継承の場合が目につく。五世紀
の履中・反正・允恭の例や、それに続く安康・雄略の例があった。六世紀はどう
であろうか。じつは六世紀でも兄弟継承は行われていたのである。
ただ、異母兄弟間の継承であったから、五世紀の場合よりはやヽ複雑であ
る。一夫多妻の婚姻では、異母兄弟が多いから、その間の継承があっても当然で
もあろう。しかし、異母兄弟間の皇位をめぐる対立・争いは、それぞれの母の背
後勢力間の抗争もあいまって、複雑である。六世紀末から七世紀にかけて、欽
明天皇の異母兄弟たち、敏達・用明・崇峻・推古の四代が続いている、その間に
は、先に述べた穴穂部皇子の皇位をねらう事件があり、崇峻が暗殺される事
件も起こった。さらには、最初の女帝推古も即位している。
そして、さらにつぎの世代を見ると、そこにひとつの傾向があることが読み
とれる。それは天皇の母が皇女の場合と、豪族(蘇我氏など)の娘である場合
の違いである。前者の場合は次世代への皇位継承はあっても、後者の場合では
継承が見られないことである。といっても、それは偶然の重なりともいえるの
で、あくまでも「傾向」ほどのことであって、「原則」とまではいえないであろう。
七世紀の前半最終期には、「大化の改新」と呼ぼれる政治改革がスタートす
る。その発端となったのが、六四五年の乙巳(いつし)の変である。中大兄皇子・中臣鎌
足らによって蘇我本家の(えみし)蝦夷・入鹿(いるか)父子が滅ぼされた事件である。
よく知られた事件である。いまは中大兄という、その名の「大兄」に注目し
たい。大兄は長男の意であるが、皇子であれば皇位継承権をもつ皇太子の意で
もある。ところが、一夫多妻の場合は、大兄は複数いることがあり、問題が生
じやすい。
中大兄皇子は舒明天皇の子であるが、同じ天皇の子で、母親違いの古人(ふるひと)大
兄皇子がいた。中大兄より年上であった。舒明天皇のあと、皇后が即位して
皇極天皇になっていたが、その後継をめぐって二人の大兄の間では暗黙の対立
が生じていた。
その間に、古人大兄は身の危険を察知していた。古人大兄は舒明天皇の皇
子ではあったが、母の法提郎女(ほてのいらつめ)は蘇我馬子の娘であり、蝦夷とは兄妹であっ
た。そこで、古人大兄は出家を決意して、仏道修行のため吉野に入った。し
かし、中大兄は周辺から、古人大兄が謀反(むほん)したことを知らされ、刺客を送り
込んで殺害させてしまった。
皇位の兄弟継承の順位を定めた形の「大兄」の出現であったが、異母兄弟間
では母の出自の優位性や、時の政局の動向などがからみ合って皇位継承は揺
れ動いた。中大兄や弟の大海人(おおあま)は父(舒明)に次いで母(皇極)も天皇であったか
ら、系統的には皇位につくのは当然のようであるが、次代の天皇には叔父に
あたる孝徳天皇がつき、中大兄は皇太子となって、一応の決着となった。
このような政争や対立の間に、皇子たちの近習や護衛の役割をつとめてき
た隼人の後裔(こうえい)たちは、どうしていたのであろうか。
『日本書紀』は、そのことについては黙して何も語っていない。おそらく、どこ
かで下働きをさせられていたはずである。これまでの隼人の動向からすると、
政権主導者たちのごく周辺で、命じられるままにその職務をつとめていたと
推測されるが、史書編纂者にとっては、歴史の激動に目を奪われて、瑣末(さまつ)な事
にこだわる余裕はなかったのであろう。
それでも『日本書紀』の編纂者は、隼人の忠実な職務遂行を、「諸(もろもろ)の隼人等(たち)、
今に至るまでに天皇の宮墻(みかき)の傍を離れずして、代(よよ)に吠(ほ)ゆる狗(いぬ)して奉事(つかえまつ)る者な
り」と評している。
改新の事業は、朝鮮半島への出兵、白村江での敗戦、皇位継承をめぐっての
壬申(じんしん)の乱などで停滞しつつあったが、その後に即位した天武天皇によって大い
に進められた。それはまた、持統天皇にも引き継がれた。その結果は隼人社会
へも変動をもたらした。
じつは、「隼人」の呼称は、この時期から用いられたとみられ、これまで使って
きた用語は遡及(そきゅう)的に借用したもので、『古事記』『日本書紀』の用例に従った
までである。いわば「プレ隼人」とでも呼んだほうが、当っていたのであろう。
そのプレ隼人も、時代区分ができそうである。まず、五世紀の近習隼人の時
代で、住吉仲皇子や雄略天皇に仕えていた。『日本書紀』によると、日向の諸県
君(もろかたのきみ)が仁徳天皇とその前代に妃を朝廷に入れているので、その勢力を背景に志布
志湾沿岸部から上京して仕えるようになったのであろう、と推定される。
つぎの段階は六世紀末から七世紀初めにかけての時代で、隼人は「兵衛」に擬
せられていた。兵衛府はのちの宮門警備などをつとめる官司であり、組織的な
機構である。したがって、その表記が用いられているところからすると、五世紀
段階の近習よりは、組織的に発展して仕えていたのだろう。殯宮の守衛もそう
推定することによって可能になろう。
このようなプレ隼人の時代を経て、天武朝からの「隼人」の時代を迎える。
政権は領域拡大をめざして、南部九州への侵攻に力を注いだ。しかし、南部九
州の中心部の攻略は、なかなか進まなかった。とりわけ、志布志湾沿岸部から
肝属川を遡上して北進する戦略は、途中から曽君勢力に拒まれ難航した。
いっぽうの九州西岸から、川内川を遡上する攻略は薩摩君に拒まれたが、
この地域の北部には、すでに肥後の勢力が進出しており、その肥後勢力と政
権は同盟を結ぶ計画が進められていた。
そこで、大隅・薩摩両半島部への侵攻を先行させ、両地域を、まず勢力下に
置き、朝貢と住民移住を強行したのであった。
その結果が『日本書紀』の六八二年七月に記されている。
隼人が数多く来て方物(くにつもの:土地の産物)をたてまつった。同日、大隅隼
人と阿多隼人が朝廷で相撲をとり、大隅隼人が勝った。
隼人の朝貢はここに姶まり、以後八世紀の終りまで続く。なお、相撲は服属
儀礼の一種とみられる。
いっぽうで、隼人の畿内移住も集団的に進められ、畿内各地にその痕跡が
残されている。また、六八五年六月には大倭連(やまとむらじ)など十一氏に「忌寸(いきみ)」姓が授けら
れ、大隅直氏もその中に入っている。前年十月に定められた八色の姓のうちの
四番目の姓であるが、直姓は大隅のみで他の十氏は連姓である。全体的には
畿内で国造(くにのみやつこ)などをつとめた氏が多く、それなりの来歴をもつ氏であり、大隅
直は異色である。したがって、この賜姓に与った大隅直は、プレ隼人の系譜を
もつ一族の可能性が大きい。
六八六年九月には天武天皇が没し、以後二年二ヵ月にわたって皇后を中心
に殯宮の儀礼が行われる。このときの殯庭で天武の皇子の一人、大津皇子が
皇太子(草壁:くさかべ皇子)に謀反を企てた。皇位継承をめぐる一例ではあるが、大津皇
子は「容姿たくましく」「学才にすぐれ、文筆を愛した」人物で、人望を集めてい
ただけに、死を賜わったことに対しては、計略にはめられたとの声もあった。
翌年五月の殯庭では、皇太子が公卿・官人たちを従え発哀した。このと
き、大隅・阿多の隼人の首領(魁帥)がそれぞれ配下の人びとを従え、互いに進
み出て誄をした。
ここでは、畿内に移住した隼人が、天武天皇の後継となる皇后(持統)と皇
太子に対して、忠実なる服属者になることを誓ったのであった。
<1.その一へ><1.その二へ> <1.その三へ><1.その四へ> <1.その五へ><1.その六へ> <1.その七へ><1.その八へ> <1.その九へ><1.その十へ>
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd