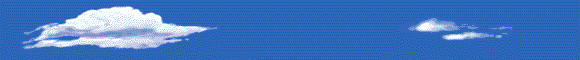
患者が主人公になれる図書館
―静岡県がんセンター「あすなろ図書館」見学記
2002年9月に開院した静岡県立がんセンターに、日本で初めて専任司書が配置された患者図書館「あすなろ図書館」が開館したニュースを耳にして、いつか実際に見学したいと思っていた。その機会は意外に早く訪れた。2003年8月、愛知ホスピス研究会主催の「いのちの授業」に招かれた私は、前日に三島市郊外にある静岡県がんセンターを訪問した。
院内に入るとすぐに目につくのが、グランドピアノがおかれ、高級ホテルを思わせるメインホール。一般利用者にも開かれている「あすなろ図書館」は、このホールに面している。病院の患者図書館にかける意気込みを象徴しているかのようであった。
あいにく専任司書の菊池さんは、夏の休暇中で、直接お会いできなかったが、図書館案内によると、蔵書は約4000冊。うち3000冊あまりが一般図書。残りが、医学関連図書で、雑誌、新聞、ビデオ、CD、DVDもある。
かつて、知りたがりやのがん患者であった私の関心はやはり医療情報コーナー。がん関連書はさすがに充実している。がんの部位別に治療や病気の説明の本。薬や検査や体の構造の本、がん関連小冊子、がん関連切抜きファイル、闘病記(私の本もありました)、患者団体の本などいたれりつくせり。雑誌も豊富。健康、医療一般の雑誌だけでなく、がん関連の定期刊行物は、バックナンバーまで配架されている。インターネットのお気に入りの項目をみて、息をのんだ。よくこれだけチェックできたなあと感嘆する充実ぶり。これなら、日ごろインターネット利用になじんでいない患者や家族にも、比較的簡単に欲しい情報を入手できそう。来館できないときは、ベッドサイドにある端末からキーワード検索し、届けてもらうこともできる。
「患者本位のインフォームドコンセント」や「患者が主人公の医療」などほとんど望みえなかったころに、がんを体験した私は、告知を受けても、医療者から専門用語を交えて一方的に伝えられる情報以外には、自身の体がどうなっているかを知る手立てがまったくなく、暗闇を手さぐりですすむような不安感にさいなまされた。退院した後になって、ようやく生きるための情報をもとめて右往左往した。こんな図書館が入院している病院にあれば、とつぜんがんの宣告を受け、いやおうなしに深刻な病気とむきあわざるをえない患者にとって、どれほど心強いことだろう。ここで提供される情報は、特定の治療法をすすめるものではないことも断ってある。あくまで情報を選び、判断するのは患者自身なのである。
この病院の基本方針に「患者参加型医療の促進」「患者に学ぶ姿勢の堅持」「こころ通う対話に基づく全人医療の実践」という項目がある。専任司書のいる患者図書館は、この方針の実現に欠かせないものとして、病院組織のなかにきちんと位置づけれているのだろう。
あすなろ図書館で聞き漏らしたのは、公共図書館とのネットワークである。利用案内には、あすなろ図書館にない本の予約サービスについて触れられていなかったので、まだ実現されていないのかもしれない。
最近、一般病院にも患者図書館をつくる動きがでてきた。ただ、厳しい財政状況もあって、継続的な図書費の確保や専任司書の配置などおぼつかないところがほとんどのようだ。そういうところでは、選書や配架やレイアウトなど、公共図書館と協力関係を築くことで、専門家のもつノウハウを活かすことができるはず。運営面でも、予約サービスやレファレンスなどを取り入れてかなり充実したサービスが期待できるのではないだろうか。
なお、菊池さんは、その後退職され、全国の患者図書館のためのコンサルトを開始された。都心にある病院患者図書館協会の事務所では、患者図書館司書養成講座が開かれたり、無料で利用できる「いのちの図書館」が開設されている。ホームページhttp://www.jhpla.jp/ には、遠隔地からでも健康法や治療法に関する文献検索ができるWEB患者図書館もある。今後あすなろ図書館のような患者図書館づくりを広める拠点になっている。
○関連ホームページ
静岡県がんセンター
![]()
子どもに親のがんを告げる絵本
「月のかがやく夜に−がんと向きあうあなたのために―」 リサ・サックス ヤッファ作 遠藤恵美子訳 こばた えこ絵 先端医学社
この本は、静岡県立がんセンターの患者図書館「あすなろ図書館」に『葉っぱのフレディ』や『種まく子供たち』など、私がいつも「いのちの授業」に使っている本に交じって、面展示されていた絵本である。
この絵本は、1998年にアメリカがん看護協会から「がん」にかかったおとうさんやおかあさんが、そのことを子どもたちにはじめて伝えるときに、また、これからのことを家族みんなで話しあって考えていくときに、役立ててほしいとつくられた絵本で、 2001年に日本語に翻訳されたもの。巻末に専門家によるがんのQ&Aがついている。先月紹介した『レアの星』のように一般の児童書出版社ではなく、医学書専門出版社から発行されたせいで、書店の店頭では見かけることはほとんどない。
翻訳者の向山 雄人氏は、1981年東海大学医学部卒業後、東京都立駒込病院、癌研究会附属病院レジデント、米国マサチューセッツ工科大学(MIT)研究員を経た後、癌研究会附属病院化学療法科、東京都立駒込病院化学療法科医長を歴任したがん専門医。現在は東京都立豊島病院緩和ケア科・腫瘍内科医長として診療、研究、教育に携わっている。
遠藤 恵美子氏は、東京女子大学短期大学部英語科卒業し、さらに国立東京第一病院附属高等看護学院卒業後、看護婦、保健婦、看護教員などの職歴を経た後、渡米しミネソタ大学大学院にて看護学を専攻。がん患者・家族とのパートナーシップという立場で研究に取り組み、現在は北里大学看護学部教授。成人・老人看護学ならびにがん看護学を担当。がん患者と家族の会やセルフヘルプ・グループのサポーターとしても活躍している方である。
10月18日、19日の2日間、鹿児島緩和ケアネットワークの大会があった。がん医療に関心をもつ医療者が中心の会ではあるが、ひろく宗教者やボランティア、一般市民も参加している。今年のテーマは「市民の視座からがん医療を考える」で、メインゲストは『看護婦ががんになって』の著者、土橋律子さん。土橋さんは、千葉で大学病院の看護婦をしていた32歳のときから、3回もがんを体験した方。その後、医療者と患者を結ぶ「ささえあいの会・α」http://www.icntv.ne.jp/user/alpha/index.htmをつくって活動されてきた。私も、土橋さんとの対談という役割をいただいて、大会に参加した。
大会のなかで、がんの告知の方法について議論がなされた。鹿児島の場合は、まだまだ本人に告知する前に家族に告知の是非を相談する場合が多く、家族に反対されて告知が進まない実態があるようだ。たとえ,本人への告知がなされても、その後の精神的なフォローができないケースがほとんど。土橋さんが行っているような患者同志の支えあいの組織が近くにあればいいが、大抵のがん患者や家族は、どこでどうして情報を得られるかさえもわからず,途方にくれることになる。
まして、働き盛りで、まだ小さい子どもがいる患者の場合、子どもに親の病気をどう伝えればいいのか悩むことになる。子どもへの告知方法を相談する人も身近に存在しない人の方が多いに違いない。
しかし、そういう場合に、こんな絵本があれば助かる。子どもといっしょに読むことで、自然に気負いなく告げることができる。子どもも、親ががんになるという不幸な体験をする子どもは自分だけではないことを知ることになるだろう。
この絵本は、鹿児島のホスピス機能をもつ診療所、堂園メディカルハウスのサイトhttp://www.dozono.co.jp/dmh/ronbun04.htmにも「遺される子供のための絵本の処方箋」と題した論文のなかでも紹介されている。堂園晴彦院長は、大切な人と永遠の別れをする子供たちに、死を教えたり、残された時間を有意義に過ごせるようにサポートするのも、終末期医療の大切な役割だとしている。
![]()