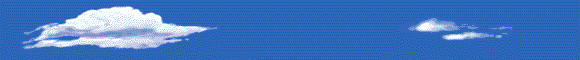死を学ぶ子どもたち PART2 第28回
あたらしく出会った「いのちの本」
私の「いのちの授業」が、先日の熊本県宇土市立宇土小学校で111校になった。
宇土小は、5〜6年生あわせて300名以上もいたのだが、長い時間集中して話を聞いてくれた。わずか5分の休憩時間には、紹介した本の周りに人だかりができ、寸暇を惜しんでみんな本を開いていた。
どこの学校に出かけても、同じ光景を目にする。本との橋渡しの場がありさえすれば、子どもたちは本が大好きなのだ。
ときどき、いのちの授業で使っているブックリストが欲しいとメールをいただく。私が使っているリストは、以前蔵満先生が担任されていた寿北小6年4組のHP
http://www.d2.dion.ne.jp/~merody/tanemurabpooklist.htm
と「種まく子供たち」の「いのちの教室」
http://www.cypress.ne.jp/donguri/life/class/booklist.html
にある。
今回は、これらのリストには、まだでていない「いのちの本」を紹介したい。
ただし、最近出会ったばかりで、これらの本を取り入れた「いのちの授業」はやっていない。
『いのちは見えるよ』
及川和男作 長野ヒデ子絵 岩崎書店 2002.2発行 小学校低学年から
著者は『森は呼んでいる』(岩崎書店)で、畠山さんたち漁師さんの森づくりをいち早く紹介した及川和男さん、絵は『おかあさんがおかあさんになった日』などで知られる長野ヒデ子さん。これまでも「いのち」を伝える本を数多く手がけてきたコンビによる最新の絵本。
エリちゃんのおとなりに住んでいるアキラさんとルミさんは、ふたりとも目が不自由で、アキラさんは、マッサージの仕事、ルミさんは、盲学校の先生をしている。ふたりには、もうすぐ赤ちゃんが生まれる。ところが、頼みのアキラさんが、骨折して入院してしまった。そんなある日、ルミさんの陣痛が始まった。病院についていったエリちゃんは、出産に立会う。やっと、女の赤ちゃんののぞみちゃんが生まれた。エリちゃんの胸に、ぐぐっとあついものがこみあげてくる。
退院したあとも、エリちゃんは毎日のぞみちゃんを見に行く。目がぜんぜん見えないルミさんが、「いのちは見えるよ」と話してくれた。「いのちがみえる」って、どういうことだろう?
やがて、エリちゃんのクラスにルミさんとのぞみちゃんがやってきた。みんなはのぞみちゃんをだっこさせてもらった。
目の不自由なルミさんに見える「いのち」とは?読んでいくうちに、主人公エリちゃんといっしょに答えを探っていけそうな気がする。クリーム色を基調にして、単純な線で描かれた長野ヒデ子さんの絵が温かい。
『わたしのおとうと、へん・・・かな』
マリ=エレーヌ・ドルバル作 スーザン・バーレイ絵 おかだよしえ訳 評論社 2001.9発行 低学年から
『わすれられないおくりもの』でおなじみのアナグマやうさぎやもぐらの絵を表紙に見つけて、思わず手にとった。これは、フランスの「幼年期と染色体異常を考える21世紀の会」の提唱でつくられた絵本だそうだ。
うさぎのリリに、おとうとのドードが生まれた。とってもかわいいが、ちょっとへん。ちっとも大きくならないし、お口もうまくきけない。スープはこぼすし、おもらしもする。ともだちは、ドードのことをからかってばかり。ママやパパも、ドードをあまやかす。ママのおなかにいたとき重い病気になったドードは、ずっと子どものままなのだ、という。ドードをあまやかすのはだめだと考えたリリはあらゆる手立てをつくすのだが、とつぜん、どうすればいいかわからなくなる。そんなリリの前にあらわれたふくろうおじさんは、「いまのままのドードくんをすきにおなり」とアドバイスしてくれる。
障害のある兄弟をもつ子どもの立場で書かれた絵本は、実話である『わたしたちのトビアス』があるが、これもうさぎのリリの気持ちになって、ドードにとってなにが必要かを考えるきっかけを与えてくれる絵本である。
『おにいちゃんが病気になったその日から』
佐川奈津子文 黒井健絵 小学館
2001.8発行小学校中学年から
なかのよかったお兄ちゃんがとつぜん頭が痛いと叫びだした。その日以来、お母さんとお兄ちゃんは、ぼくの前からいなくなった。ぼくさえがまんしていい子にしてれば、お兄ちゃんは元気になれるんだと思ったけれど、いつまでたってもよくならない。ぼくだって、お母さんといっしょにいたい。でも、そう思うのはいけないこと。ぼくは、じぶんをしかった。
家族の誰かが重い病気になって入院することは、たいへんなことだ。とくに子どもが病気になると、周囲の関心は、すべて病気の子に注がれてしまう。病気の子も、もちろんつらいのだが、その兄弟姉妹も同じようにつらい思いをしている。だが、元気な兄弟姉妹の淋しさ、不安、いらだちに寄り添える大人は少ない。この本は、幼いころ、弟が重い病気になってしまった著者が自身の体験をもとに、「たとえ兄弟が病気でも、楽しいときは笑って、悲しくなったら泣いていいんだよ、今までのきみでいいんだよ」と伝えたくて書いた本。
『世界がもし100人の村だったら』
池田加代子再話 ダグラス・スミス対訳 マガジンハウス 2001.12発行 高学年から
ご存知インターネットで世界をかけめぐった「現代民話(?)」が、本になったもの。世界の人口63億人を100人に縮めたら、違う世界がみえてくる。私自身も同時多発テロの発生から間もない昨年の9月末、あるMLで、このメールを受け取った。ショックだったのは、「すべての富のうち6人が59%をもっていて、みんなアメリカ合衆国の人です。」「たった1人が大学の教育を受け、たった2人(メールのときは、1人だった)がコンピュータをもっている」という個所であった。さっそく、大学の講義や中学での「いのちの授業」で紹介した。
本には「中学校に通う長女の担任は、生徒たちに、毎日メールで学級通信を送ってくださるすてきな先生です」の前書きがついている。そのすてきな先生も私が受け取った同じMLに入っていらっしゃるらしい。(そのへんの事情は、その生稲勇先生自身が現在中高MMで連載中)
http://www.synapse.ne.jp/~kanoyu/sukaji/touroku.html
『僕たちは、自由だ』
クレイブ・キールバーガー 佐光紀子訳 本の泉社
2000.6発行 高学年から
この本だけは、かなり前に出会っていたのだが、なかなか紹介する機会がなかった。
『100人の村』にも「20人は栄養がじゅうぶんでなく、1人は死にそうなほどです」とある。豊かな日本に住んでいる私たちは、つい忘れがちになるが、家族の食料がじゅうぶんでなく、幼いうちから重労働にかりだされている子どもたちが世界にはたくさんいる。この本は、そういうアジアの児童労働の実態を同じ年頃のカナダの少年の目で記したものである。
カナダの少年クレイグは、12歳のある朝、ふと見た新聞でパキスタン人少年イクバル・マシーが殺されたという記事を読んだ。幼いころ奴隷のように働かされ、後に子どもたちの権利を訴えて世界をまわっていたイクバルの生と死に、強いショックを受けたクレイグ。そしてある日、クレイグは南アジアへの旅にでかける。働かされている子どもたちに会うために。
そして、自分にできることを知るために…。
クレイブの活動は、児童労働から子どもたちを救い出す「フリー・ザ・チルドレン」
http://homepage2.nifty.com/FTCJ/index.html
![]() トップ
トップ