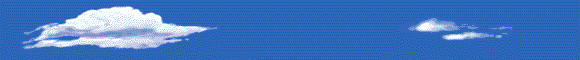連載 死を学ぶ子どもたち PART2 第23回
「子どもにがんを告げる」
「子どもにがんを告げる」には、ふたつのケースが考えられる。
ひとつは、子ども自身ががんにかかったとき、その病名を告げるかどうか。
告げるとすれば、誰がどんな風に告げるのがいいのか。
もうひとつは、親や祖父母、兄弟など身近な家族ががんにかかったとき、子どもに告げる方がいいのか。告げるとしても、子どもが幼児や小学校低学年ぐらいの場合はどう説明すればいいのか。
私はちょうど1年前の夏、ドイツの小児病棟を訪れた。このMMでも、2〜3ぐらいからがんという言葉を使ってきちんと伝えるという取り組みを紹介している。
この春刊行された『種まく子供たち』の佐藤律子さんは、あとがきで「これは告知をすすめる本ではない」と記している。
その『種まく子供たち』のドラマを最近テレビで見た。
ミニバラ色の種、加藤祐子さんの最後の夏をテーマにしたもの。祐子さんは、2000年2月19歳で旅立った。
ドラマを見て、涙がとまらなかった。そういえば、佐藤律子さんから初めてのメールをもらったのが、祐子さんがなくなる1ケ月ほど前のこと。「種まく子供たちの7人のなかには、今生死の境で必死に頑張っている人がいる」と記してあった。
『種まく子供たち』に祐子さん自身が書いた文章によると、13歳で白血病になった祐子さんには、当初貧血と説明されていたようだ。偶然見つけた1枚のメモで「白血病」と知ったとある。それでも主治医から正式に告知されるまで、両親にも話すことができなかったそうだ。
結果的に『種まく・・』の子どもたちは、幼い育ちゃんをのぞいて全員告知を受けている。亡くなった子どもたちも含めて「告知されて(して)良かった」と記してある。それでも、残念ながら今の日本の医療現場は、「告知した方がいい」と断言できる状態にはないようだ。
後のケース、家族ががんにかかった場合、それを子どもに告知すべきかどうか、私もときどき相談を受ける。
私ががんの告知を受けたとき、当時大学生と高校生だった息子たちには、夫がすでに知らせてしまっていた。
大きくなった息子たちは、十分受けとめられるし、母親を支える力もあると判断したらしい。
では、子どもがもっと小さい場合はどうだろう。私が「いのちの授業」で出かける学校でも、幼児や低学年のとき、親のがんと遭遇した子どもたちは予想外にたくさんいる。
私は相談を受けると、「子どもを信頼して、率直に子どもに伝える方がいい」と答えている。
いたずらに不安をかきたてないよう、誰がどんな風に話せばいいかは、十分考えたうえで、という条件つきだが。
ドイツではどうしているのか、昨年夏の滞在中は調べる機会がなかったが、あのとき小児科病棟を案内くださった二村エッケルト敬子さんから、最近ドイツで出版された絵本を訳文つきで送ってもらった。
タイトルは
Als der Mond vor die Sonne
trat (月が太陽をよぎったとき)。
内容は、8歳と5歳の姉弟の母親が乳がんと診断され、手術のために入院することになったという設定。この家族は祖父といっしょに暮らしている。祖母はがんで亡くなっている。「ママもおばあちゃんみたいにがんで死んでしまうの」と不安がる子どもたちに、大人は「ママは、早期発見だからおばあちゃんとは違う」と説明する。
医師が書いた本らしく、子どもにも分かりやすくがんとはどういう病気で、どんな治療が施されるかが語られている。巻末には大人にも役立つ専門用語の図解入り解説まである。
こんな本をぜひぜひ日本でも出版してほしい。
死を語るいのちのブックトークでも紹介したい。
![]() トップ
トップ