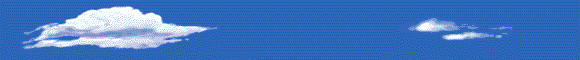死を学ぶ子どもたち PART2 第12回
「ドイツで学んだことーその1」
7月24日から3週間、夫の留学先ドイツのハイデルベルグに行ってきました。いちばんの目的は、涼しいところで、ゆっくり、のんびり過ごすということでした。夫の逗留先のアパートから、ハイデルベルグの城が見えるんです。夜はライトアップされて、とてもきれいでした。
最大の収穫は、ハイデルベルグ大学の医学部のキンダークリニック(小児病棟)を訪れる機会があったことです。たぶん、普通では行けない小児ガンの病棟も案内してもらいました。
「生と死の倫理」を中心に研究している夫が、ハイデルベルグ大学医学部卒の日本人医師、敬子・二村・エッケルトさん(彼女の専門は血管学、現在ボランティアでホスピスに関わっている方で、偶然ですが、夫と同じ愛知県立旭丘高校卒)と知り合って、彼女が紹介(兼通訳)しくださって、主に小児ガンなどの厳しい病気になった子どもたちとその家族へのサポートのことを知ることができました。
そこで,学んだことを二回に分けて報告します。
説明してくださったのは、ハイデルブルグ大学医学部・心理社会的腫瘍学研究所のヘベルレさん。部屋に入るなり、「実はきのう私たちの『Better
days camp』のプログラムのために16,000マルクの寄付もらったのよ」とうれしそうに報告されました。『Better
days camp』とは、小児ガンの子どもたちの夢をかなえるためのキャンプで、重い病気の子どもたちを10日間自然のなかに連れ出して、普段ならとても体験できないアドベンチャーを行うプログラムだそうです。写真を見ると、乗馬やロッククライミング、カヌーなどに挑戦している子どもたちの姿がありました。なかには、骨のガンで足を切断している子もいるそうですが、とてもそうは思えない明るさ、たくましさ。もちろん,専門スタッフやボランティアが慎重に準備するのでしょうが・・・。
ドイツでは、たとえ子どもでも病気のことを、ガンという言葉を用いて本人に必ず伝えるというのです。「いったいいくつぐらいの子
から,伝えると思いますか」と質問されて、私は「4〜5歳」と答えたのですが、なんと2〜3歳ぐらいからだそうです。言葉だけでなく、絵本やビデオなどが用いられます。小さい子にも分かるような絵本やビデオ、気持ちをほぐすぬいぐるみなどがヘベルレさんの研究室にもおいてありました。小児病棟には、もちろん、複数のサイコロジストが配置されていて、子どもと家族の精神的なサポートをします。
ドイツでも、そういう告知をするようになったのは15〜16年まえからだそうです。医師や家族によっては、死を話題にするのを避
けたがる傾向もあるとか。でもそれは,子どもにいい影響を与えない、というのがヘベルレさんの意見です。なぜなら、重い病気をかかえた子は死について知りたがっている、大人が避けるとよけいに不安感をもつというのです。
死のことを話題にするとき、よく使っている本ということで、真っ
先に出してこられたのが、『わすれられないおくりもの』のドイツ
語版。「私もよく使います」思わず声をあげてしまいました。
夫が「子どもに死後の世界について聞かれたらどう説明するか、例えば、パラダイスがあるということを伝えるのか」と質問したら、
まずその子がそれまで、親にどういう風に聞いてきているかを聞き出して、それを尊重する形で、死後の世界にも希望をつなげるようなメルヘンを使って話をする、ということでした。でも、こちらの考えを押し付けないように気をつけているとのこと。「なにしろ,私自身も行ったことないので、パラダイスの存在に確信もっているわけではない」ユーモアを交えて答えてくださったのが印象的でした。
かの有名なキューブラー・ロスがパラダイスの存在を確信的に伝えているのと対照的で興味深かったです。
子どもが亡くなるときは、家で看取りたい場合はその希望に添えるよう援助するそうです。病院で亡くなるときは、病棟全体で見送るようにするとのこと。同じ病気の子にも隠さないそうです。穏やかに死を迎える場面に出会うことは、死への不安感をなくす働きをするからのようです。たしかに仲良しだった子が亡くなって、ショックを受ける子もいるけど「あなたには、まだまだ希望がある」と伝えるそうです。もっとも、そういうことができるようになったのはごく最近だそうです。
日本では、亡くなる子を同じ病気の子が見送るなんてことはありません。「せめて、仲良しだった子ぐらいにはお別れしてほしかった」と亡くなった子の親が願っても,ほとんど許されないようです。
ショックを受けた子を心理的に支える体制がないから,無理もないことですが・・・。
![]() トップ
トップ