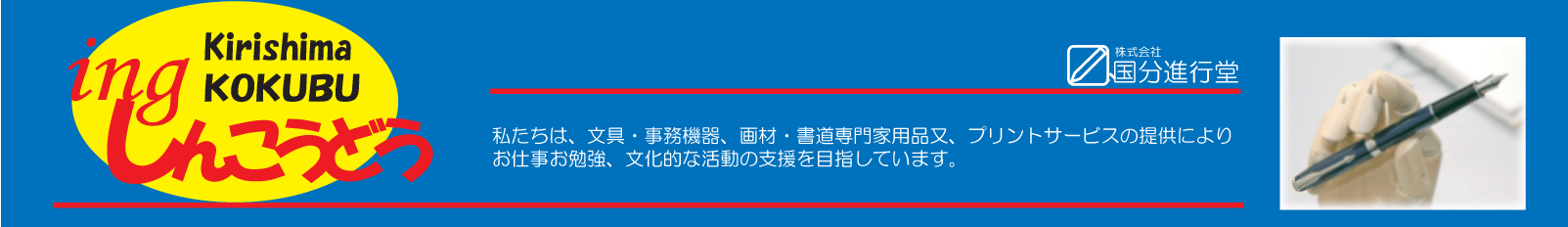2018年1月 第214号


明けましておめでとうございます。本年もモシターンきりしまご愛読のほど、よろしくお願い申し上げます。2000年4月スタート
の本誌も今年3月には18周年となります。編集者も40代から60代となり、話題も尽きるかと思われましたが、未だに取材先が枯れること
もなく、霧島地域の本当の豊かさはまだまだこれから現れるものだと信じております。
さて、多くの求道者がそうであるように、創作や修行を究める人々のこれで良いという地点は生涯をかけてつかんでいくもののようで
す。地域における遺跡や偉人の生かし方にしても、研究やその意義を体現し続けるリアルタイムな存在感こそが文化的地盤を作り出して
いくものでしょう。霧島市も都市としての文化のステージを意識しなければなりません。既存の、あれもこれもあるといった豊かさにか
まけているときではないのです。
県都への文化集中はどんどん進んでいきます。県下第2の都市を名実ともに目指すなら、文化的アベレージが上がって初めて都市と
言える、街並みが変わる、生活者の誇りが作られる、そういう地域であって欲しいものだと思います。
さて、新年早々前置きが長くなりましたが、今回の特集は、霧島市と少なからず関りを持つ三名の若手アーティストの取材をリレー形
式で掲載いたしました。三名とも昨年のコンクールなどで優秀な結果を残されて、これからの活躍が大いに期待される方々です。
彼らのアートに秘められた共感性は、きっとこれからの地域づくりに役割を果たしていくものだと思います。どうぞ三人三様の世界
を感じてみてください。
【日本画、濵田悠介氏-霧島の風景に回帰して】
インタビュー当日にはそれぞれの作品をデータで持ってきてもらった。濵田氏の作品を確認す ると、その中の1点に見覚えがある。少し前(平成13年)の霧島市美術展での受賞作(霧島市長賞) で「夕さりの空」という作品だった。その時は印象的な夕景の色彩と立ち木の細かな描写に気をと られていたが、背累の遠くにはビルやクレーンを配したちょうど霧島の市街地のような街並みが 描かれている。それは濵田氏が少年時代をすごしたこの地でこそ出合えた、技術と感性が融合した 世界だった。
松陽高校美術科に学んで
濵田氏は大口の生まれということだが、父親の仕事の関係で徳之島や加世田を経て、小学校3~
4年生のとき父の里の国分清水に家が建ち、中学までそこで過ごした。入学して美術部が創設され
ると、指導者だった武田信雄先生の下で鹿児島の美術界に触れることになる。
高校は県立の松陽高校に進んだ。特に美術以外に興味がなかったところに、松陽高校に美術科が
あるということを親伝いで知って、高校で美術ばかり出来るならとその道に進んだ。出来たばかり
の松陽高校の4期生だった。
高校の3年間はすごく楽しかったと語る。基礎的なもの、自分にたりなかったものが吸収できた
し、もうすでに自己表現のできる力のある上級生もいて、美術大学並みの設備とカリキュラムの中
で通常の高校では出会えない創作の経験を積むことができた。
「2年生になると絵画、彫刻、デザイン工芸の選択をすることになります。油絵に進むと漠然と
思っていましたが、日本画に進む生徒が少なく、先生に誘導されるうちにやってみようかと思うよう
になりました。洋画の手法とは違い、参考に示された作品、岩絵具などの画材、その手法に感動し興味
を引かれていきました。なかなか思うように使いこなせない材料でしたが逆にそこが面白くなって
いったのです。」
日本画画材の自然に任せて描く手法を覚えると、自分以上の力を日本画が引き出してくれる
と思えるようになった。高校生にして、描くという行為にかかる時間と日常を生きるという
こととがリンクしていくのを感じていたという。描くことは生活から切り離された趣味や楽
しみ事であるのが一般的だが、この高校の現場では早くも創作家的生き方の一つを若い心に
目覚めさせていたのだ。
大学時代の戸惑い
濵田氏は二浪したが2003年に武蔵野美術大学に進学した。すでに日本画の手法を身に
つけていた濵田氏だったが、彼が直面した悩みは、日本画科に入学してきた学生がはじめて日
本画に触れる人たちばかりだったことだった。
「ある程度高校時代で経験したことを横に置いて、東京に出て予備校に通い、受験のための
技術習得をやっていました。いつしか技術的なことが先立っていったのでしょうか、大学で多
くの学生が早々に自己表現へと先走るとそれに反発するような心が生まれました。もっと技
術を追究すべきで、自分と技術のマッチングの中で自己表現に向かうべきではないかと。東京
のように人の多い環境の中では、自分のこだわりを持ち続けるあまのじゃくな態度も必要と
しました。」
武蔵野美術大学では絹本に描く技術を研究し習得した。それからはずっと絹の魅力にとら
われ追求しているという。絹本はフラットだ。絹が薄い素材なのであまり厚塗りが出来ない。
絵の具で染色していくようにして描いていく。だから取り組み前に画題をしっかり決めてか
らかからなければならない。何をどう描くかを決めることが制作の半分を占めるという。
絹本に描かれた「夕さりの空」は国分に戻って制作をしており、霧島市の持つ空気感や光を絵
に込められないかと描いた作品だそうだ。

国分の田園風景を見つめながら
今回南日本美術展で海老原賞に輝いた作品も国分の田園を描いたものだった。最近の風景作品
は国分の田園風景が多いと言う。確かに遠景に姫城山の姿があったりしている。
「東京では人より上に行くための技術力にこだわって、現実を超えるものを表現しようとしてい
ました。ところが自分自身を見つめなおすきっかけが、私の原風景の中にありました。身近にある
ものとか、見過ごしてきたものの中に、はっとさせられるものがあることを知りました。私の得た
日本画美術の力でそういうものを表現したいと思ったのです。」
海老原賞に輝いた作品、題名は「8分前の光」。太陽から発せられた光が地表
を照らすまでに約8分の時間がかかるという。そのテーマと描出された輝く田
園風景の間で鑑賞者は何かとてつもないものと出合うのだ。130号という大
画面、この夕景の前に立っているあなたは何者でそれはどういうことなのかと。
「ぼくは国分からそれを感じて…個人的なものが人にも伝わり、また違った見
方もしてもらえる。その辺にアートの力というものを感じるのです。」
「大学の間はほとんど風景は描かなかったのです。鹿児島に帰ってから風
景を見る目が変わりました。空はすごく広く、海は広がり、どこにもない自
然がありました。その中で過ごしている人たちが日常見ている風景のすご
さが見えてきたのです。」
海老原賞の留学への期待を聞くと、美術しか知らない自分だが、その美術で世界の様々
なものと関係を持つことが出来ることの嬉しさを語ってくれた。明治期の留学生のよう
に、美術の力を信じている青年こそが持ち帰られる宝物に期待したい。
【彫刻、丸田多賀美さん―日常に宿る共感】
昨年4月2日「今日は一日モシターンの日」と銘打って、国分シビックセンター多目 的ホールに本誌関係者が一堂に会して発表会を開催した。上床利秋先生の第一幼児教 育短期大学(社会人講座)のグループもテラコッタ人形や彫刻の展示で参加頂いたが、 その中に丸田多賀美さんの作品「いい湯だよ」も展示されていた。ドラム缶風呂に浸っ て穏やかな顔でくつろぐ老人、その横で小枝を火にくべながらその様子を見上げる子 供。日常の情景に漂う優しさ、穏やかさ。着彩された彫刻から発せられるメッセージ。二 番めのインタビューは現在霧島市の第一高等学校・中学校、隼人工業高校で美術講師を 勤める丸田多賀美さんの取り組みである。
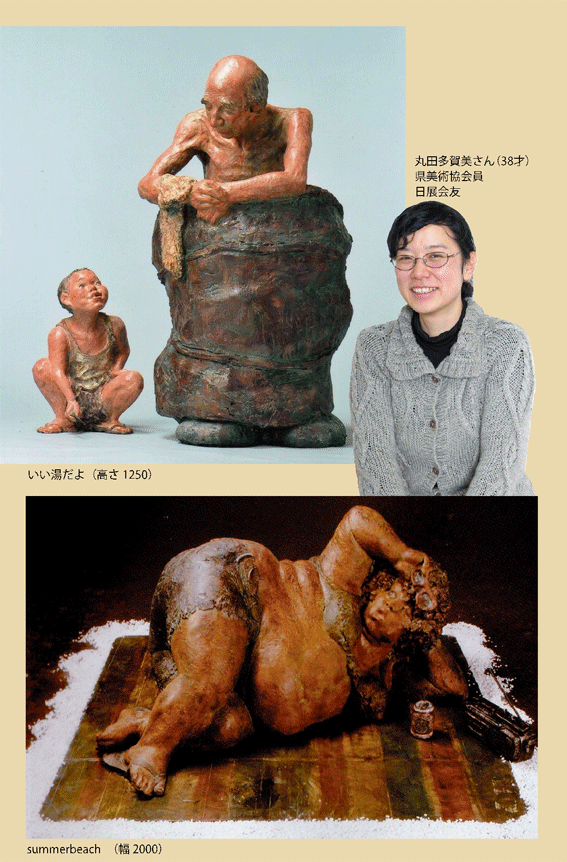
松陽高校第一期生となって
丸田さんは宮城県で生まれ、小学校時代は東京と横浜で育った。鹿児島に来たのは
父親の出身地ということで中学校のときだった。絵は好きだったが中学校に美術部は
なく、高校選びのとき美術科のある松陽高校が出来ることを知った。関東から来たという
地域ギャップもあったが、一人でいろいろすることの好きだった性格もあって、次第に美
術科以外は考えられなくなっていった。松陽高校の新設は時を得た出来事だった。
「普通の大人になって、働く社会人である自分に自信がなかったというか、社会になじ
んで行く自信が持てませんでした。松陽の第一期生として入学し、そのときの担任が本誌
の記事も執筆しておられる上床利秋先生でした。入学して最初は漠然と絵をやりたいと
考えていましたが、授業で首像を作ることがあったとき、楽しんで作れて、才能があるん
じゃない!と気楽に言ってもらえたことがきっかけで、彫刻の方へ進んでいき
ました。」
「彫刻ではみんなで型を取ったり心棒を立てたり、協力し合って作業
したりすることがあったのです。絵画は孤独な取り組みが多いのに比べ
て、彫刻の全体で行う作業を通して、偏屈な子供だった私が協調性を得て
いくことにもつながりました。」
県下から美術好きな子供が40人集まった情景を想像して欲しい。そこに
は様々なレベルの違いもあれば、こだわりや偏屈な性格を持つ生徒、素
直に先生の言う技術を身に付けていく生徒などいろいろだ。丸田さんは、
自分は不器用だなと感じていたら、先生から「不器用は才能だよ」といわ
れたという。「器用なヒトは壁が出来るとすぐあきらめたりするが、不器
用な人は長続きするし、作品に味も出る。だからお前には才能があると思うよ。」
上床先生のこの言葉がその後もずっと彼女のを支えてきた。
具象と抽象
鹿児島大学に進学すると、自由に個性を膨らませて置いてくれた松陽高校時代
と違い、技術の習得のための授業が始まった。
「コンセプトよりも技術中心となり、美しいプロポーションの男性、女性像の制作に、
頭の固い私は何が作りたかったのかまとめきれず、性格とか個性とかを廃した人の像、
裸婦像を作ることになじめませんでした。いつしか自分はそういう抽象的な人物は作れ
ないと思うようになり、話し方や暮らし向きなどモデルのコンセプトやイメージがない
と制作が出来ない性格だということがわかってきました。」
彫刻というと誰しも裸の人物の立像を自然に思い描くことが出来るだろう。そして
そこに清廉さや爽やかさ、孤独や孤高、といった観念的イメージを付していく。そう
いう作業を丸田さんは抽象的な表現という言葉で呼んだ。大学での制作はいやではな
かったが苦しさが伴った。一方で「お前の良さはそっちじゃない」と明確に言ってくれ
たのは、高校の担任だった上床先生だった。 ではその対極である具象というのはどう
いうことなのか。
「子供でも老人でも、太った人もやせた人も、突き詰めると自分の中にあるものの表
現、自刻像だと思っています。自分の中のものをモデルとなった人の姿を借りて表現
し、それが鑑賞する人とも共有、共感できるというところが具体的なのだと。優
美とか、崇高とかいった日常と離れているイメージだと共感がしにくく、それは抽象
的、概念的だと思うのです。」
日本人が彫刻の芸術表現に触れ始めてまだそう時が立っていない中で、西洋彫刻的
なもので自分を表現する感覚は、まだアカデミックに陥りやすく、この国の彫刻全体
がまだ勉強の途中なのではということもあるという。形や職人芸ではなく作者の感動
を伝えようとする気持ちがこもっているかどうか。創る側と観る側の共感、日常にある
人の姿の豊かさ、表現の自由さをテーマに話が続いた。
境遇を受け入れて楽しむ
母親をモデルにしたという太ぶととデフォルメされた女性が、ビーチで寝転がっ
たり、戯れる子供の下で昼寝していたり、洗濯物を干したり、バスを待っていたり、風呂上り
にテレビを見ていたり。汗じみた服をまとった作業員のちょっとした仕草、河馬を中心に動物
をテーマとしたもの、子供たちの一瞬の表情…作品にはそれぞれに着彩も施され、どう見ても
記念碑的な彫刻とは一線を画す。
「共感を得るには色もあった方がと思っています。技術優先の先生方からはいろいろと
いわれますが…。」だが昨年秋、改組第4回の日展で特選を受賞した作品「家族から」の、ス
マホを覗き込む工事現場のおっちゃんの像もしっかり着彩された像だった。写真でも絵
画でもなく、彫刻として日常から拾い出されて置かれた人物像。それは生きている様々で豊か
な人間を表象して見せてくれるのだ。市井のあちこちに空間とマッチして躍かれる、彫刻
の溢れる霧島市の姿を想った。
【染色、牧野美枝さん―自然素材から始まる空間造形】
3人目の登場は国分松木にお住まいの牧野美枝さん。結婚して二人の子供を育てるお
母さんアーティストだ。鹿児島の実家が創作の現場。そしてその作風はというと…
何の知識もなくて、今回初めて牧野さんの作品を見せていただいた瞬間、正直戸惑っ
た。染色家と聞いていたが一見それらしい物はない。広げられたうす布に絡みつく紐のよ
うなもの、小石のように盛られた繭、緻密に織り込まれた分厚い柱状の塊。鏡とマネキン
の置かれた空間でそれらは何を語ろうとするのだろう。

大やけどから始まった創作
謎を解くためには、牧野さんの生い立ちから始める方が良いと思った。
生まれは鹿児島市の緑ヶ丘。牧野さんの父親は県の工業試験場で大島紬の普及研究員
をされていた。繊維関係の研究者で、当時県産品として大いに注目されていた分野だっ
た。鹿児島大学に非常勤講師で派遣されたとき、家政科の学生だった女性と知り合い後に
結婚した。二人は繊維関連のことで息が合い、草木染めや機(はた)織りをともに研究しながら
子育てをした。母親の方はやがて鹿児島女子高の家政科の先生となったが、以来今日まで
女子高に在籍して染色の指導などをしながら、染色作家としての活動もされている。
家には一階の作業部屋(アトリエ)に機織り機、草木染めや絹糸や繭などが置かれてあ
り、そんな中で牧野さんは育った。
中学3年のとき、一人で料理をしていたところ誤って油を手にかけ大やけどを負った。
医者からはもしかしたら右手が動かないかもという診断を受けたが、そんな折、母親が
使っていた機織りを少しやってみると楽しくなり、手を動かす訓練にもなるということ
で興味が膨らんでいった。大やけどした右手は機織りへの意欲の中で動くようになって
いったのだ。
自由に思うように織ればいい
鹿児島中央高校に進学すると美術部に入った。そこで出会ったのが米田安希先生である。今
は退職されて、この地では霧島美術協会の会長や弊社の美術教室の講師などされている。「美
術には何も決まりやこうしなきゃならないということはない。自由に、自分が楽しいことをすれ
ば良い。」といわれたことが後押しし、美術部ではデッサンや美術の基礎をやりながら、家では
織ったり染めたりして創作を進めていった。
身の周りには材料がそろっていた。蓬(よもぎ)で染めた糸、茜(あかね)で染めた糸、糸の種類によって染まり方
も違い、それを絵の具のように引っ張り出して織っていく楽しみ。紬の柄などはそれこそ計算
しつくされた織り方をしなければならないが、母親(杉尾緑さん、染色家)は牧野さんにどこか
ハープを弾くような感覚で何の束縛もなく機を織らせてくれるのだった。
生きるカが運命的に作り出していくもの
大学は最初宮崎大学に進学した。そこで美術科に学びながら、大やけどの右手を回復させ自
分の未来を作ってくれた美術の力を障がいのある子供達のために生かせないかと、障がい者美
術、作業療法の分野を研究した。さらに鹿児島大学大学院に進み、そこでも知的障がい児に対
する美術教育の在り方などを研究した。
自分の大やけどを克服させてくれた創造的エネルギーという体験は、もう つ観点を創作の
中で育てていく。それは、南日本美術展の空間造形部門の応募コンセプトの中にあった。
「すべての生命に根付いているはずの『前向きな心』や『祈り』、自分を取り巻く環境にある蚕(かいこ)
の、わずか50日ほどの一生は、全身全霊で背負った運命を最大限に発揮しながら、たくましい生
命力で絹糸を吐き出し、美しさを共感させてくれる。」そのように、誰しもが自由に精一杯自分
を発揮すれば、きっと人々の共感を呼ぶ何かを作り出していけるのではと牧野さんは考えた。
障がいをもつ人でも命いっぱいの表現があり、それは共感を生むものであると。
絹糸を吐き出す蚕のように
話を聴いているうちにようやく提示された作品が編集者なりに見えてくる気がした。共感が
生じたのか。蚕が絹糸を吐き出しながら繭を形作っていくように、作者は塔のような、祈りの塊
のようなものを「紡ぎ出し」ながら表現しているということだ。時に編み物のように、時に鳥や昆
虫の巣作りのように、吐き出された形は命が背負う生きる力の結実として存在する。様々な形
となって跡を残す。まるで時間と命の曼茶羅だ。
その共感について、牧野さんは短い詩で語っている。…「織りは人生そのもの、長い経(たて)糸は私の
歩む一本の道、過去現在未来、その道に今日の私を緯(よこ)糸として残す、織り上げた布は『祈跡』そ
のものである」と。
その表現スタイルがついに改組第4回日展に入選を果たした。ジャンルにこだわらない表現は工
芸とはまた違ったオブジェとなって全国へ羽ばたくかもしれない。その背後に大島紬の研究や米田
先生の言葉や南日本美術展の自由な応募形態などがあったことを思うと実に楽しい気分になる。
地域が作家を生む…地域の中で才能はこうして育っていくものかもしれない。
牧野さんの人生の織物は、結婚して霧島在住10年を経て様々な職場で生かされつつあるようだ。
母親とのコラボ作品や個展や草木染めの教室、第一幼児教育短大や幼稚園、来年には牧之原養護学
校で働くことが決まっているらしい。障がいのある子供たちが何を生み出そうとするのか、その思い
の先を彼女はじっと見つめていることだろう。
今回の三人の若手創作家へのインタビューの間に、二つ大きな共通点を見出した。一つは三
人とも美術というものの力を信じていること。もう一つは作る人と観る人との間の共感がその
美術~芸術を生む創作の支えとなっていること。言い換えれば、創作する自分とそれが存在する
空間、鑑賞者を通した社会との関わリ(役割)まで彼らは考えているということだ。
鑑賞者にもパワーが必要だ。市民の中に共感力が育たなければ、若い芸術家のエネルギーも
発路を見失ってしまうかもしれない。要は、感動と出合ったとき、作者の思いに匹敵するような
スタンディングオベーションを恥ずかしがらずに送ってあげることだ。
未来を託す子供達の世代が、身近に美術の力に触れられる環境も必要だろう。若い才能を存
分に取り入れることの出来る霧島市であって欲しいと思った。
(文責/編集室)
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd