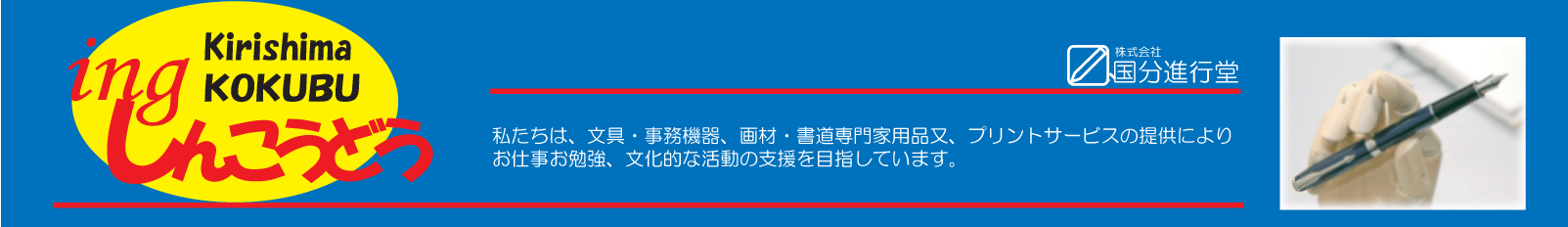

新シリーズ

俊寛と鬼界島
【鹿ケ谷の謀議】
武家として太政大臣にまで昇りつめた平清盛とその一族が、後白河上墨を頂点とする
旧来の貴族政権を凌駕(りょうが)して、勢力を増大しつつあった。
これに対し、権大納言の藤原成親(なりちか)・成経(なりつね)父
子、法勝寺執行(しゅぎょう)の僧俊寛(しゅんかん)・平康頼(やすより)・清和源氏
の多田行綱(ゆきつな)らが、京都鹿ヶ谷(ししがだに)(現、京都市左
京区)の俊寛の山荘に会合して、平氏打倒の謀議をはかっていた。
ところが、多田行綱はこの密議を平家側にもらしたため、陰謀が発覚したと『平家物語』
は伝えている。治承元年(二七七)五月のことである。
清盛は、成親や西光(さいこう:藤原師光)を捕え、処刑している。また、成経・康頼・俊寛は鬼界島
に流された。三人のうち、藤原成経・平康頼はやがて清盛の娘、建礼門(けんれいもん)院徳子(とくこ)懐妊慶事の
大赦(やいしゃ)によって召還されたが、俊寛は許されず、同島で死没したと伝えている。
その俊寛については、鹿児島市の西本願寺別院近くに、流されるときに船出したという
場所があって、「俊寛之碑」がたっている。
この一帯は、いまでは繁華街に近く、古い建物は高層に建て替えられることが多かった
が、その基礎工事をすると、地下から古い石垣の跡などがしばしば見つかるという。
筆者は、この石碑の道路向かいに古本屋があったことから、よく立ち寄っていたが、その
古本屋が建て替えられるときにも、地下から古い構築物が見つかったという話を聞いたこ
とがあった。また、一帯は古くは「俊寛堀」といわれ、明治の中期までは堀があったが、その後
埋め立てられたともいわれている。
いっぽう、鬼界島とはどこか、という疑問があろう。
この疑問に、いち早く答えを出したのは、音読みの島名が通じる奄美大島の喜界島で
はなかったかと思われる。それも島名による単なる話ではなく、出土遺物まで提示してい
たから、一応は説得されるものがあった。
鹿児島県三島村の硫黄島を支持する人びとの中には、この出土資料をあげての喜界島
説に唖然(あぜん)とした人があった。
筆者が喜界島で俊寛の銅像と、その横の説明板を見たのは三十年近く前であったと思
う。空港を出たすぐの所にあったので、目に付いた。説明板には出土遺物とそれを鑑定した
高名な学者の名が記されていた。この銅像と説明には、筆者は少々驚かされた。喜界島と
俊寛と結びつけることは、筆者には想定外のことであり、意外であった。
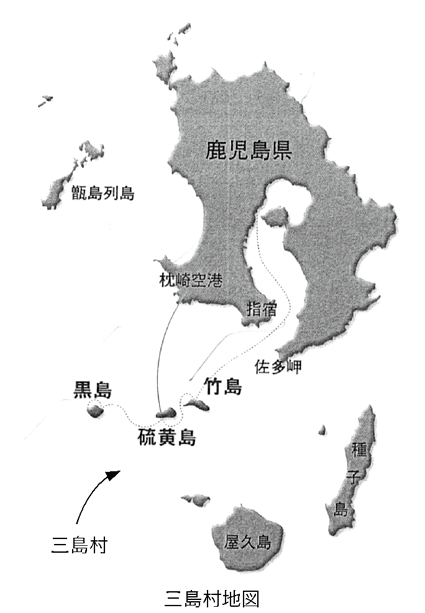
鬼界島を訪ねる
その後、筆者は硫黄島を二度訪ねた。
硫黄島は、薩摩半島南端の長崎鼻から遠望したことが何回かあったので、さほど遠い
所という感じはなかった。調べてみると、約四〇キロの距離だという。天気の良い日に硫
黄山の噴煙も見えたことがあったが、それは久しぶりの噴火で偶然であったらしい。
また、硫黄島の東に位置する竹島には、以前にも遣唐船の遭難場所の伝承を探して、
渡島したことがあったので、竹島から硫黄山を望見したこともあった。その間の距離は約
十五キロと聞いている。
さて、筆者が三島の硫黄島を「鬼界島」と考えたのは、『平家物語』の記述によっている。そ
の記述の一部を引用してみると、つぎのようである(一部省略)。
三人、薩摩潟(がた)鬼界が島へぞ流されける。彼の島は都を出てはるばると、浪路を しのいで行く所也。島のなかにはたかき山あり、とこしなえに火もゆ。硫黄と云 物みちみてり。かるがゆゑに硫黄が島とも名付たり。
この記述から見ると、薩摩潟(薩摩周辺の海)・高い山で火山・硫黄の産出・一名硫黄が
島などから、三島の硫黄島より他は考え付かなかったのであった。
したがって、奄美大島の喜界島に俊寛が流されたという説には、思いおよばなかっ
たのであった。
また、流人といえども、まったく支配外の地域に送致することは、歴史的には
考えにくいのであった。罪人は配流先でも監視下にあり、緩急(かんきゅう)の差はあっても、その
生活を拘束できる状況下にあった。その点でも、硫黄島は薩摩の南であっても、屋久島の
北であり、また穂子島の西に立地しており、その条件に一応はかなっていたといえよう。
なお、喜界島は近年になって、遺跡の発掘があい次いでいる。「城久(ぐすく)遺跡」は複数の遺跡
群からなり、東シナ海域の有力な交易拠点ではなかったかといわれ、また島南部の「崩(くず)リ遺
跡」では製鉄跡が確認されている。
前者では、古代~中世の中国・朝鮮半島の陶磁器や長崎(彼杵:そのき)半島産の滑石(かっせき)製品が出
土し、後者は十二世紀の遺跡で、本土並みの製鉄技術をもった集団の存在が認められ、さ
らに隣接地(川寺・中増遺跡)からは十三~十五世紀前半の、金を施した銅製贔や琥珀(こはく)
も見つかり注目されている。また最近、南島初の銅鏡が出土したともいう。しかしながら、
これらの遺跡の発見と、俊寛の配流とは別のことにして、それぞれに考えねばらないこと
である。
話を硫黄島にもどしたい。
筆者が史跡探訪するのは、長期の休暇のときが主であり、とりわけ夏休みが多い。硫黄
島も夏に訪ねた。鹿児島からの船の出航日時や島での宿泊所などについては、鹿児島にあ
る三島村役場で世話していただいた。
役場は三島村の現地にはなく、鹿児島市の海岸通りにあるから、面白い。役場の職員の
話だと、三つの島の、どの島に役場を置いても不便なのだという。それは、さらに南の十島村
も同じで、十島村役場も鹿児島市にある。
また、筆者が島に行くことは、現地のクチョウ(区長?)さんに連絡しておくので、
困ったことがあったら、何でも聞いてくれということであった。そのクチョウさんは、現地で
出迎えて下さり、また、各地を案内しても下さった。
昭和の終末、一九八八年ごろのことで、観光客はわずかで、民宿で出会った客はほどんど
釣客であった。各人お目当ての釣場があるようで、釣客仲間の話はにぎやかであった。
船が硫黄島港に近づくと、海面が黄色に染まったいたので、硫黄の溶け込んだようなこ
の海水では、生きものは棲めないだろう、と勝手に思っていたので、釣客が多いのは意外で
あった。釣客との同宿で、夜の食事は盛りあがったが、明朝は早く出立つということで、筆
者は一人とり残された。
クチョウさんには、二日間にわたり島中を案内していただいた。各所でくわしい説明を
聞いていると、どこまでが歴史で、どこからが伝説か、その間に一線を引くのがむつかしくな
るようであった。
島には、俊寛ばかりでなく、安徳(あんとく)天皇にまつわる伝説が色濃く伝えられている。この二
人は、対立的立場にある人物のはずであるが、ここでは共存して語られている。
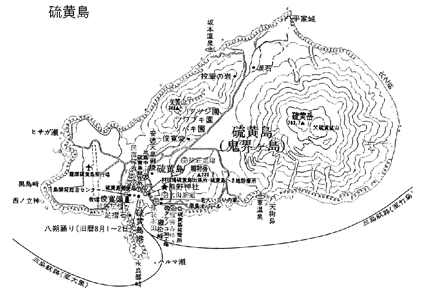
俊寛と安徳天皇
流人三人のうち、藤原成経と平康頼は赦免されたが、俊寛の名は赦文(ゆるしぶみ)になく、島に残
されることになった。
そして、いよいよ二人を乗せた船が出ようとすると、俊寛は船べりに取りすがり、自分
も乗せるようにせまった。そのようすを『平家物語』はつぎのように描写している。
取つき給へる手を引(ひき)のけて、舟をばつひに漕出(こぎいだ)す。僧都(俊寛)せん方なさに、 渚(なぎさ)にあがりたふれ臥(ふ)し、をさなき者の、乳母(めのと)や母なんどを慕(した)ふやうに足摺(あしずり)をし て、「是(これ)乗せてゆけ、具(ぐ)してゆけ」と、をめきさけべ共、漕(こ)ぎ行く舟の習(ないらい)にて、跡 は白浪ばかり也。いまだ遠からぬ舟なれ共、涙に暮(くれ)て見えざりければ、僧都たかき所に走りあがり、澳の方をぞまね きける。
その後、俊寛は許されることなく、失意のうちに、島で三七歳の短い生涯を閉じたとい
う。
村人は、その死を悼(いた)んでその住まいの庵(いおり)の跡に俊寛を祀ったが、現在は俊寛堂が建てら
れ、村人によって守られている。
俊寛の生涯の物語は、歌舞伎界の大御所中村勘九郎によって、硫黄島の現地で上演さ
れることになった。それも一座十三名の大挙しての上演で、しかも砂浜の舞台という、歌
舞伎界初の試みであった。
平成八年(一九九六)五月に上演された歌舞伎「俊寛」の観客は八〇〇名にものぼり、硫
黄島は人であふれかえった。
俊寛を勘九郎、成経を獅堂、康頼を勘之丞、御赦免の使者を助五郎・翫雀(かんじゃく)、成経に恋
い焦がれる島の娘千鳥に勘太郎という豪華メンバーの熱演に観客は感涙にむせぶ人が多
かったという。
勘九郎は、前年五月の「俊寛像」除幕式にも出席しており、その折に島の地形・地理を
勘案して、俊寛公演の舞台の場所・背景を構想したようである。なお、「俊寛像」はきわめ
て写実的に製作されており、一人島に取り残された俊寛のわびしい心情があふれ出ている
像である。
 歌舞伎では、『平家物語』に加筆、脚色された話の筋になっている。
歌舞伎では、『平家物語』に加筆、脚色された話の筋になっている。
じつは、歌舞伎では俊寛も他の二人とともに赦免され、三人とも本土に帰還することに
なった。ところが、俊寛は成経と祝言(しゅうげん)を済ませた島の娘千鳥も船に乗せるよう願い出る。
ところが赦免使は、乗船人数を理由に乗船を許可しなかった。そこで俊寛は自分の代
りに千鳥を乗せて、島から送り出す、という話になっている。
いずれにしても、俊寛は島に一人残されることになった。船べりに取りすがり足摺(あしずり)をし
たという岩、俊寛が泣きくずれたという涙石、俊寛が筆を投げて書いたという梵字が刻
まれた岩など、島には多くの伝説がいまに伝えられている。
安徳天皇の墓所
平清盛の娘、建礼門院徳子と高倉天皇の間に生まれた安徳天皇は、祖母の平時子に抱
かれて入水(じゅすい)した。文治元年(一一八五)三月、源義経に長門・壇之浦で平氏一門が討たれた時
で、天皇は八歳であった。
ところが、じつは安徳天皇はひそかに脱出し、硫黄島まで逃げのびたという。その後、帝
は資盛(すけもり)の娘を后として、皇子(隆盛親王)が誕生、寛元元年(一二四三)六六歳で波乱の生
涯をとじたという。
この安徳天皇をめぐる話は、伝説とばかりにはいいきれないところがあるので、その後日
談も少し記しておきたい。
というのは、硫黄島には安徳天皇の墓所が現在も伝えられており、子孫である長濱家の
人びとによって大切に祀られている。また、長濱家には多くの資料が伝えられているとい
う。
江戸時代の文政十年(一八二七)、薩摩藩主・島津斉興(なりおき)は硫黄島に資料調査のための使
者を派遣している。使者の五代直左衛門が持ち帰った硫黄大権現宮の神体、神刀・古鏡な
どに藩の学者たちも驚いたという。
斉興は、古鏡は離島に置くべきではないとして預かり、別の鏡をいれた「明けずの箱」と、
島津の定紋を打ったカブトを奉納した。また、硫黄権現宮を修復し、御前(ごぜん)山にある安徳
天皇墓所と従臣の墓を竹垣で囲い、それぞれに墓碑銘を建てさせた。長濱家は、いまも島
の神官を務め、島では高貴な家系として崇敬されているという。

竹島のコモリ港
三島のうち、筆者がはじめて上陸したのは竹島であった。いまから三五年くらい前のこ
とである。
そのきっかけは、『日本書紀』に遭難した遣唐船の乗員五人が、「胸に一板をつなぎて竹島
に流れ遇(あ)ふ」の記事があったからである。遭難の場所は、「薩麻之曲(くま)、竹嶋之間」とあるの
で、三島村の竹島とほぼ推定できる。
白雉(はくち)四年(六五三)七月のことである。かれらは、「竹を採(き)りて筏(いかだ)と為し、神嶋に泊る。凡(すべ)
てこの五人、六日六夜まったく食飯せず」して、無事帰還したのであった。
この記事の内容を、実検してみたいという興味からであった。幸いに、竹島在住の古老か
ら、その遭難、漂着の場所の伝承地が存在することを聞いた先学から、現地に行って尋ね
てみたらと勧められたことが、きっかけであった。
思い立って、便船が筆者の休日に合うことを知って、竹島へ行ったのであった。日程の都
合で、この時は竹島一島だけの旅であったが、薩摩半島からさほど遠くない島の環境や島
民の生活に、筆者は衝撃を受けた。
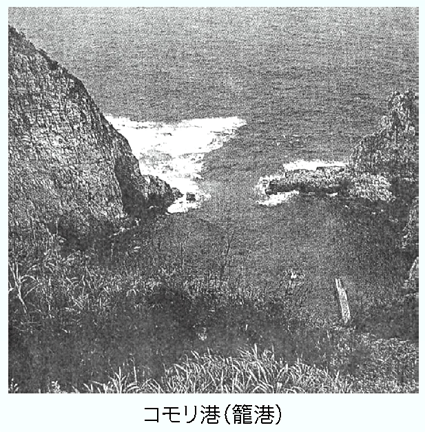 島は、一面竹ばかりであった。それも物干し竿程度の太さで、高さ三~四メートルの竹で
ある。「ダイミョウ竹」とか「リュウキュウ竹」と呼ばれ、しばしば本土に積み出されて竹材
として利用されるが、船には積載量に制限があるので、多くは積めないという。また。竹の
子は美味で、人びとに好まれているという。
島は、一面竹ばかりであった。それも物干し竿程度の太さで、高さ三~四メートルの竹で
ある。「ダイミョウ竹」とか「リュウキュウ竹」と呼ばれ、しばしば本土に積み出されて竹材
として利用されるが、船には積載量に制限があるので、多くは積めないという。また。竹の
子は美味で、人びとに好まれているという。
古老に案内してもらい、遣唐船漂着の伝承地を尋ねたが、古老は片手に大型の鎌を持
ち、行く手をはばむ竹を切り払いながらの探索であった。しばらく進むと、小さな祠(ほこら)が現
われた。古老はひとり言のように、竹の成長が早いので祠への道がわからなくなる、との意
の言を発していた。この小さな祠が、難破した遣唐船の乗員の霊を慰めるために建てられ
たものだという。
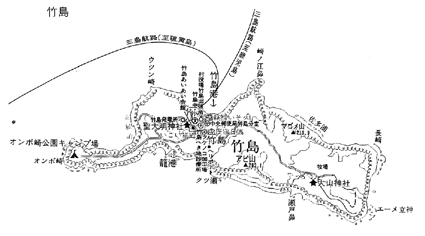 つぎに、五人の乗員が漂着したという、港に案内してもらった。その港は、崖の下にあっ
た。数十メートルの岩崖の下で、筆者は上からのぞき見るだけで肝を潰す思いであった、
コモリ港(「籠港」とも表記)という。港とは名ばかりで、岩に囲まれた小さな入り江で
あった。筆者が上陸した竹島港は、島の北側で、コモリ港は南側である。北風の強いとき
は、コモリ港を利用することがあるという。
つぎに、五人の乗員が漂着したという、港に案内してもらった。その港は、崖の下にあっ
た。数十メートルの岩崖の下で、筆者は上からのぞき見るだけで肝を潰す思いであった、
コモリ港(「籠港」とも表記)という。港とは名ばかりで、岩に囲まれた小さな入り江で
あった。筆者が上陸した竹島港は、島の北側で、コモリ港は南側である。北風の強いとき
は、コモリ港を利用することがあるという。
そのときは、ハシゴ・縄バシゴで上まで登るという。聞くだけでゾッとした。竹島は竹ばか
りでなく、岩の島でもあり、波打ち際まで石ばかりで砂がない。波打際には小岩・小石がゴ
ロゴロしている。
案内していただいた古老は、ケントウシが漂着した話は聞いて知っているが、自分は字
が読めないので、本を読んだり、詳しいことを調べたことはない、ということだった。
古老の話では、竹島で学校が始まったのは「昭和五年」だという。それで、自分は学校に
は行っていないという。筆者は、全国で学校制度が始まったのは「明治五年」だから、古老は
昭和と明治をまちがっている、と単純に思っていた。
以前に、奄美群島や沖縄に行った時にも、学校制度が遅延したという、そんな話は聞
いていないし、奄美・沖縄の明治生まれの人とは年賀状を交換してもいた。ところが、後
になって知ったことであるが、三島で学校が始まったのは、古老のいう通り「昭和五年」で
あった。学校制度は、三島村(十島村も)を忘れたかのように、実施されていなかったので
あった。
古老は、大東亜戦争が終ったことも、数カ月は知らなかったという話もした。終戦前後
のほぼ一年間は、本土との通信も、連絡船の往来もなく、空襲におびえた生活が続いたと
いう。その古老は、それから五~六年後に筆者が再び竹島を訪ねたときには、亡くなって
いた。もっと話を聞きたかったのであったが。
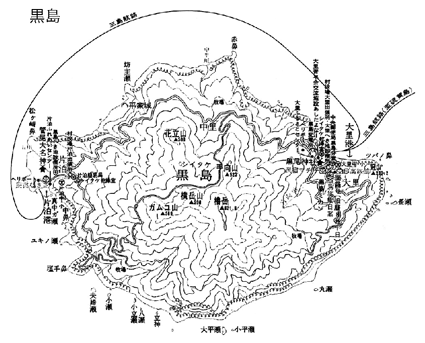
人びとはいつから島に
文明から取り残されたような三島。この島々をめぐり、住民の生活を実見し、体験し
たりしていると、ある懐かしさが筆者の身体の底から湧いてくる感じがしてくる。
筆者の父祖の代、もう少し前の昔には、水道もなく、電気もなく、もちろん家には電話
もなかった。そんなに遡(さかのぼ)らなくても、記憶に残っている小学生時代から振り返っても、火
鉢・炭コタツ・湯タンポが暖房であり、ウチワが唯一の冷房具であった。はきものは下駄で
あり、店にはワラぞうりも売っていた。
そのワラぞうりを作る店のおばさんの作業がおもしろく、学校帰りに友だちとしゃが
み込んで、その作業の手順を、何度か見た。ワラを槌(つち)でたたき、縄をなう、両足の先に縄を
かけ、ぞうりを編んでいくのである。家に帰って、縄をなう真似をしてみたのであったが、う
まくできず、放り出してしまった。そんな思い出が、いまも蘇(よみがえ)る。
この三島に、いつから人が住みはじめ、どんな生活をしたのだろうか、それが疑聞であっ
たが、黒島の大里(おおざと)でその痕跡の一端に接することができた。
どの島でも、学校が文化センターの役割を果たしているので、ここでも大里小・中学校を
訪ねたら、学校近辺で採集された石器類を見せていただくことができた。磨製石斧(せきふ)がほと
んどで十数個あり、縄文時代から人が住んでいたことが確認できたが、筆者の鑑識眼では、
それ以上の詳しい判定は無理であった。
黒島の中心部には、五~六〇〇メートルの山がいくつかあり、大里と片泊の(かたどまり)二つの集落
間を往復した筆者には、そこはまさに縄文的風土であった。黒島は、ほかの二島とは異なる
景観で、縄文人にとっては好環境であったようである。
なお、鹿ヶ谷事件をめぐる流人たちの、南部九州と硫黄島間の陸路・海路については、 長門(ながと)本『平家物語』の記述によるルートが解明されてきており、本誌にもかつて絵図入り で紹介されている。参考になるので一読をおすすめしたい。
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd