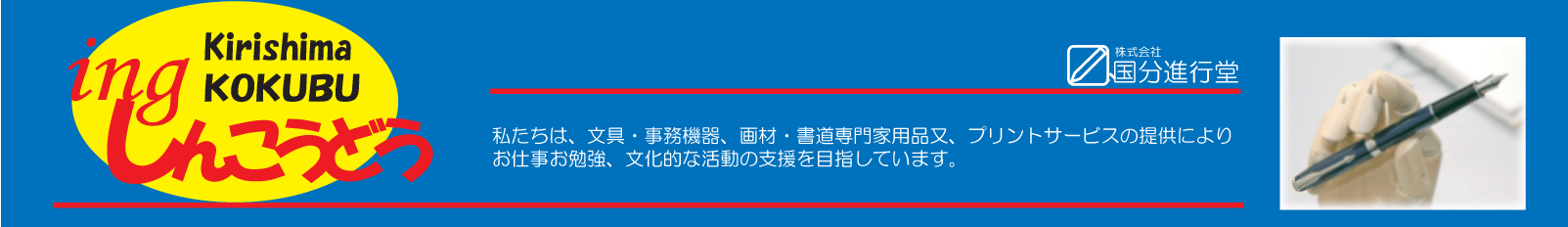

新シリーズ

火山は語る②、黒井峯のムラ
黒井峯(くろいみね)。聞いたことのない地名であろうか。
じつは、火山噴出物でムラがそのまま封印された群馬県の遺跡名である。関東
の知人から、そのニュース速報が筆者に伝えられたので、春休みでもあったから、気
軽に観察に出かけた。
現地に行ってみて、驚いた。噴出物の下から古代の集落がそのまま姿を現して
いたのである。火山の多い日本列島内でも、このような遺構の出土は前例がなく、
火山と共生している南部九州の人びとにも、ぜひ見てもらいたいという思いがつ
のった。
【火山灰のタイムカプセル】
黒井峯遺跡をじっくり見学させていただいた数日後、筆者は鹿児島に帰り、鹿児
島の人びとにこの遺跡を見て欲しいと思い、まずは南日本新聞社文化部のN記者
に、ぜひ現地で取材して報道するように電話でお願いした。一九八八年三月のこと
である。<br />
しかし、取材先が群馬県となると容易には日程がとれないらしく、とりあえず
東京の支社に依頼するとの返答であった。
ところが、やがて東京支社でも数週間後になる予定だという話になり、ついには
筆者に書いてくれということになった。
当方も新学年度が始まり、気分的に落ちつかない時期であったが、まあ何とかな
るだろう、と引き受けることになってしまった。そして、一九八八年(昭和六三)四
月十一日付の記事になった。三回ぐらい書いたら終る予定で、一回につき、原稿四
枚(一六〇〇字)程度、写真か図版一枚と聞いたので、各回の大筋を立てたのであっ
た。
ところが、読者からの反響があったらしく、もっと続けてくれるように、とのN
記者からの要請が寄せられた。そして、結果的には五月九日までの約一月間にわた
り十回の連載となった。
その連載に、新聞社がつけたタイトルが「火山灰のタイムカプセルー黒井峯に古
代のムラを探るー」であった。その連載は、地元の読者の反響だけでなく、月刊で全
国の発掘情報を速報する専門雑誌『文化財発掘出土情報』(ジャパン通信社)が同
年六月号で、十回にわたる全文をそのまま載せることにもなった。
筆者としては恐縮し、汗顔の至りであった。地元の群馬県や黒井峯の発掘担
当者をさしおいて、なぜ鹿児島在住の、しかも門外漢が書いた見学記が全国版にま
でなるのか。「なぜ」という思いがつのるばかりであった。
ところが、南日本新聞社が現地に届けた新聞記事に対して、現地からは、黒井峯
の発掘調査状況をよくぞ取りあげてくれた、という謝意の手紙が新聞社に寄せら
れたのである。筆者としては、とまどいながらも何とか十回までこぎつけたしだい
であった。
その新聞連載の第一回分を、ここにそのまま再掲し、それ以後の内容については、
この遺跡が火山に囲まれた南部九州の住民に何を教示しているのかを、学びとる
よすがにでもなればと願っているところである。(なお、地名などはすべて発表当
時のままである。)
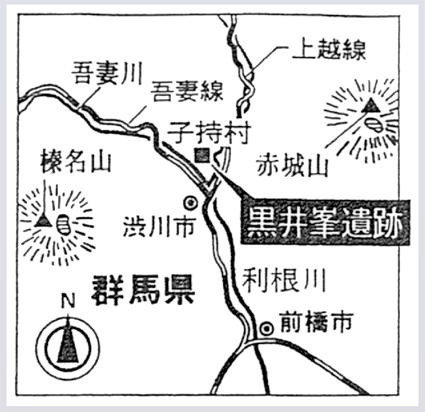
およそ千四百年前のある日、群馬県の榛名山(はるなさん)が突如火
を噴いた。すそ野にあったムラの住民が、どこに逃げ去ったか、今では知
りようがない。が、わずか数時間のうちに軽石や火山灰で封印された集
落を掘り出してみると、大隅一帯の火山灰土から近年出土した遺跡と
様式、構成が似た住まいをはじめ、垣根や道、水場、畠、牛小屋など、古
代人の息づかいまで聞こえてきそうな遺構が姿を現した。規模、保存状
態とも現代考古学の記念碑とされる登呂遺跡(弥生後期・静岡県)を
しのぎ、古代史のナゾを解く鍵(かぎ)として脚光を浴びている黒井峯
遺跡(子持村)。今後の総合的調査に備え埋め戻し作業に入った三月末、
現地を訪ねた中村明蔵教授に報告してもらった。
子持村は、北群馬部に属する。村といっても人ロ一万二千人余で、その
名の通り人口も増加しつつあるという。
村名は、北部にある子持山に由来し、「万葉集」(巻十四・三四九四)にも
「児毛知夜麻(こもちやま)・・・」とよまれており、古くからモミジの名
所として知られていたことがその歌からわかる。その子持山の南側すそ
野一帯に村は位置する。
村の南には利根川と吾妻(あずま)川の合流点があり、東方に赤城(あかぎ)山系、南西
に榛名山系が遠望でき、景観にすぐれている。
黒井峯(土地の人はクレイミネという)遺跡は吾妻川に面した河岸
段丘上にある。台地状をなし海抜二五〇メートルと聞いたが、村の中
心地がすぐ近くに見え、遺跡地内には子持中学校もあって、それほどの
高さは感じなかった。
遺跡地は、およそ十七万平方メートルと推定されている。うち、発掘
したのは三万平方メートル余りであり、本格的調査を開始してから三
年間にわたる集計であるから、未調査地域がまだ広く残っている。なお、
黒井峯とは小字名からとった遺跡名であるが、付近には、押手遺跡・西
組遺跡などと呼ばれる遺跡もあり、いまは「黒井峯遺跡」をその総称と
して話をすすめたい。
ところで、私は渋川市から子持村に行く途中で吾妻川にかかる橋を
渡り、車の中から川岸のそそり立つような崖(がけ)を見たとき、鹿児島
のシラス台地の崖を見ている思いであった。少し違っているのは、地層を
形成している粒子の粗いことと、帯状に黄褐色の層が走っていることで
ある。遠くから眺めていることなので細かい観測はできないが、火山噴
出物の堆積層であろうかと思いながら車で通り去った。
遺跡一帯は現在民有地で、ほとんどがコンニャク芋の畠である。コン
ニャク芋は、排水性があり適度に湿気を含む土壌が栽培適地で、この一
帯の地質に合うらしい。その栽培の休閑期間にあたる冬期には、畠の地
下にある軽石を採取する。軽石は建材の軽量ブロックの製造や、砕いて
グラウンド・ゴルフ場などの下地として使用されるそうで、かなりの需
要があるという。
かつて上州(じょうしゅう:群馬県)名物といえば、「かかあ天下にからっ風」といわ
れた。その「かかあ天下」の背景には女性労働力を必要とする養蚕があ
ると聞かされてきたのであるが、この一帯ではコンニャク芋が優先して
いる。
じつは、そのコンニャク芋の栽培の休閑期間に行われる軽石採取が
遺跡発見のきっかけとなった。軽石下から大小の凹地が確認されたの
である。昭和五十七年三月のことであった。その後の三年間は、軽石未
採堀地八万平方メートルにわたる地下レーダー探査が実施された。
地下レーダー探査というのは、地下に電磁波を送信し、土質境界や
地中の異物での反射を利用したも
ので、その結果、竪穴式住居の凹地百十カ所を確認している。
それにしても、畑地所有者、軽石採取業者の協力による長期にわた
る広域の予備調査と、厳冬期の雪と寒風のもとでの研究者の労苦がな
ければ、この遺跡は消え去っていたであろう。
【噴火は、突然に】
六世紀後半の晩春から初夏のころの、昼間のことであった。
突然のごう音と地響きに、人ぴとは襲われた。榛名山のニツ岳の爆発で、噴出物
が天空高く吹き上げるのが見えた。黒井峯の集落は、ニツ岳の北東約十キロの所
にある。
空はたちまちのうちに暗くなり、稲光が何本も走った。不気味な地鳴りで地面
が割れそうであった。
子供たちは泣き叫び、畑に出ていた人はわが家へ走った。水場にいた女性は、水
がめを投げ出し、かけ出した。家畜小屋の牛や馬は、狂ったように鳴き声をあげて
いる。
やがて、暗黒の空から雹(ひょう)が降るように軽石の礫(つぶて)が落ちてきた。礫は見る見るう
ちに、地面や畑をおおい、家を沈めていった。
母親は幼児を抱き、子供の手を引き、頭からムシロをかぶってムラの高台へ急い
だ。父親は食料を土器に押し入れ、妻子のあとを迫った。
ムラの高台にほぼ全員が集まったのを確認し、ムラの長老が避難する場所を指
示し、人びとは長老のあとに続いた。長老は五十年ほど前に起こった噴火の際の体
験から、いち早く避難場所を判断し、そこに人ぴとを誘導したのであった。
降下した軽石は余熱があり、地面に足をしっかり着けられない。そのうえゴロゴ
ロして歩きにくい。上空からは、たえまなくこぶしほどの、ときには人の頭ほどの軽
石が降ってくる。
人びとは、長老の誘導によって、ムラのほどんどの住民は何とか逃げおおせたよ
うである。それでも、何人かの負傷者は出た。
これより半世紀前にも、ニツ岳の噴火で、吾妻川の対岸の集落が壊滅している。
そのときは火砕流が襲い、多くの死傷者が出たようで、逃げ遅れた住民の遺体ら
しい脂肪痕がいくつも見つかっている。
ところが、今回の黒井峯の発掘調査では、降下軽石層はニメートルの層をなして
いるが、人体の痕跡らしいものは出土していない。発掘地域に限定すれば、人びとは
全員逃げ出したとみられる。
ニツ岳は、その名の通り二つの山が連なったような形をし、高さは一、三四ニ
メートル。桜島よりは二〇〇メートル余り高い。
 しかし、それが六世紀の爆発前の山と同じ姿ではないであろう。爆発で噴き出
した軽石礫(れき)は高温であったが、落下にともなってしだいに低温となり、黒井峯に到
達する時点では、発火をさそう高熱はなかったようである。
しかし、それが六世紀の爆発前の山と同じ姿ではないであろう。爆発で噴き出
した軽石礫(れき)は高温であったが、落下にともなってしだいに低温となり、黒井峯に到
達する時点では、発火をさそう高熱はなかったようである。
それでも、このときの軽石粒が東北の仙台市付近まで分布していることが確認
されているので、わずか十キロしか離れていない黒井峯一帯がすさまじい状況を呈
していたことは、想像にかたくない。
軽石はたちまちに地面をおおい、数時間のうちに黒井峯の集落をかくすほどに
なった。建物の屋根に落ちた軽石は、すぐには屋根をつぶさず、屋根の勾配(こうばい)にした
がって軒下に落ちた。したがって、軒下に積もった状況から屋根の形が推測でき、
復元できる。
たとえば、切妻(きりづま)屋根の場合には軽石は二方向に流れ落ち、寄棟(よせむね)屋根の場合は軽
石は四方向に流れ落ちることになる。そのようにして軒下に堆積(たいせき)した軽石が屋根
の高さに達すると、つぎには屋根に堆積し、その重みで屋根がおしつぶされること
になる。
その間には、軒下に積もった軽石の圧力が建物の壁にも加わり、壁が破れて軽
石が建物の内部に流入することになる。
このような状況を予測した上で発掘をすすめると、屋根の形、壁の素材と構造、さ
らには床面のようすまで、かなり具体的に解明可能である。
現に、黒井峯遺跡の軽石断面層では、おしつぶされた屋根のようす
を的確におさえており、その落ち込みの状況から慎重に発掘作業をす
すめ、建物の復元に成功している。
筆者が子持村を訪ねたとき、応待してくれたのは、社会教育主事の石井克己さ
んで、発掘を担当した中心人物であった。
 予告なしに役場に行ったのであったが、石井さんは懇切に現場で説明して下さり、
また筆者の質問にもわかりやすくお答えいただき、感謝している。
予告なしに役場に行ったのであったが、石井さんは懇切に現場で説明して下さり、
また筆者の質問にもわかりやすくお答えいただき、感謝している。
その石井さんの話の中で、この小さな遺跡でも、一九二三年の関東大震災と同
じ様なことが起こったようです、と興味のある話を聞いた。それは建物を復元して
わかったのであるが、三棟が火災で焼けていた、というのである。
おそらくは、屋内にあったカマドの火による火災で、消失してから避難する、とい
う災害時の気くばりができなかったのではないか、との推測であった。突発的災害
時では、やはり命が先か。
【水田より畑が優位】
黒井峯遺跡では、畑があちこちで掘り出されていた。大・小さまざまである。広
いものは一反歩(約三百坪)近くもある。
よく耕されていたらしく、畝(うね)の立てかたもみごとで、現代の畑の景観と見まごうよ
うであった。
畑に対し、水田はわずかしか見つかっていない。石井さんの話では、「水田は畑の五
分の一程度ですよ」とのことであった。大陸から稲作文化が伝来した弥生時代以
降、日本列島は稲作優位の農耕社会に一変したように語られるが、地域によっては
六世紀になっても畑と水田がこの程度の割合でしかなかったことを、再発見したの
であつた。
「再発見」というのは、筆者は大隅・薩摩両国の古代では、稲作の痕跡はあって
も、稲作が広域にわたって普及したことは認めがたいことを主張してきたので、わ
が意を得たりの感じであったからである。
それも、同じく火山と共生した両地域性の類似を、石井さんから示唆されたか
らであった。
 発掘された畑は、その形態から三種類に区分されるという。畝を立てず土壌の
撹搾(かくはん)のみのもの、傾斜にそって縦畝を作っているもの、碁盤(ごばん)目状に畝を立てたもの
などである。このような各形態が何によるものかも考える必要がある。
発掘された畑は、その形態から三種類に区分されるという。畝を立てず土壌の
撹搾(かくはん)のみのもの、傾斜にそって縦畝を作っているもの、碁盤(ごばん)目状に畝を立てたもの
などである。このような各形態が何によるものかも考える必要がある。
その要因の一つは、耕作される作物の種類との関連である。遺跡からは、これまで
アズキ・アワ・ヒエ・ヒョウタン・アサ・イネ・ハトムギなどの種が検出されている。植物
の種類の知識に乏しい筆者は、最近出土したというハトムギを見せられても、対応
できるような質問はできなかった。
ところが、ハトムギは熱帯アジア原産で、その伝来はかなり後世と考えられて
いたが、黒井峯からの出土によって、その伝来時期の修正が必要になったという。
六世紀後半の黒井峯のムラの火山性土壌における畑の形態や作物の種類など
は、同じ火山性土壌で畑地の多い南部九州の古代農業を考えるとき、大いに参考
になる資料である。
黒井峯遺跡の一角から、ムラの祭祀(さいし)遺跡が見つかっている。通用道路がT字に交
差した場所や、道の両側に1メートルほどの土盛りをした場所で、土師器(はじき)の圷(つき)類・
管玉(くすだま)類・須恵器(すえき)の圷や甕(かめ)類などが置かれ
ていた。
 南部九州から沖縄諸島にかけては、T字路に「石敢當(せっかんとう)」を立てて邪霊を排除する
魔よけの習俗があり、いまでもそのような石碑を見かけることがある。黒井峯と
いう、南部九州とはかけ離れた所でも、石碑はないものの、同じような精神構造
や宗教的習俗が存在していたことは注目すべきことであった。
南部九州から沖縄諸島にかけては、T字路に「石敢當(せっかんとう)」を立てて邪霊を排除する
魔よけの習俗があり、いまでもそのような石碑を見かけることがある。黒井峯と
いう、南部九州とはかけ離れた所でも、石碑はないものの、同じような精神構造
や宗教的習俗が存在していたことは注目すべきことであった。
筆者は、古代隼人が邪霊を払うために吠声(はいせい)をいう、犬の吠(ほ)え声を発するときの
ようすを思い出してもいた。隼人は天皇の行幸の供をすることになっていたが、行幸
が「山川・道路之曲(まがり)」にいたると、行列の先頭に出て、邪霊を排除する先払(さきばR)いの吠声
を発していた。その吠声とも通じる思考形態であり、習俗である。
【大規模な一戸構成】
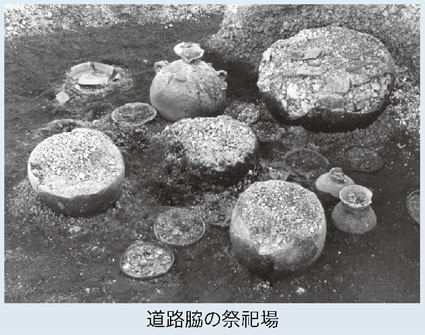 黒井峯遺跡の発掘担当の中心であった石井さんは、古代家族の「一戸」構成を復
元していた。
黒井峯遺跡の発掘担当の中心であった石井さんは、古代家族の「一戸」構成を復
元していた。
筆者は、これまで正倉院文書に残存し、そこに記載されている戸籍の大家族構成
の具体像を画くことは困難であった。一戸の人数が二十名とか、それ以上になるこ
とは珍くない。ところが、各地で掘り出される竪穴住居では、せいぜい四~五人し
か生活できない広さである。したがって、一戸は竪穴住居が五軒前後集合して構成
されているのであろうと、その程度しか想像してなかった。
石井さんは、その「一戸」の古代大家族の一例を具体的に浮び上がらせたのであっ
た。石井さんが作成した一戸には、平地式住居・縦(竪)穴住居のほか高床式建物
(倉庫か)・納屋・家畜小屋・作業広場・畑のほか、周囲には柴垣がめぐらされてい
た。この復元からみると、大家族が結構生活を楽しんでいたと思われる。
伝存している正倉院文書の戸籍では、養老五年(七二一)の下総(しもふさ)国大嶋郷(現・東
京都東部)の場合で、一戸平均約二四人であるから、それぐらいは生活できるとい
う。
学生時代の講義では、いまでいう従兄弟(従姉妹)ぐらいまで、一つの家族とみな
され、一人の戸主のもとで戸籍が編成されていると聞かされた。また、東国では後進
的で保守的傾向が強く、それが家族構成に反映している、との研究論文があるこ
とも知らされた。
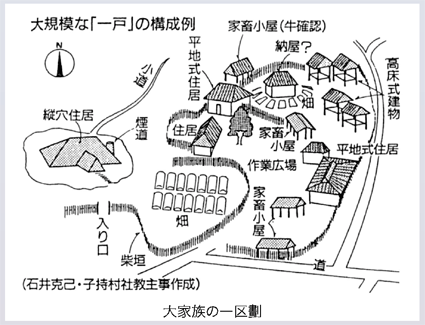 しかし、後年になって筆者が西国九州の豊前国(大分・福岡両県域)などの戸籍
を調べても、一戸の大家族数などにおいては、さほどの違いはなかった。
しかし、後年になって筆者が西国九州の豊前国(大分・福岡両県域)などの戸籍
を調べても、一戸の大家族数などにおいては、さほどの違いはなかった。
いっぽうで、八世紀に筑前国(福岡県)の守であった山上憶良(やまのうえおくら)は、『万葉集』の「貧
窮問答歌」(巻五・八九二)で、農民の生活の惨状を「伏(ふ)せ盧(いほ)の曲げ慮の内に直土(ひたつち)
にわら解き敷きて父母は枕の方に妻子どもは足の方に囲みゐて憂(うれ)ひさまよひかまどには火気(ほけ)吹き立てず・・・」と長
歌を詠(よ)んでいるが、そこには地域性として一概に論じられない、さまざまな農民の
生活が映し出されているようである。
それにしても、生活を楽しんでいるように見えた黒井峯のムラは、火山の噴火の 猛威には何らの抗(あらが)いもできず、数時間のうちにたちまちに消え失せてしまった。
Copyright(C)KokubuShinkodo.Ltd